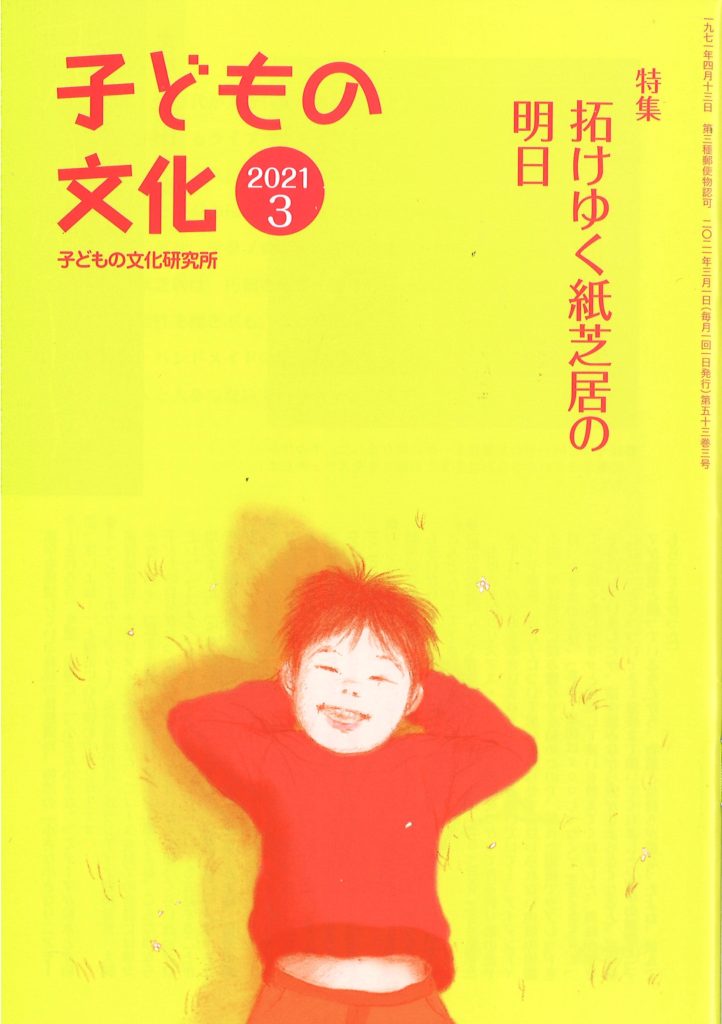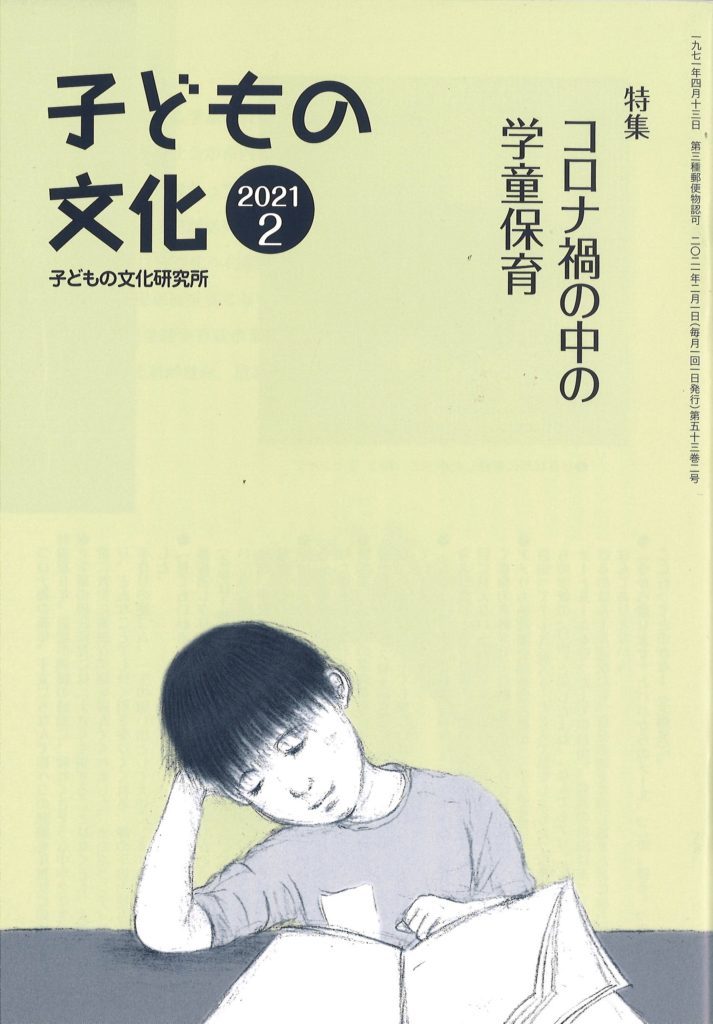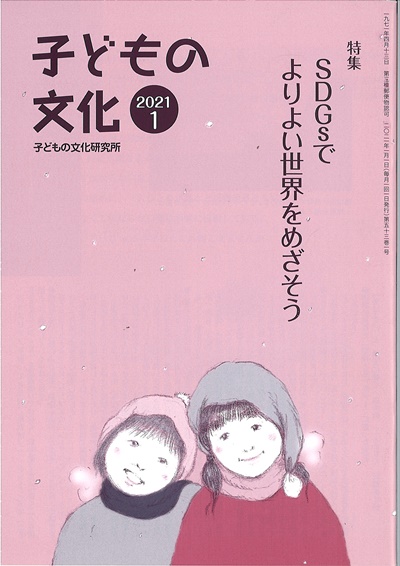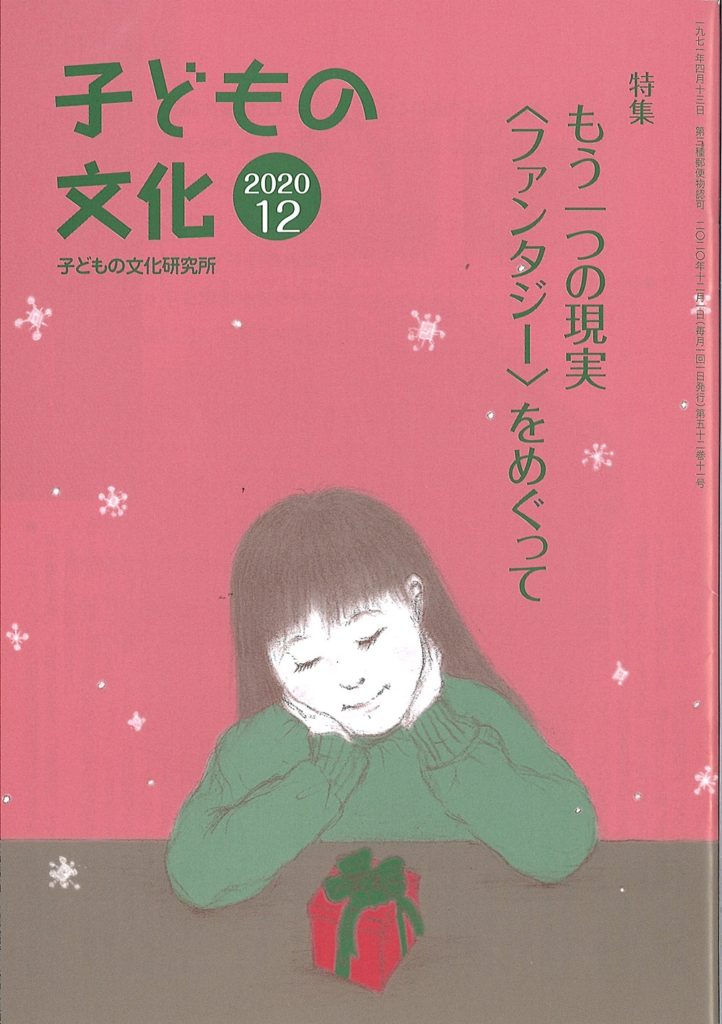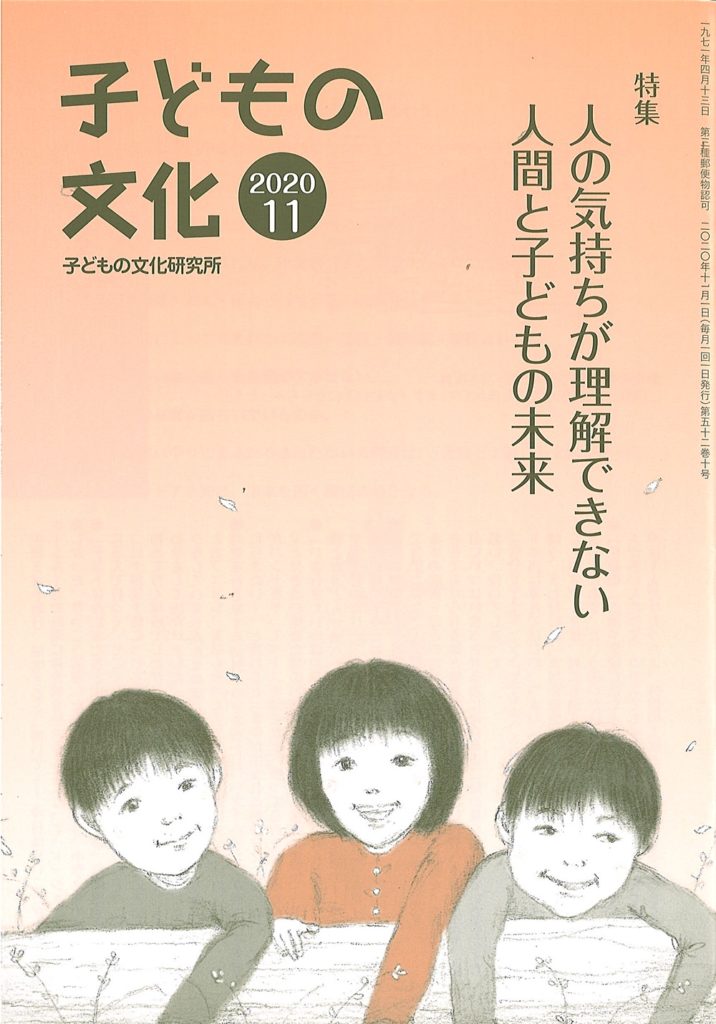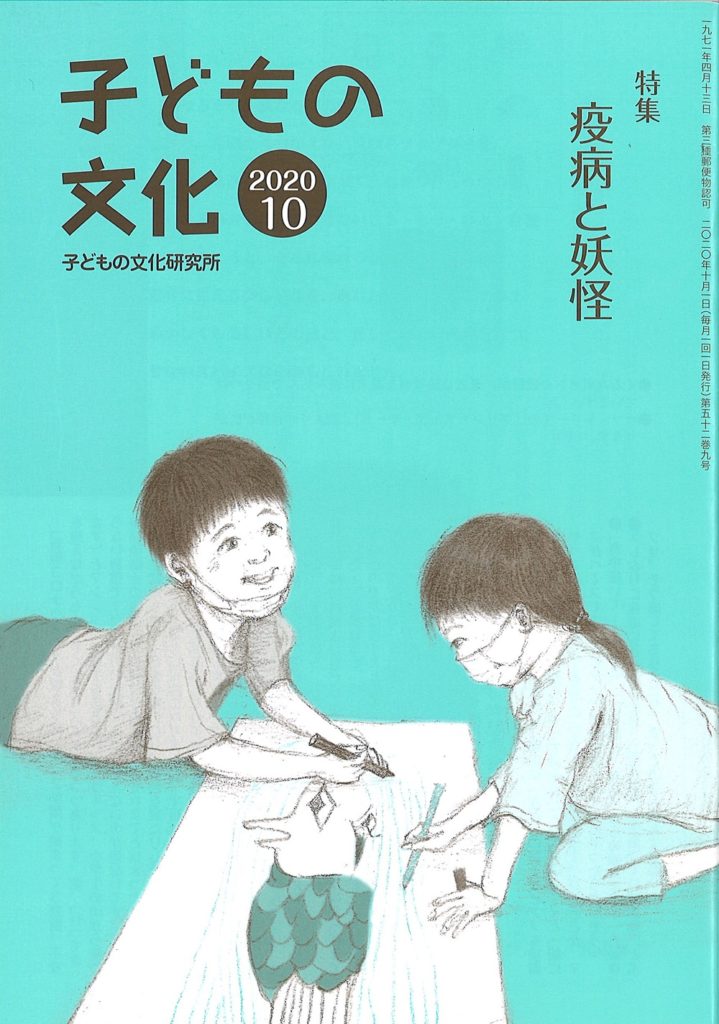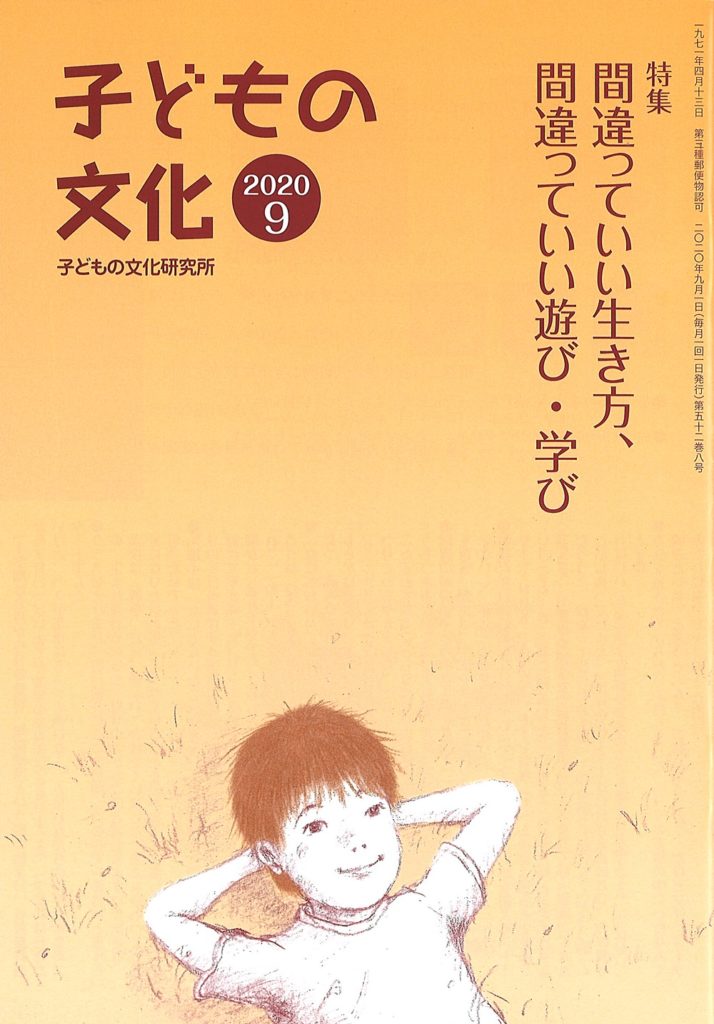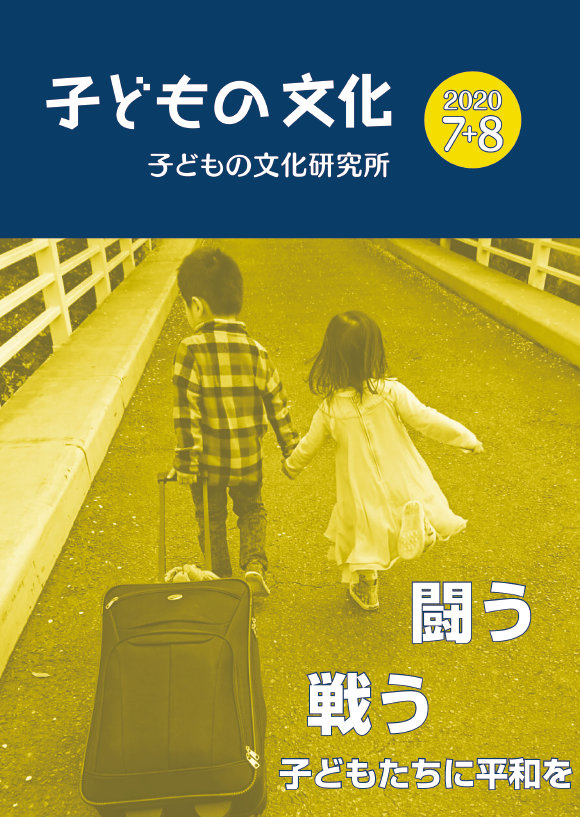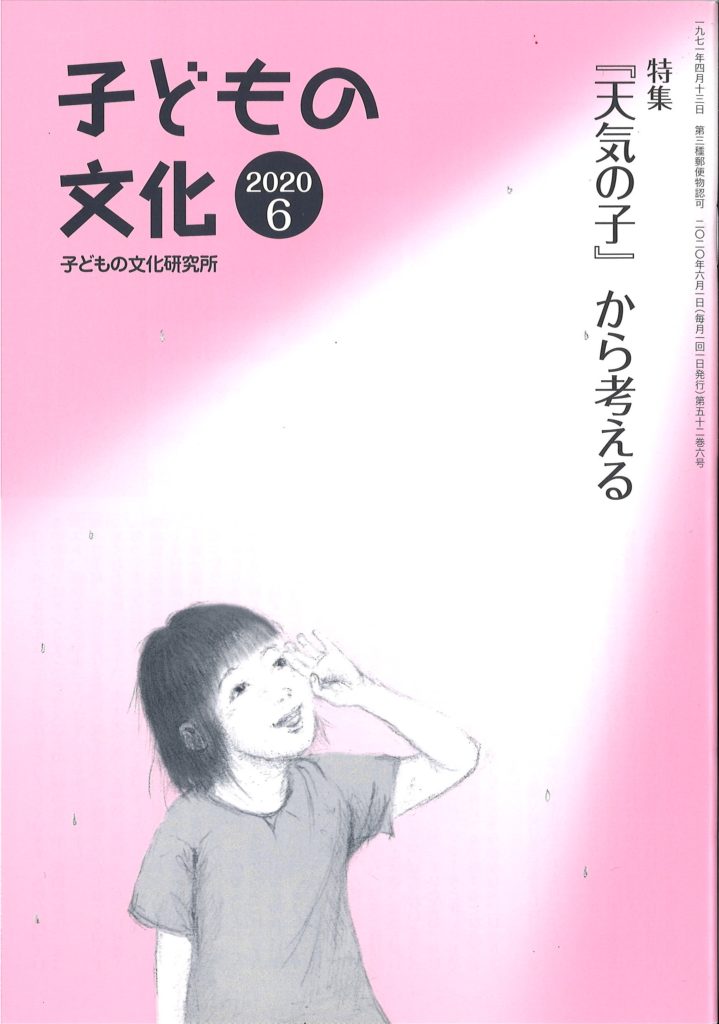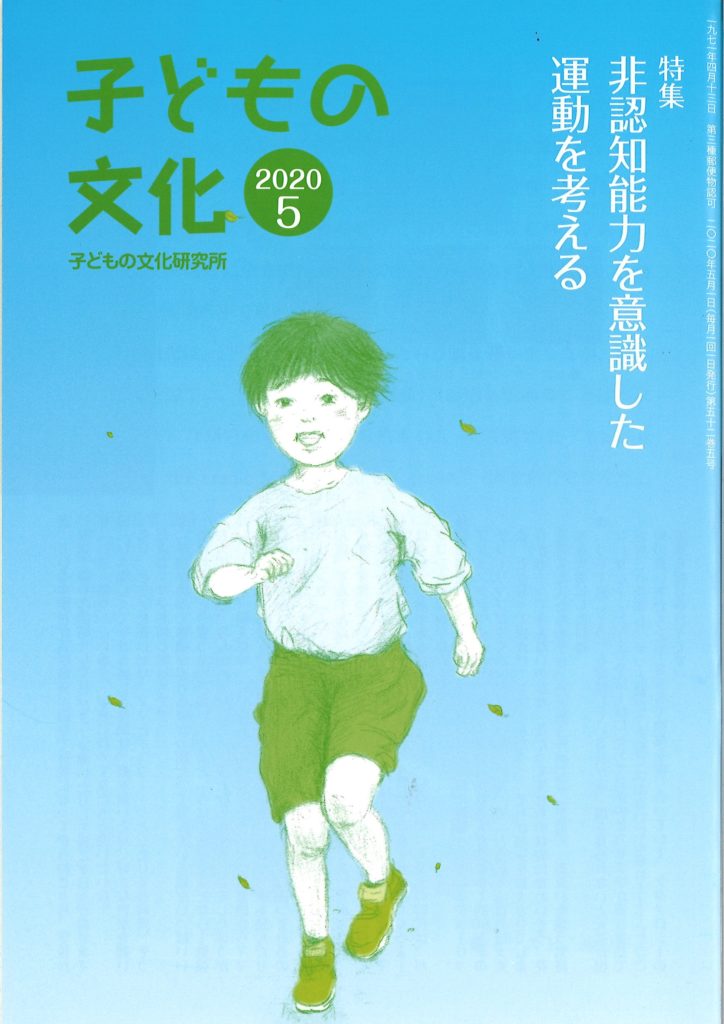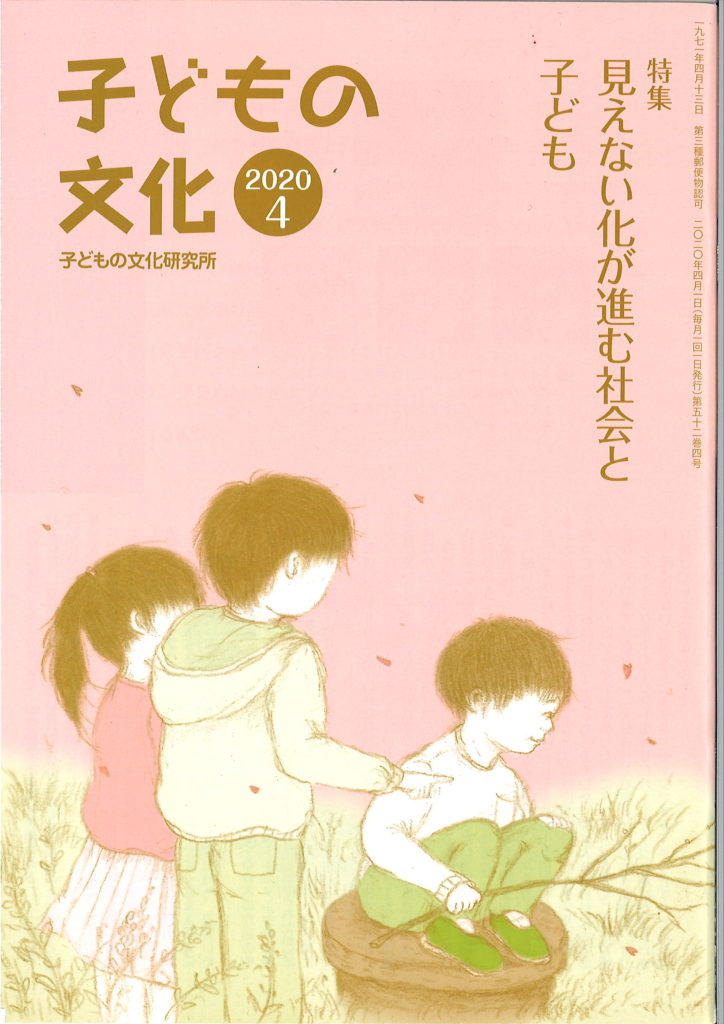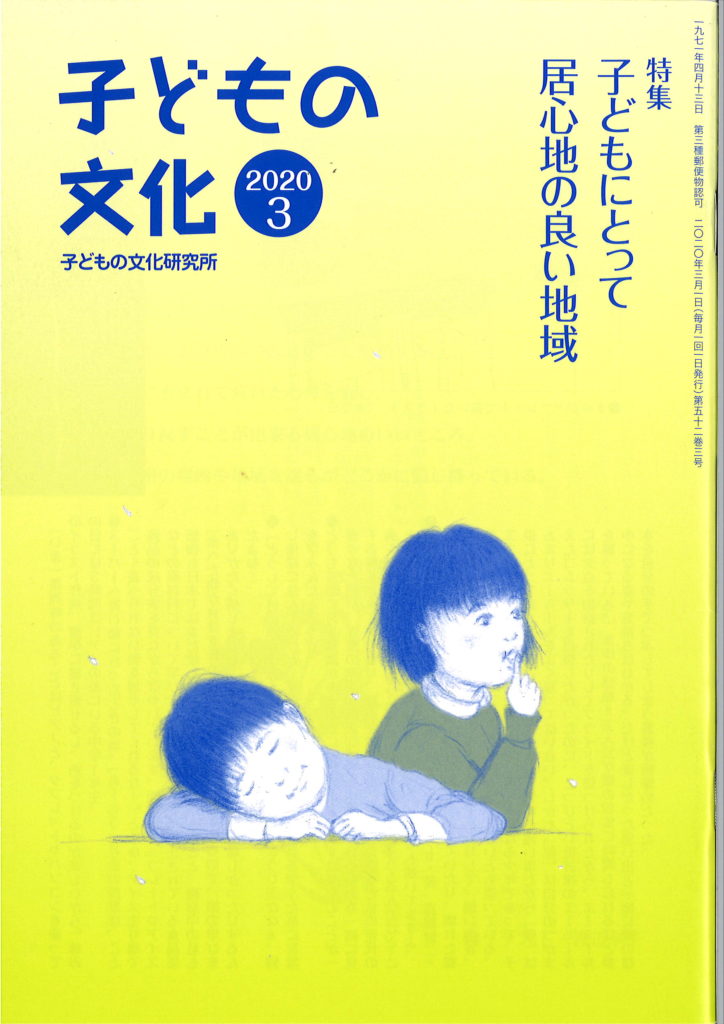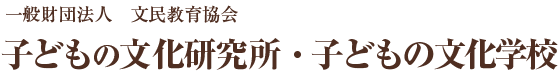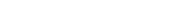月刊子どもの文化・研究子どもの文化
2021年3月号
-
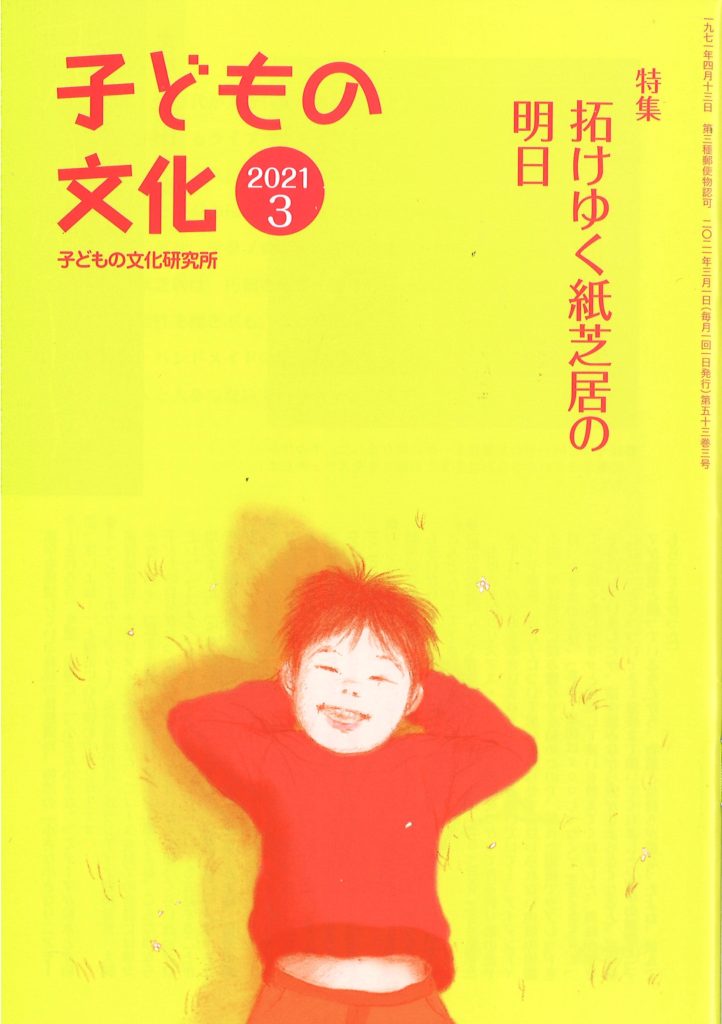
-
2021年3月号
ビジネス・手づくり紙芝居・世界での広がりなどを参考に紙芝居のメディア性を検証した特集です。
大阪のてづくり紙芝居館の創設や、WKF(World Kamishibai Festival)の取り組みなど最新の情報交えて、紙芝居の現在とその特性を生かした紙芝居の明日を探ります。
2021年2月号
-
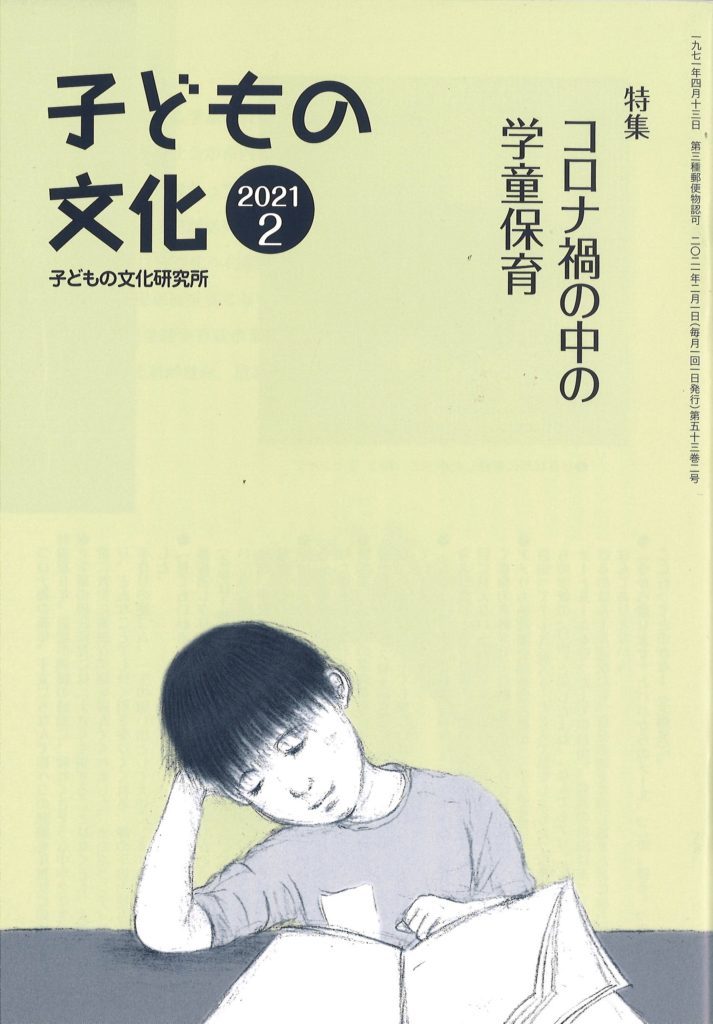
-
2021年2月号
コロナ禍で生じた問題と、その中で学童保育が果たしたものを、東西の各学童の様子から執筆して頂きました。
2021年1月号
-
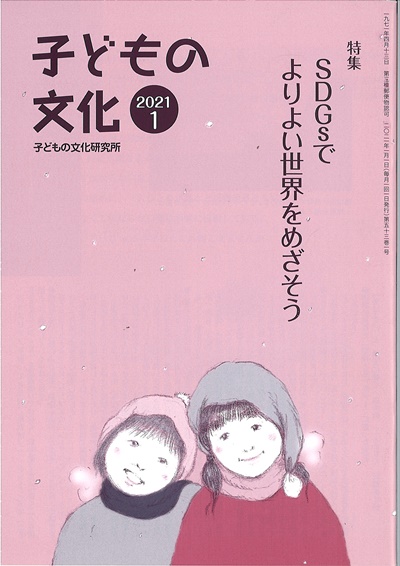
-
2021年1月号
SDGsという言葉を最近耳にするようになりました。SDGsは国連で作られた地球が持続可能な開発のための国際目標です。第4項質の高い教育をみんなにを中心にコロナ禍の中で、保育を基点に私達は何をしていくべきかを、汐見稔幸先生と島本一男先生に対談していただき、その先の未来について考えていきます。
2020年12月号
-
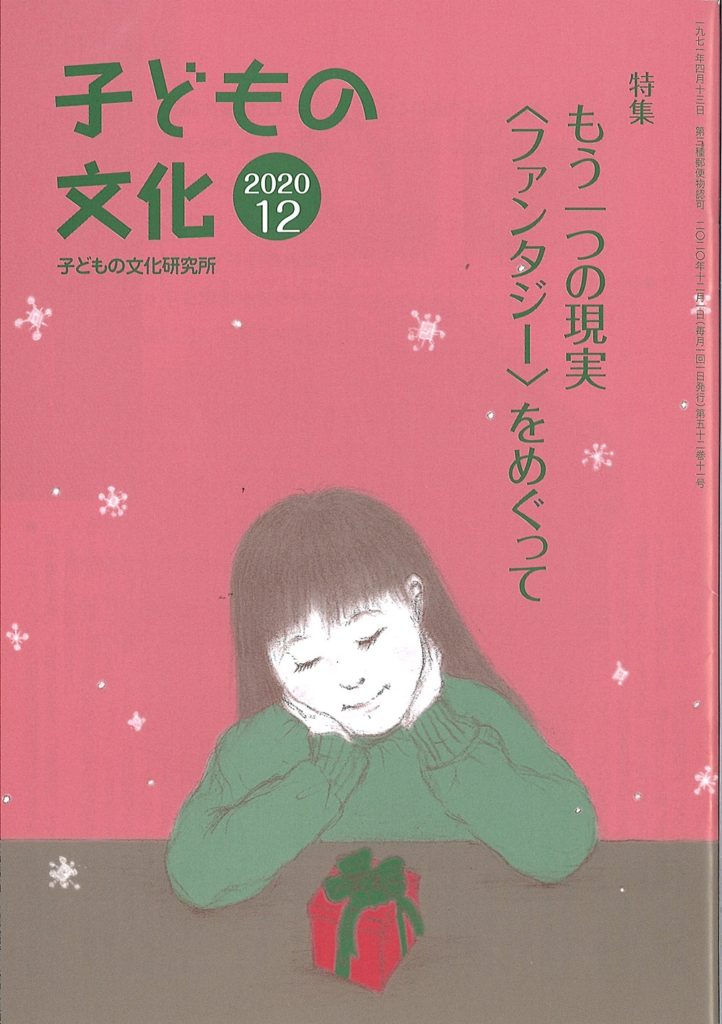
-
2020年12月号
2020年12月号 日本は、様々な場所でファンタジーがあふれている。ファンタジーは、「行きて、帰りし物語」が基本だったのに、現在は世界に留まる物語となってきている。「もう一つの現実」を求めるあり方は、いったい何を意味し、何をもたらしているのだろうか。様々な面から、ファンタジーについて探っていく。
2020年11月号
-
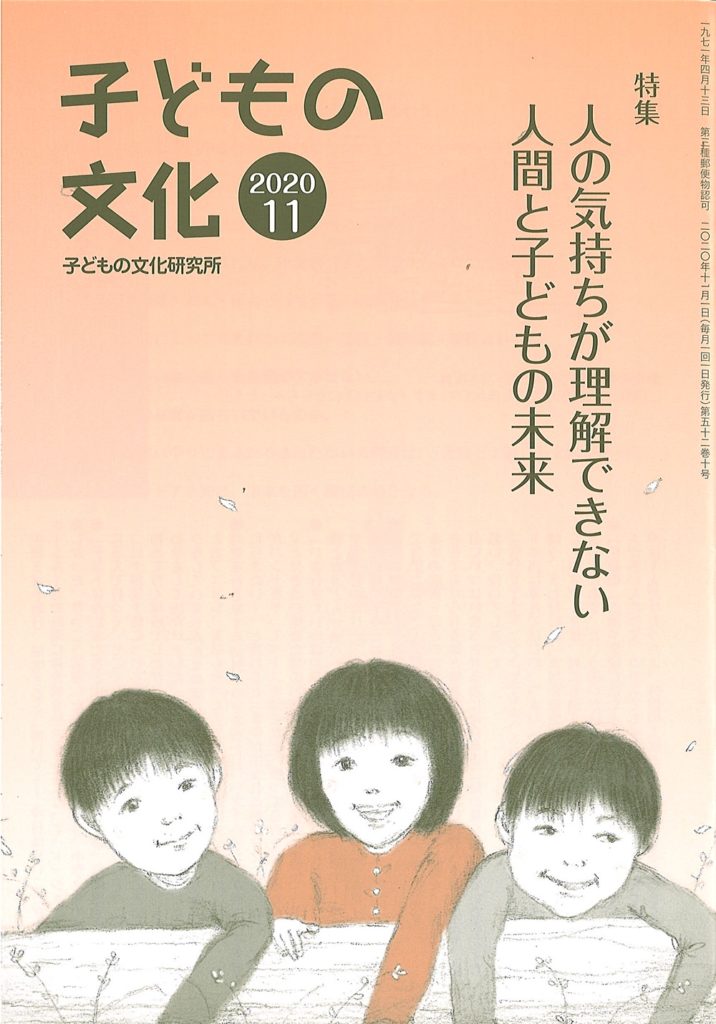
-
2020年11月号
2020年11月号 人の気持ちが理解できない人が増えているという。しかし、実際は大人が子どもに一方的に気持ちを押し付けていないだろうか。子どもの持つ能力に焦点を当て、社会が「子ども理解を深め、安心して自己表現しながらアイデンティティを構築できる環境を作る」ために何を目指すべきかを考えていく。
2020年10月号
-
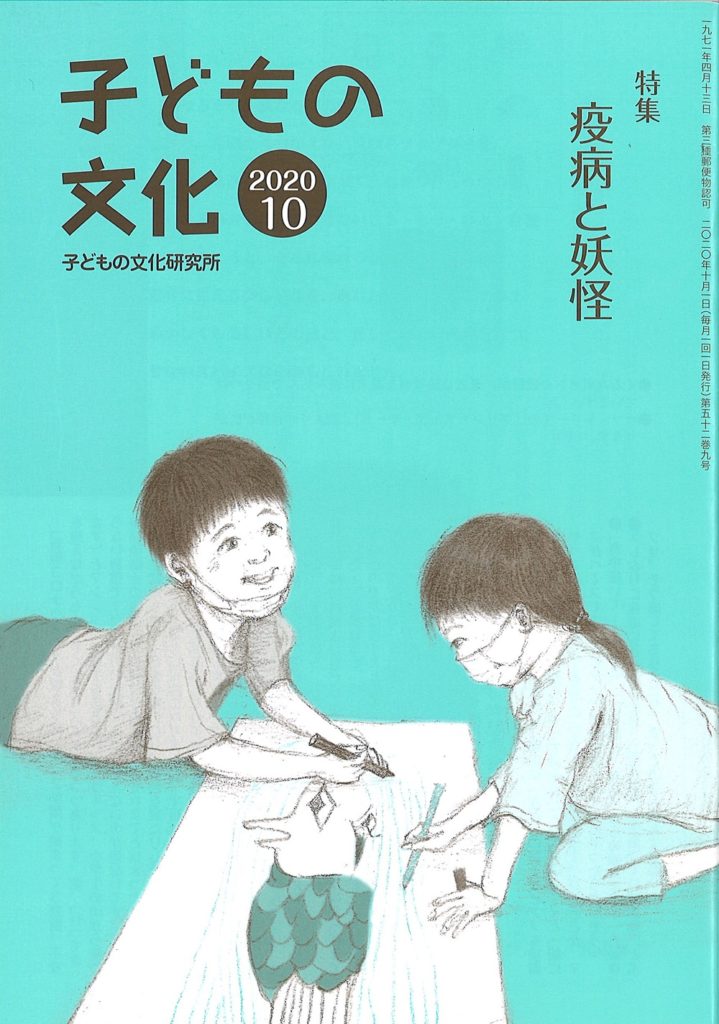
-
2020年10月号
このコロナ禍の中、対コロナウイルスのアイコンになったアマビエにスポットライトがあたりました。そこから、日本人と妖怪の深い関わりが注目されています。日本人にとって、アマビエとは、何だったのでしょうか。そして、疫病とは何なのでしょうか。様々な角度から、日本人と疫病、そして妖怪との関係を歴史などから探ります。
2020年9月号
-
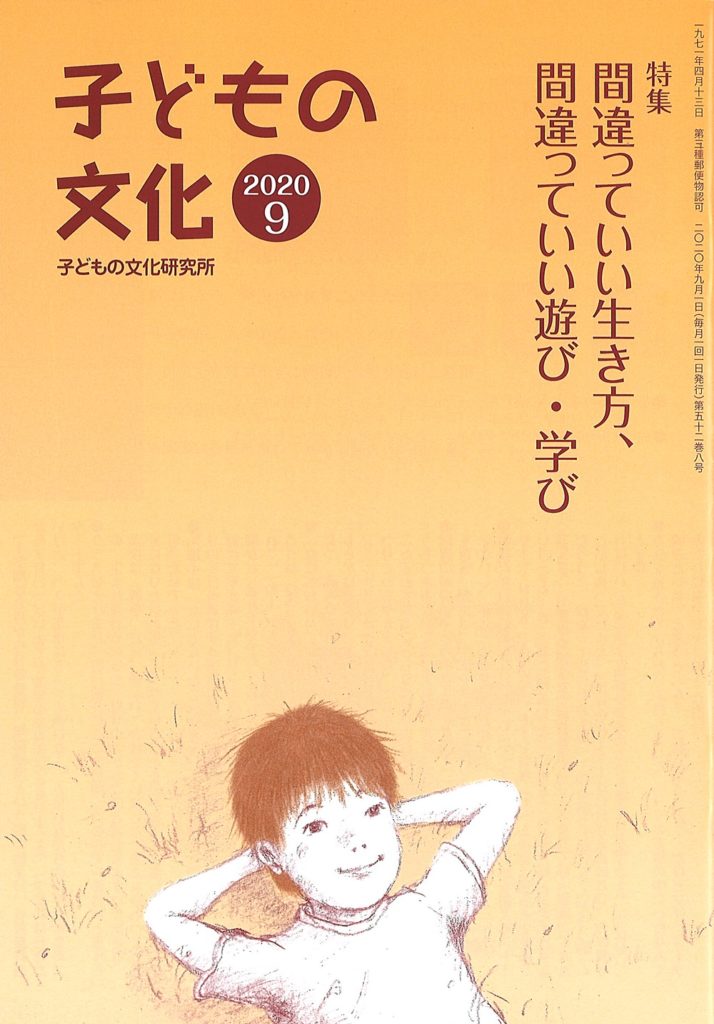
-
2020年9月号
ゆるぎのない「正しい」社会が薄れてきている現代の日本。今、「間違えてもいい」という考え方やとらえ方が受容される社会へと少しずつ変化してきています。「間違わない」社会とは何なのでしょうか。若き気鋭の先生方と「間違っていい」生き方と、これからの学びや新しい社会について考えていきます。
2020年7+8月号
-
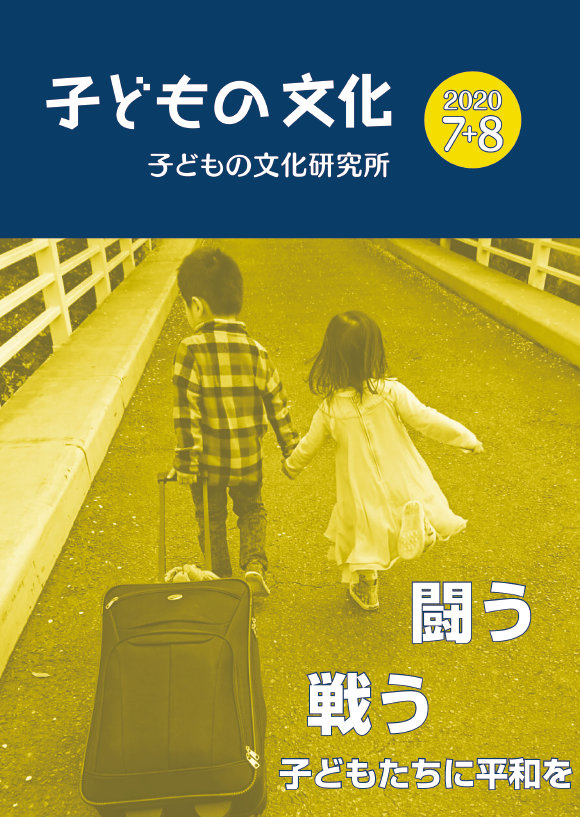
-
2020年7+8月号
5年に1度の戦争特集。オリンピックイヤーとなるはずだった今年は、「たたかう」ということを幅広くとらえ自分の身近な闘いや戦いについて執筆して頂きました。難民を救うために闘う若者たち、差別と向き合い闘う若者たち、書籍から存在が知られてきた模擬原爆のパンプキン。目に見えないウイルスの脅威と闘う今、わたしたちの身近なところにも戦争の種になるかもしれない大きな問題がたくさん潜んでいることに気づかされます。「この悲劇を2度と繰り返さない」ために、戦争の歴史を語り継ぐだけでなく、今起きている問題にも目を向た、どの世代にも読んでほしい夏の合併号です。
2020年6月号
-
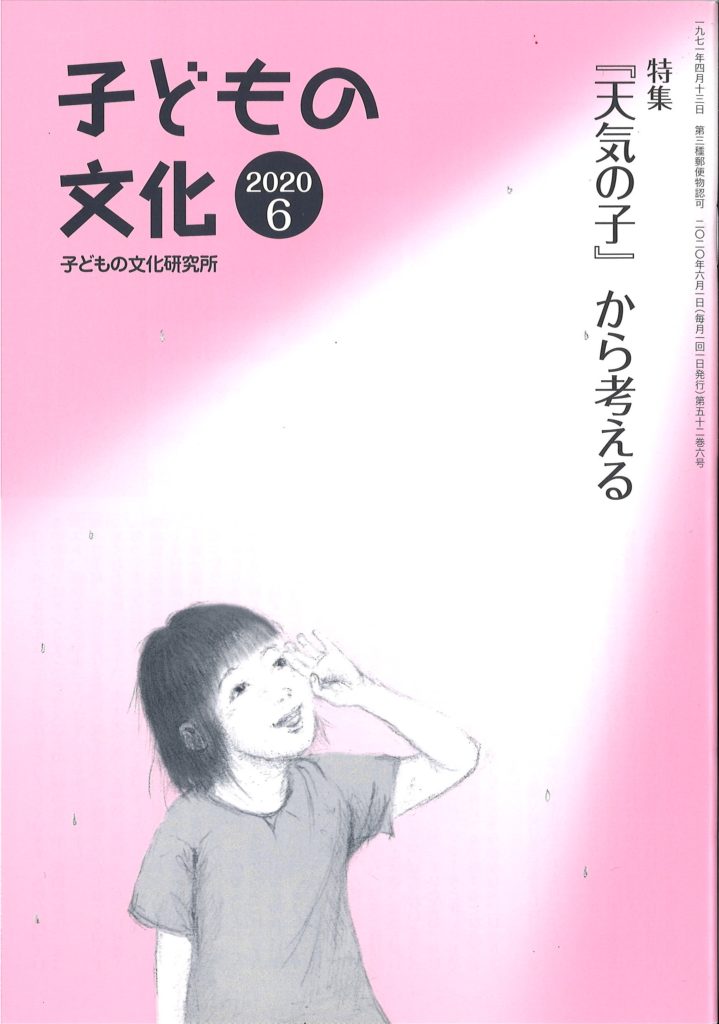
-
2020年6月号
新海誠監督の話題作『天気の子』は、我々にたくさんのことを投げかけている。作品のおもしろさ、新海監督の他の作品との比較、環境問題から隣の人の話題まで快眠談義と称して血気盛んなワニザメ党の青年3人がざっくばらんに語ります。他にも科学読物研究会副運営委員長の市川雅子先生が天気や気象の子どもの本を紹介します。
2020年5月号
-
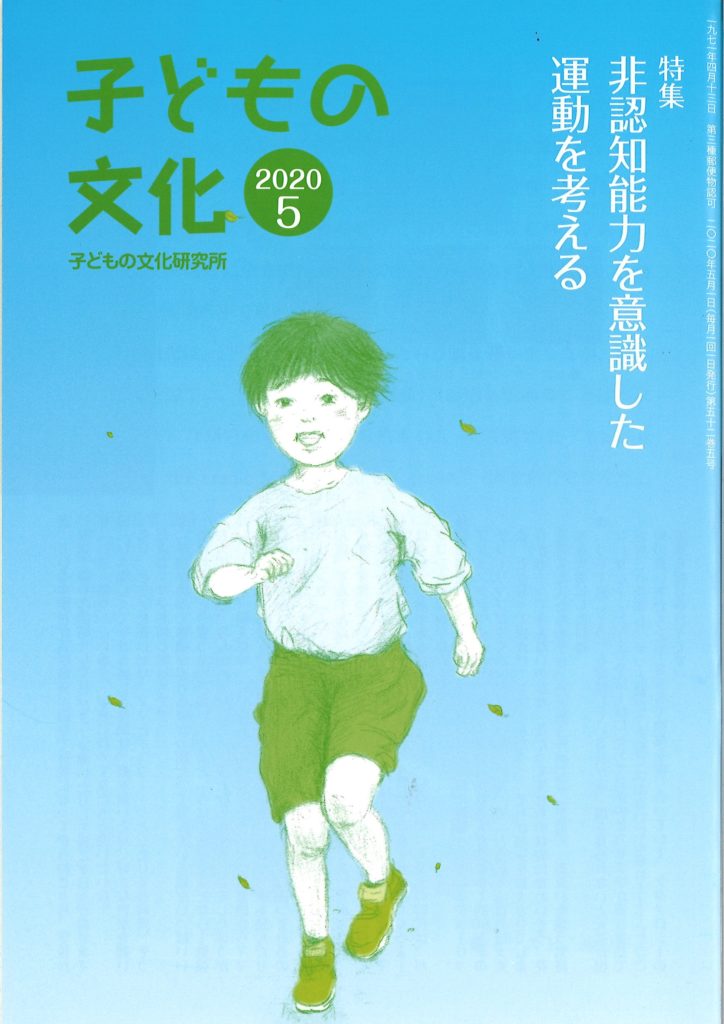
-
2020年5月号
子どもの運動能力をどう発達させるか―それは総合的な学びとして運動遊びをとらえていくこと。その具体例を長年子どもの遊びと運動を実践してきた菊池一英先生と島本一男先生が提起します。広大な里山にある東京ゆりかご幼稚園園長内野彰裕先生とサーキット遊びを展開する片山喜章先生の実践は目からウロコ!ぜひ手にとってお読みください。
2020年4月号
-
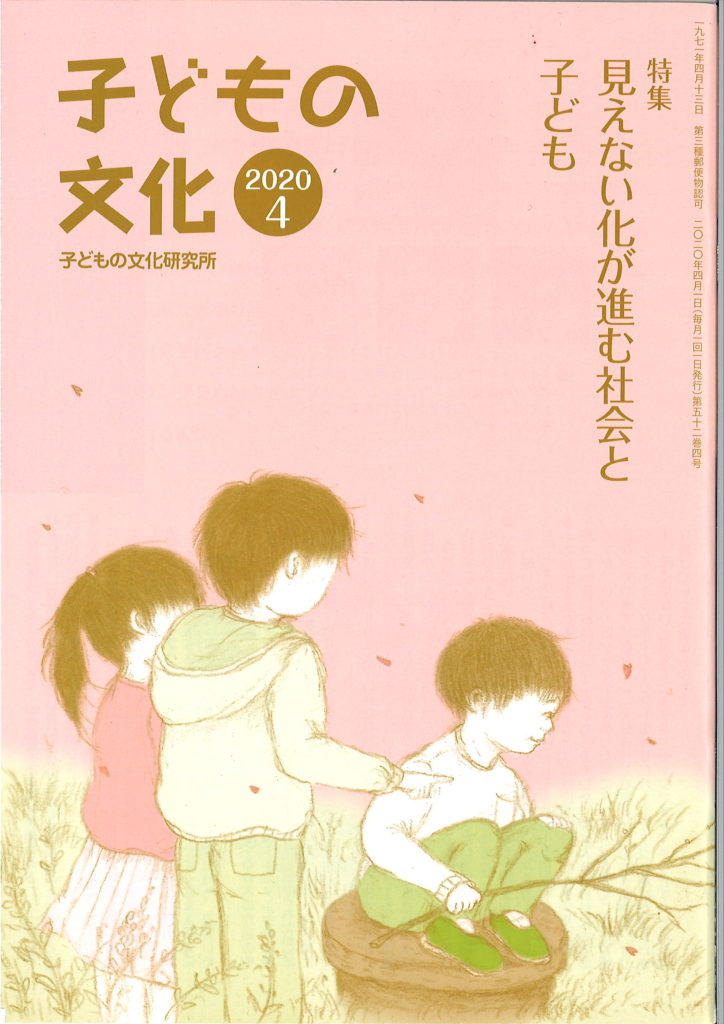
-
2020年4月号
労働やお金、ショービジネス、交友関係など今までは当たり前に目に見えていたものが、キャッシュレスやSNSなどの普及でそのやりとりは目には見えなくなっています。
子どもたちがこれから過ごす社会はさらに、‶見えない化”が進むことでしょう。お店ごっこではレジの人と会話をせずに、お金を置いて去っていく。現場では、そんな光景も見えるようになってきました。キャッシュレス社会から見る世界の動向と、子どもたちの様子、切っても切り離せないSNSとの付き合い方と可能性、子どもたちが生きるこれからの社会をみすえる特集です。
2020年3月号
-
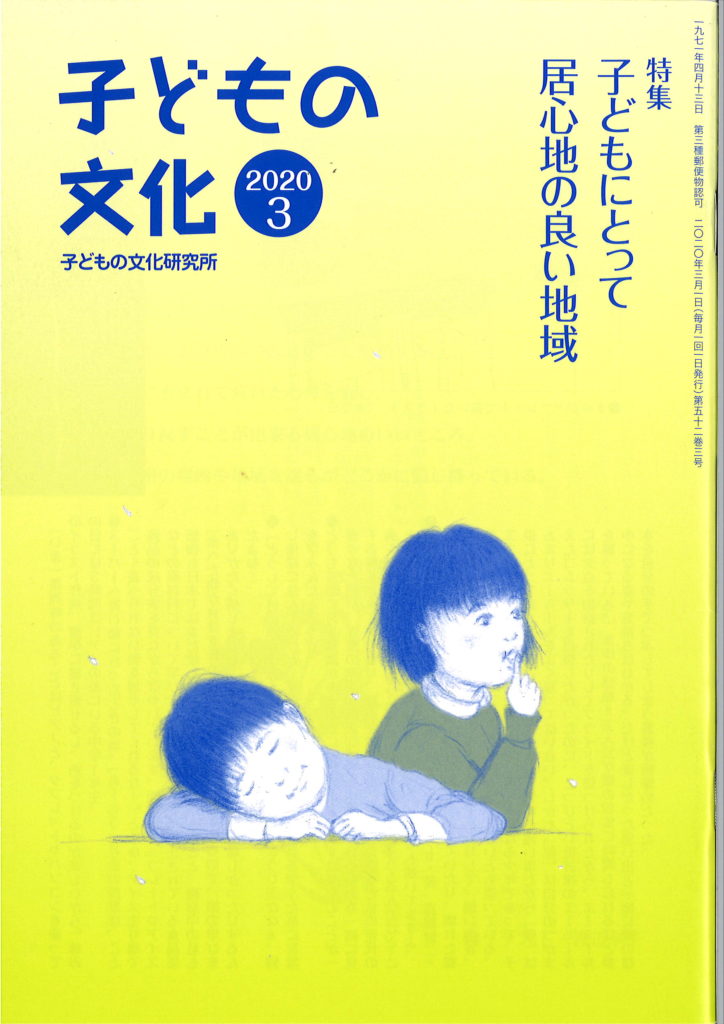
-
2020年3月号
多様な人たちがかかわって地域を元気にする手法「ローカルガバナンス」そのためには、住民、NPO、企業などの団体や個人が地域経営にかかわることが求められます。そんなローカルがバンスを保育でとらえる特集です。子どもたちに「なんだか居心地が良い」と思ってもらえるような場所づくりに求められるものはなんでしょうか。居心地の良い保育園や幼稚園、子ども園は保護者にとっても、保育者にとっても、地域福祉にとっても居心地の良い場所につながるのではないでしょうか。