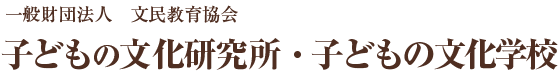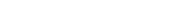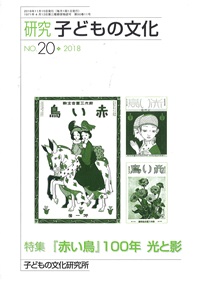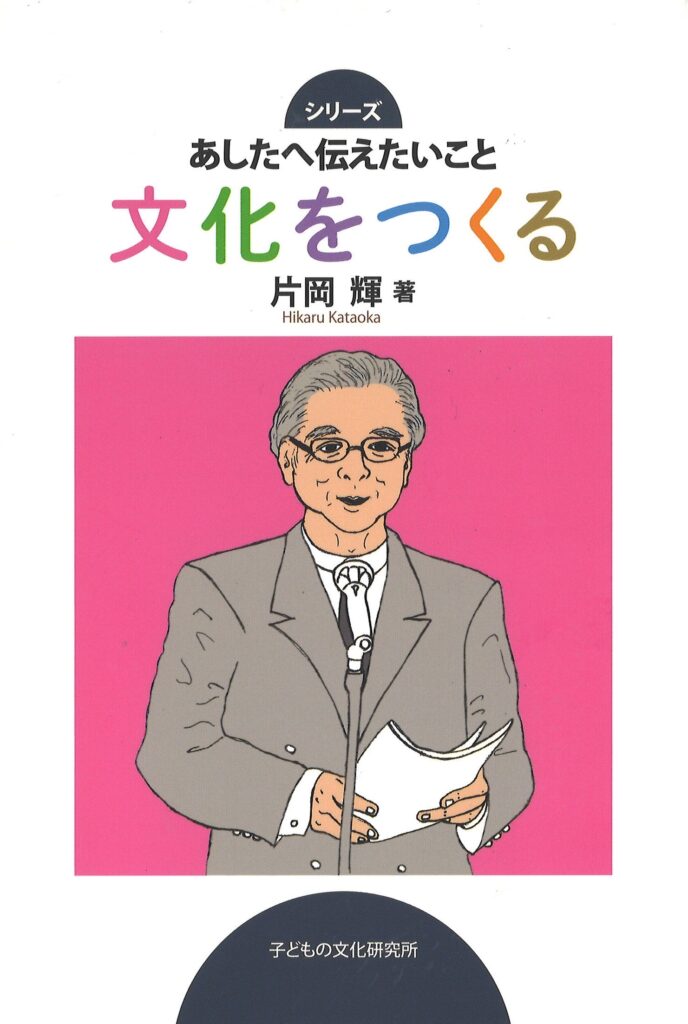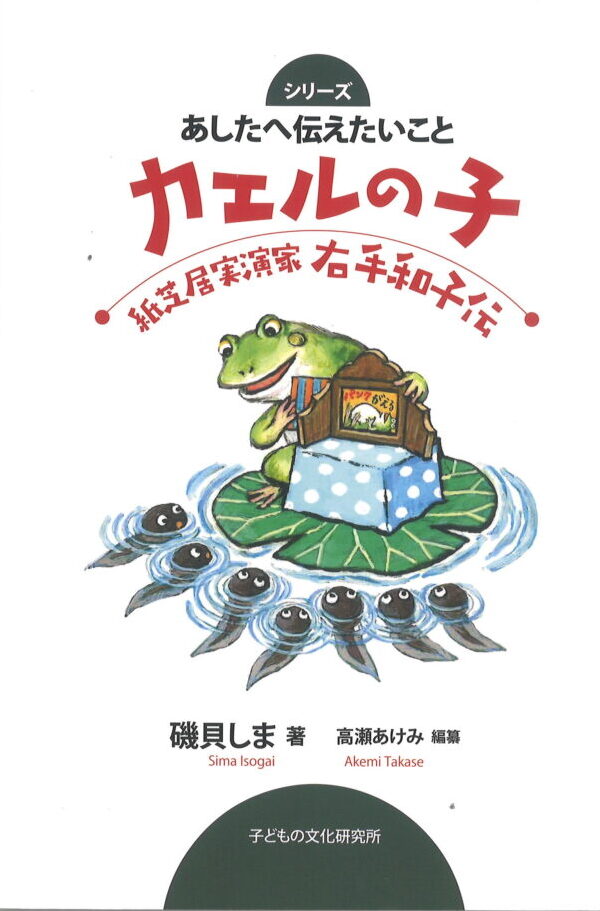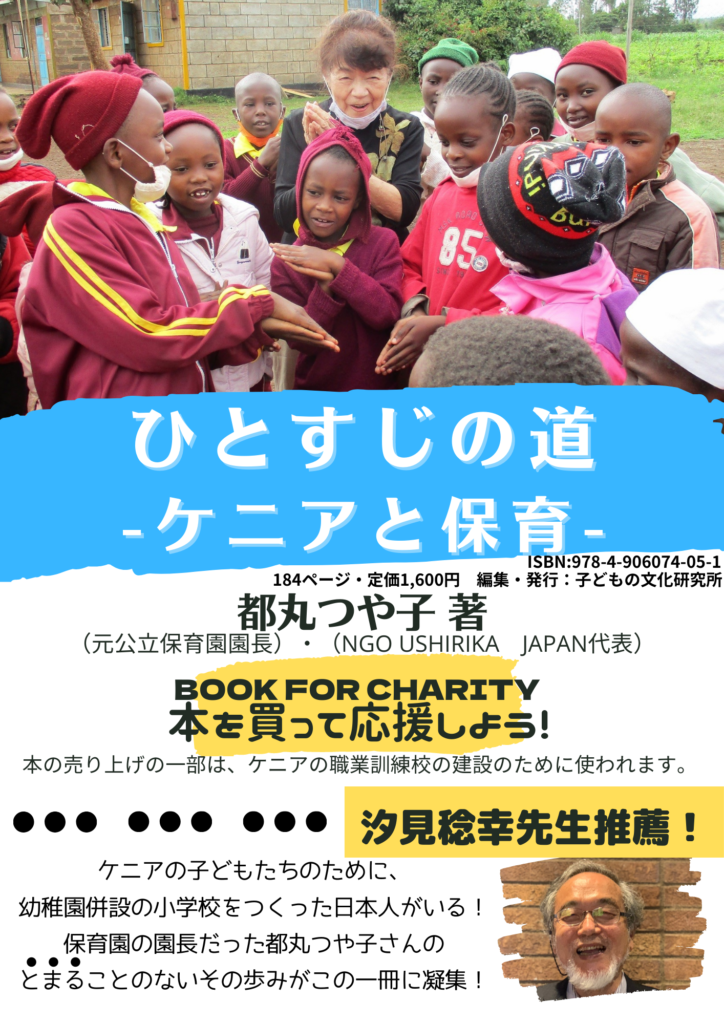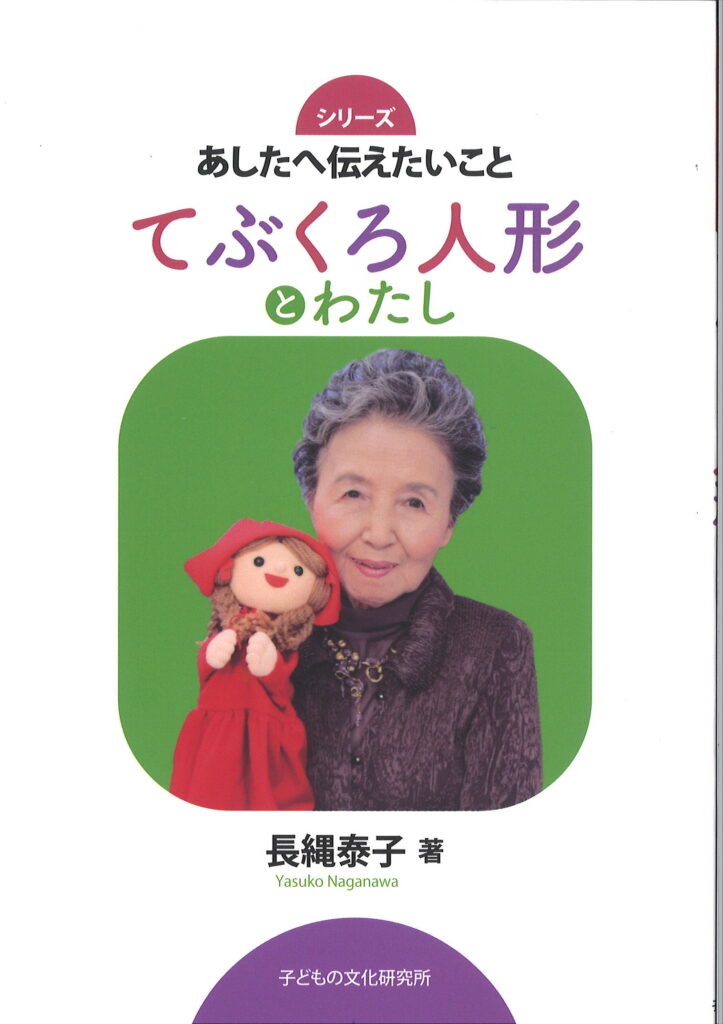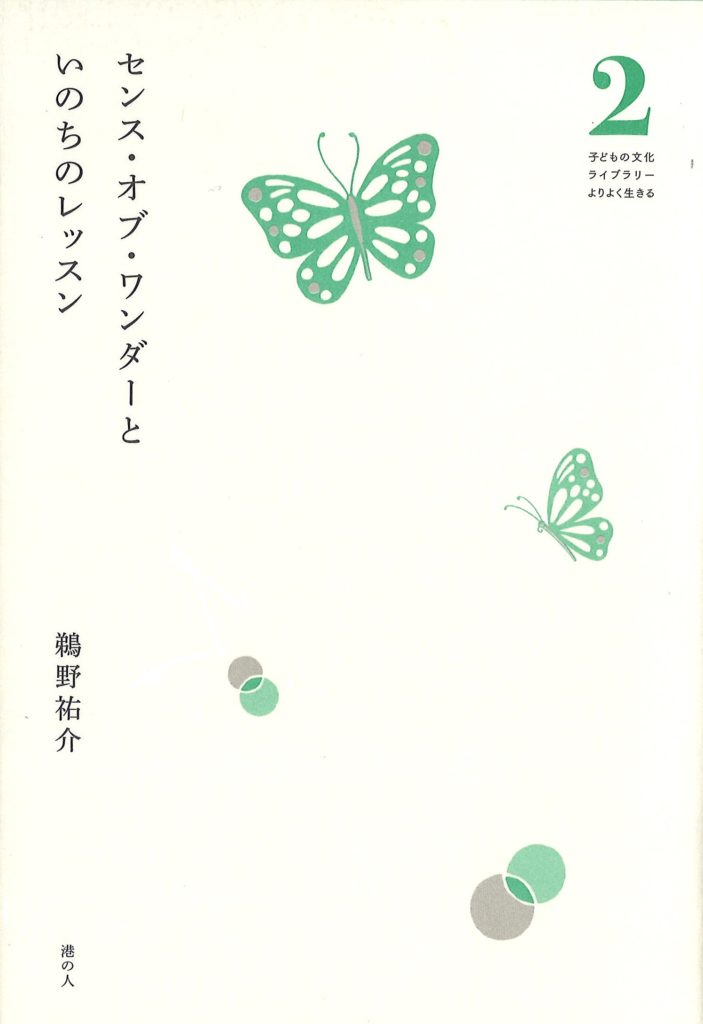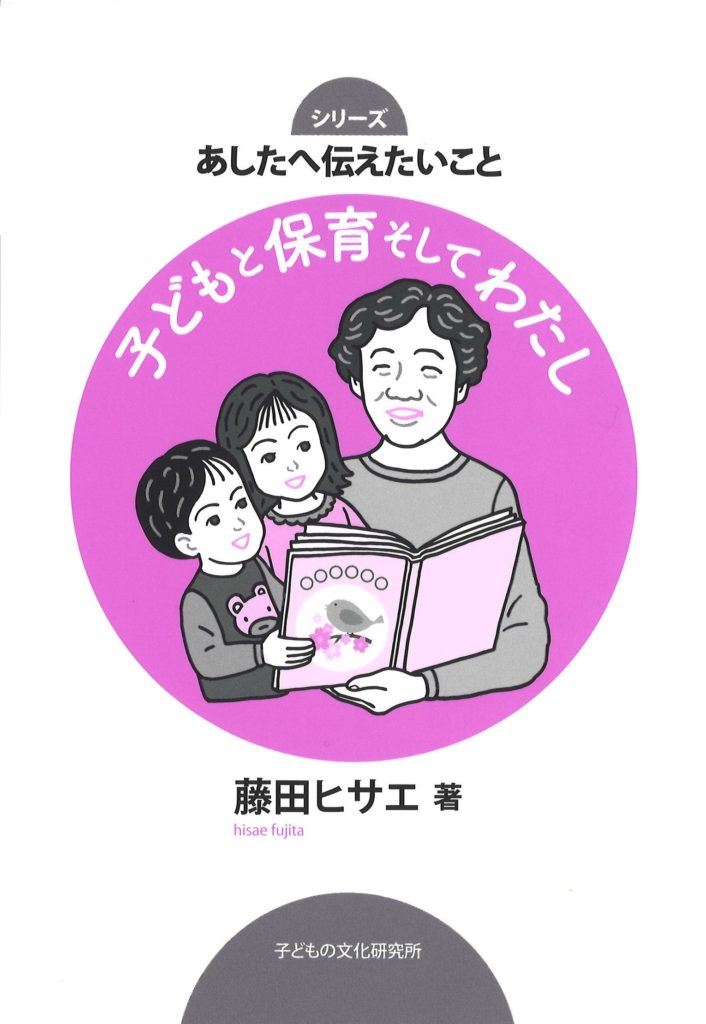『子どもの文化』は、日本で唯一、“子どもの文化” を総合的に扱う月刊誌です。
子どもたちに関わるすべての方に向けて発信しています
2025年6月号
-
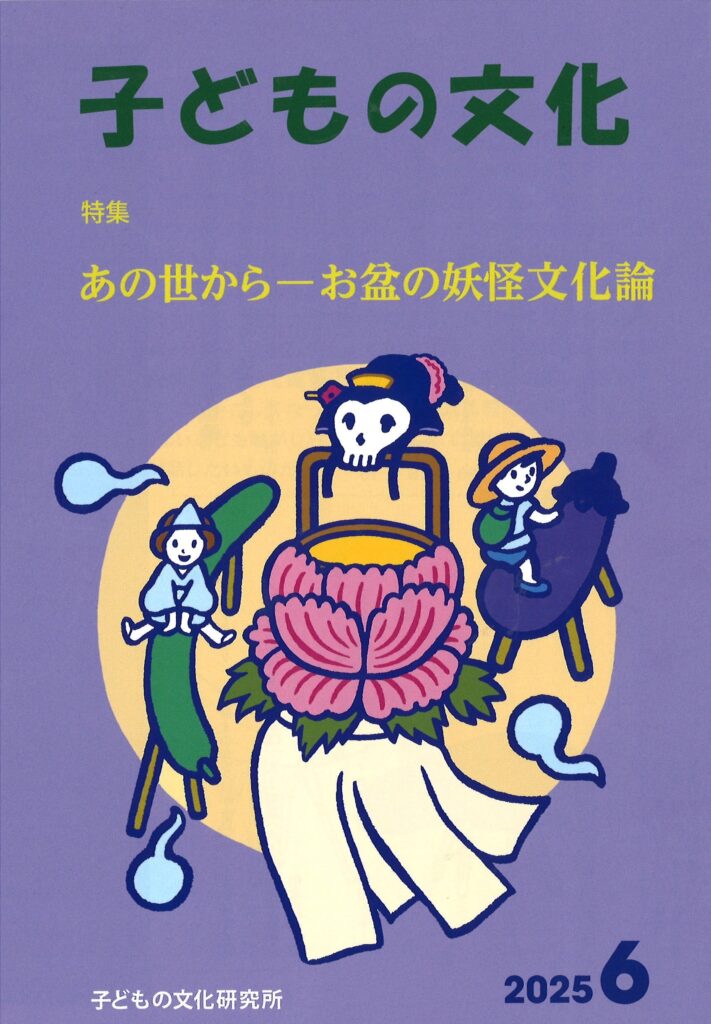
-
特集 特集 あの世から―お盆の妖怪文化論
今号の特集では、お盆を「妖怪・神・霊魂」との対話の場として見つめ直します。 祖霊や無縁仏、帰れぬ霊や森に宿るものたちに、私たちは何を届け、何を託してきたのか—— 過去と現在をつなぐ、「お盆のかたち」をひもときます。
2025年5月号
-
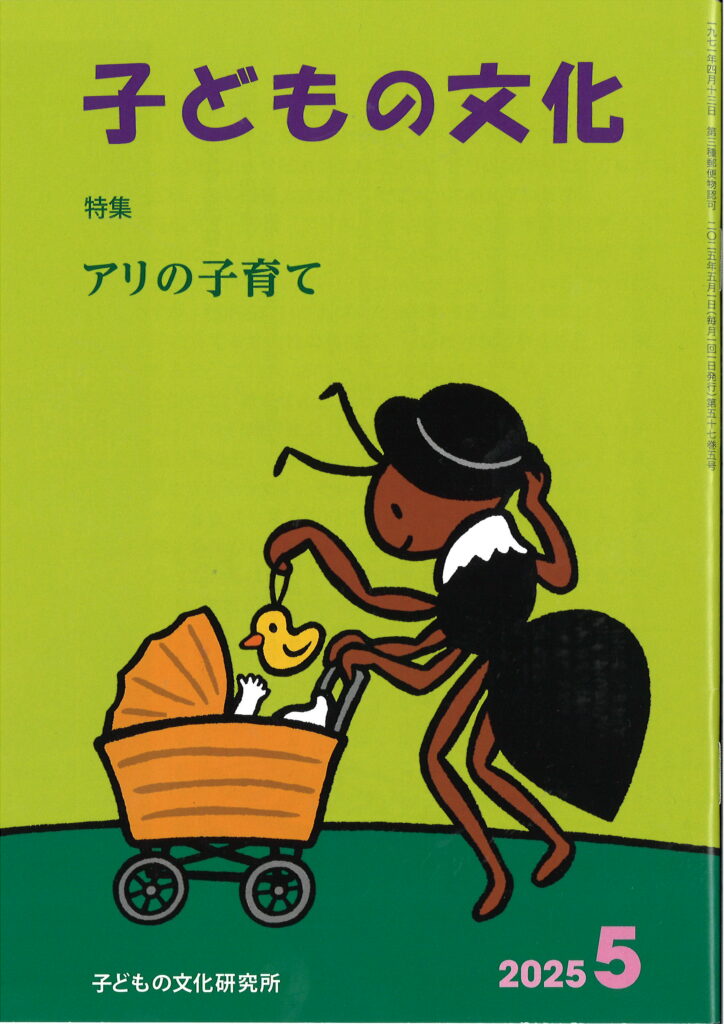
-
特集 アリの子育て
アリの行動や生態を研究している久本峻平先生を囲んでの座談会。アリの社会では共同育児が基本。お世話をされないとアリの幼虫は生きていけない。働きアリが協力しながら、餌を口移しで与え、体を舐めてグルーミング、適度な温度の場所に移動、羽化の手伝い、ゴミ捨て、と手厚いお世話。まるで保育園のよう。アリの社会は全員が同じ方向だと状態や状況が硬直化してしまい、個性があることが社会システムの原動力になる。アリの子育てから学ぶ特集です。
2024年12・1月号
-
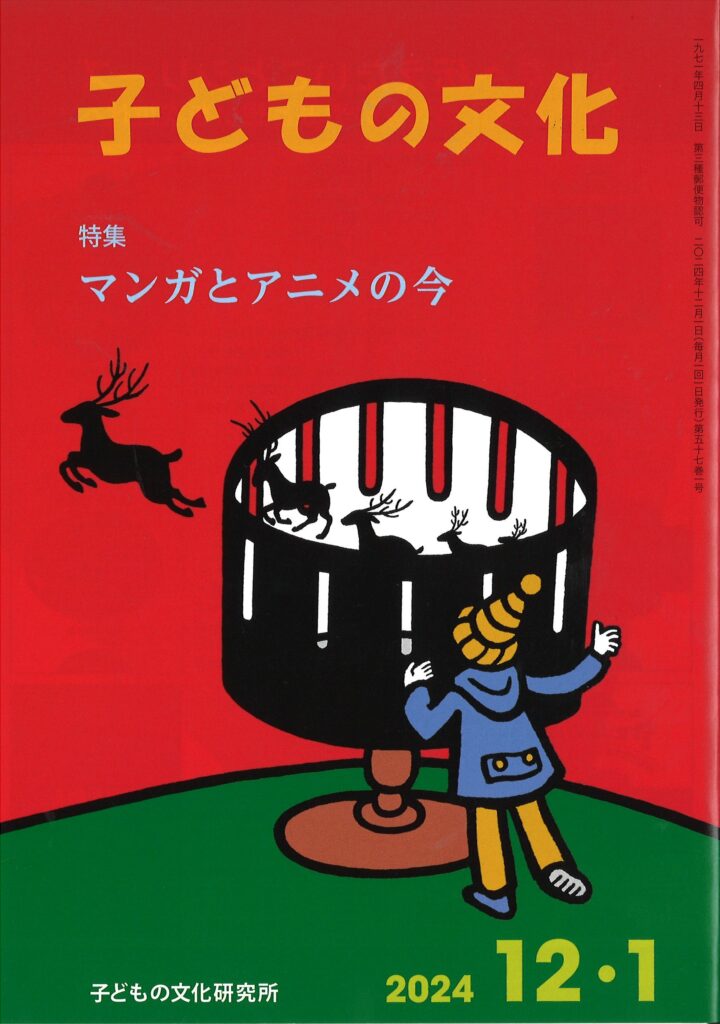
-
特集 マンガとアニメの今
本特集では、日本の誇る文化であるマンガとアニメを「過去・現在・未来」の視点から多角的に探る。PART1では、マンガとアニメの文化的、技術的進化に迫る論考を収録。中野晴行によるマンガ文化の変遷や、藤本由香里による「紙からデジタル」への移行の本質、後藤隆基が語る『サザエさん』の普遍的な魅力、数土直志の世界アニメーションの動向解説、村木美紀の現代マンガとアニメの概観といった多彩な視点から、マンガとアニメの「今」を描き出す。特集では、日本のマンガとアニメを「過去・現在・未来」の視点から多角的に探る。文化的・技術的進化や手塚治虫のインタビューを再掲載!現代の受容のあり方を論考や座談会を通じて考察。全国のアニメ・マンガミュージアムの動向も紹介し、マンガとアニメの社会的役割と未来を見つめる1冊です。
2022年 7+8月合併号
-
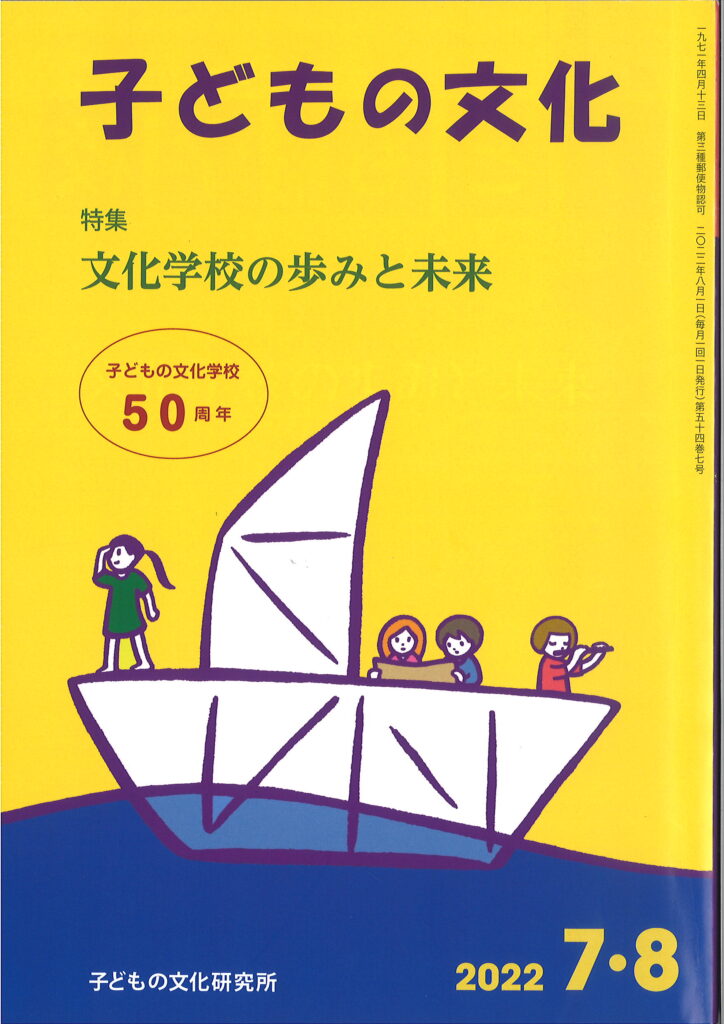
-
特集 文化学校の歩みと未来
50周年を迎えた子どもの文化学校を1冊まるごと特集します! 50年の歴史の歩みを「歴代校長の講義録」と、現学校長加藤繁美先生による解説つきの教室リーフレットで、時代の流れと活動の歴史を振り返ります。 文化学校に通ったことがある人も、そうじゃない人もぜひ一度お読みいただけたら幸いです。 先人たちの言葉と提示する課題は今に通ずるものばかりで、私たちが目指すべきところや忘れてはならない格言にこれからの道筋を考える一冊です。
2021年7+8月号
-
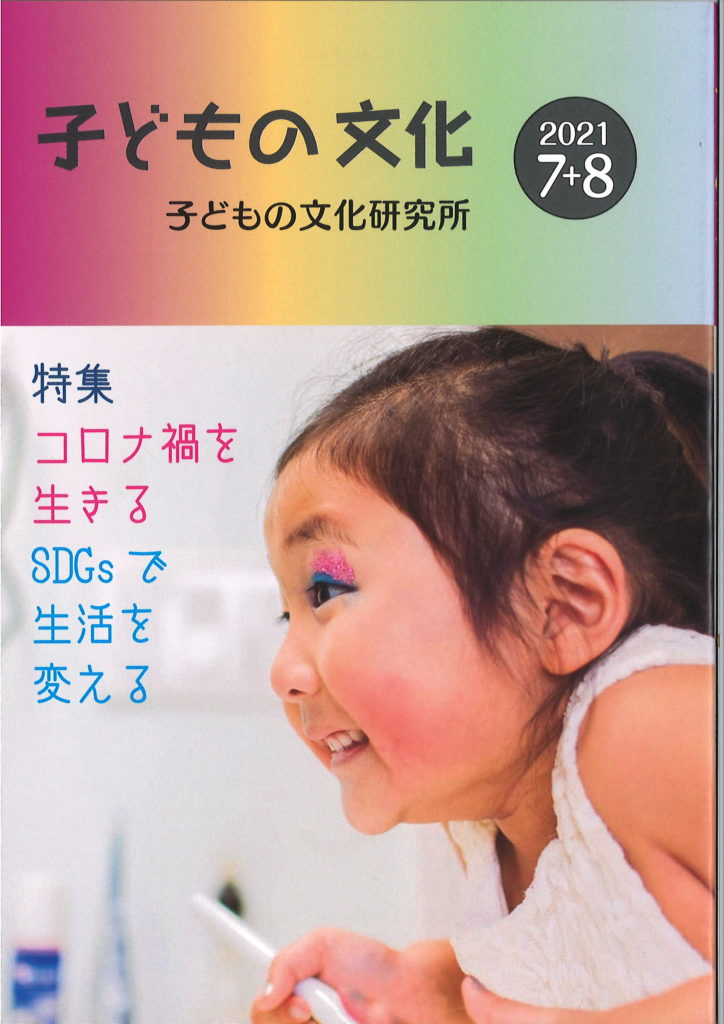
-
特集 コロナ禍を生きる・SDGsで生活を変える
第一部には、井桁容子先生と遠藤先生の公開対談「コロナ禍の中で語りたい保育の営み-変化すること、守っていくもの‐」の抄録、第2部には「汐見稔幸先生が語るSDGs」として、汐見先生のインタビューを抄録!全152ページの夏の特別合併号です。
2019年7+8月号
-
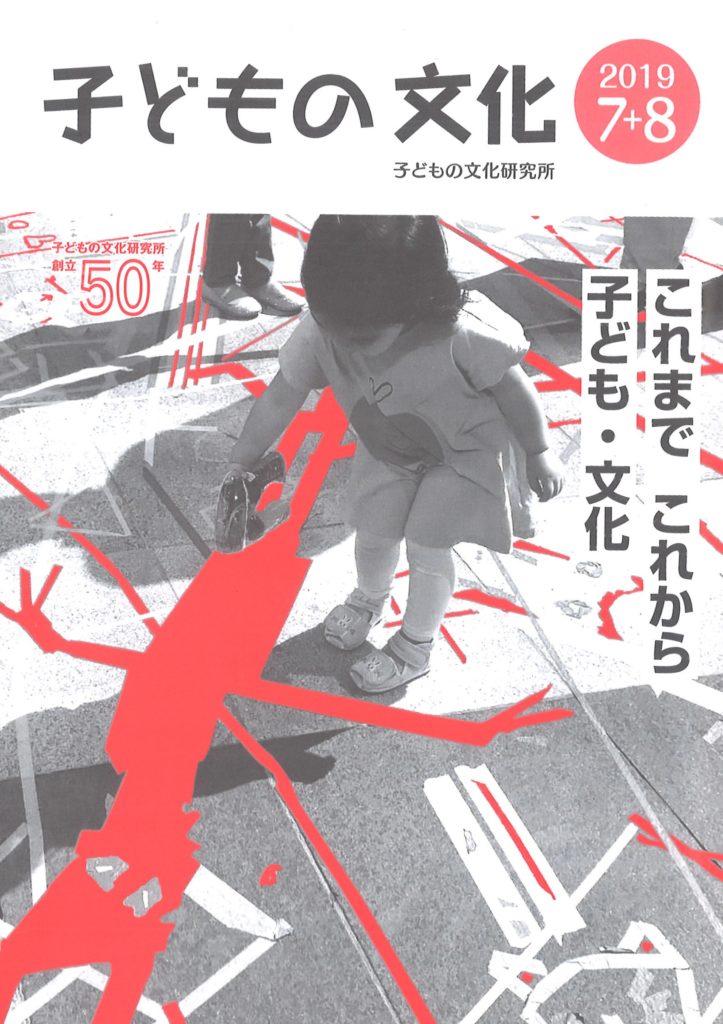
-
特集 これまで これから 子ども・文化 【子どもの文化創立50周年】
子どもの文化の普及・調査・研究と、新たな子ども文化の創造を目的として子どもの文化研究所が設立されてから今年で50年。 子どもが幸せに生きる社会の実現を志向し、「児童の世紀」といわれた20世紀を経て、21世紀は「子どもの文化を守る」世紀から、「子どもの生活を守る」世紀へと後退しているのではないでしょうか。 この特集では、教育・保育、子育て、生活、文化の4側面から、これまでの50年を振り返り、子どもや大人、そして社会がどのように変わったのか、今後、どのように進んでいくのかを探ります。