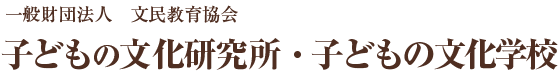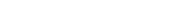紙芝居資料室
戦前から戦後昭和30年までの教育紙芝居600部余をはじめ、歴史的に価値のある希少な作品や、五山賞候補作品を中心に4000部を所蔵。
「所蔵作品リスト」を年代順に作り、所蔵・保管しています。
一方、紙芝居研究や所蔵機関の拠点としての役割を担い、紙芝居に関する様々な活動を行っています。
- 閲覧希望の場合は電話予約(03-3951-0151)が必要です。(平日午後1時~午後5時)
- 貸出用紙芝居(有料)もございます。
- 資料的価値の高い紙芝居の収集と、他の関連団体や各地の所蔵機関等との交流を行い、情報を共有しています。
- 各地の紙芝居イベントや研究会等の情報を、雑誌「子どもの文化」で発信したり、紙芝居研究やフォーラム、「紙芝居カフェ」やテーマ毎の紙芝居展等を企画し、実行しています。
紙芝居資料室所蔵作品検索
紙芝居資料室所蔵の全作品のデータベースが検索できます。
キーワードでも検索できるので、保育や実演の紙芝居選びにご活用ください。
紙芝居三賞(五山賞・右手賞・堀尾賞)
紙芝居の賞として、当研究所では紙芝居唯一のグランプリである五山賞(作品創作部門)・右手賞(実演部門)・堀尾賞(研究部門)の三賞を審査・授与する活動を行っています。
贈呈式のご案内
2024年7月13日(土)午後2時~4時(受付開始午後1時30分~) 会場 東京教育専門学校地下ホール(〒171-0031 東京都豊島区目白3-1-26)
五山賞
五山賞は1962年に高橋五山の紙芝居の業績を顕影して設けられ、一年間に出版された紙芝居の中から最も優秀な作品に授与されます。(創作部門)

第63回五山賞 絵画賞(2024)
『はじめての やぎとライオン』
出版社……教育画劇
中南米の民話をもとに、子どもたちに親しみやすい絵画表現とアナログとデジタルを融合した絵が評価された。脚本の歌に合わせた絵が印象的で「演じ方で魅力が引き出せる」と高い評価を得た。
右手悟浄・和子賞
右手賞は戦前、戦後紙芝居の名演者として大活躍された右手悟浄氏と、紙芝居一筋80余年の生涯を送られた名実演家、右手和子氏の親子二代の業績を記念して2015年に新しく設けられた演者として、また普及活動に優れた業績を上げる個人・団体を対象に贈られます。(実演部門)
第10回右手賞 団体賞(2024年度)
受賞者・受賞グループ……越前らくひょうしぎの会
日常的な活動のみならず、紙芝居を演じたい時に演じられる環境として、手づくり舞台・拍子木・紙芝居を寄贈する活動に取り組んだ。また、児童館・放課後児童クラブ・子育て支援センター等の指導員や先生方を紙芝居の演じ手として、紙芝居の作り手として、育成するという人的環境に力を入れたことが高く評価された。
堀尾賞
堀尾賞は、紙芝居作家・宮沢賢治研究者・第3代子どもの文化研究所長として子ども文化の広い領域で活動された堀尾青史氏の業績と生誕100年を記念して2015年設けられました。「堀尾賞」は、紙芝居にかかわる研究、調査、出版、評論活動など、広く紙芝居文化の振興に貢献した個人・団体を対象に隔年に贈られます。(研究部門)
第6回堀尾賞(2025年度)
受賞者・受賞グループ……谷 暎子
占領期児童出版物の研究における日本の第一人者であり、早い時期からGHQによる紙芝居に対する検閲についても注目し、数々の研究成果を発表された。一方で、戦中期から戦後初期において北海道で活発に繰り広げられた紙芝居に関わる活動について、長年にわたって地道な調査を続けてこられた。