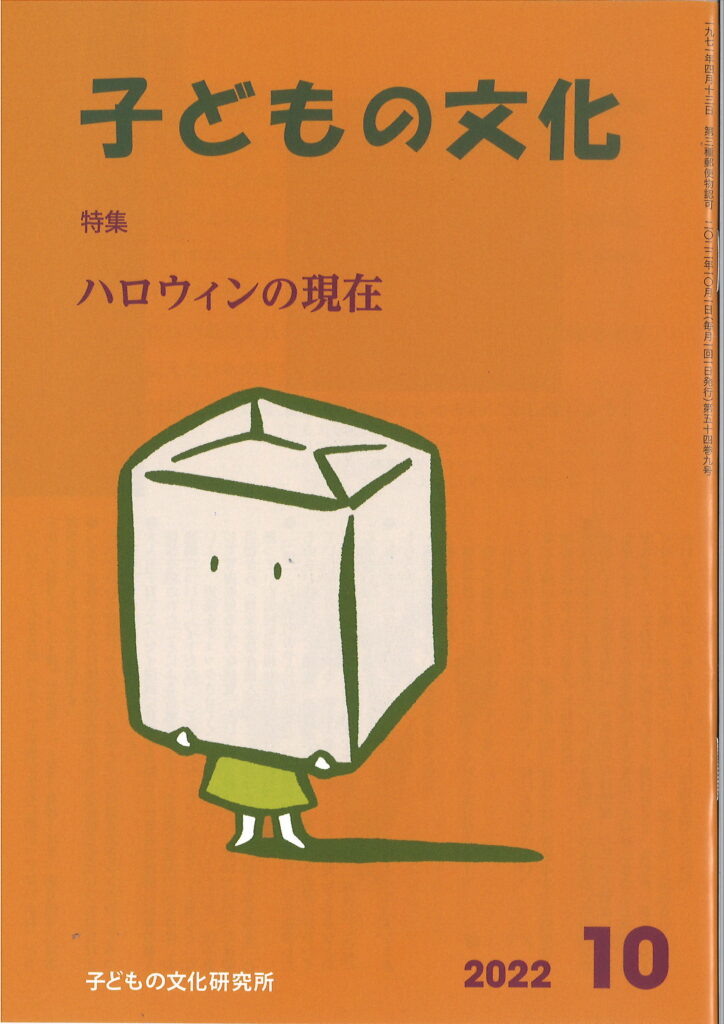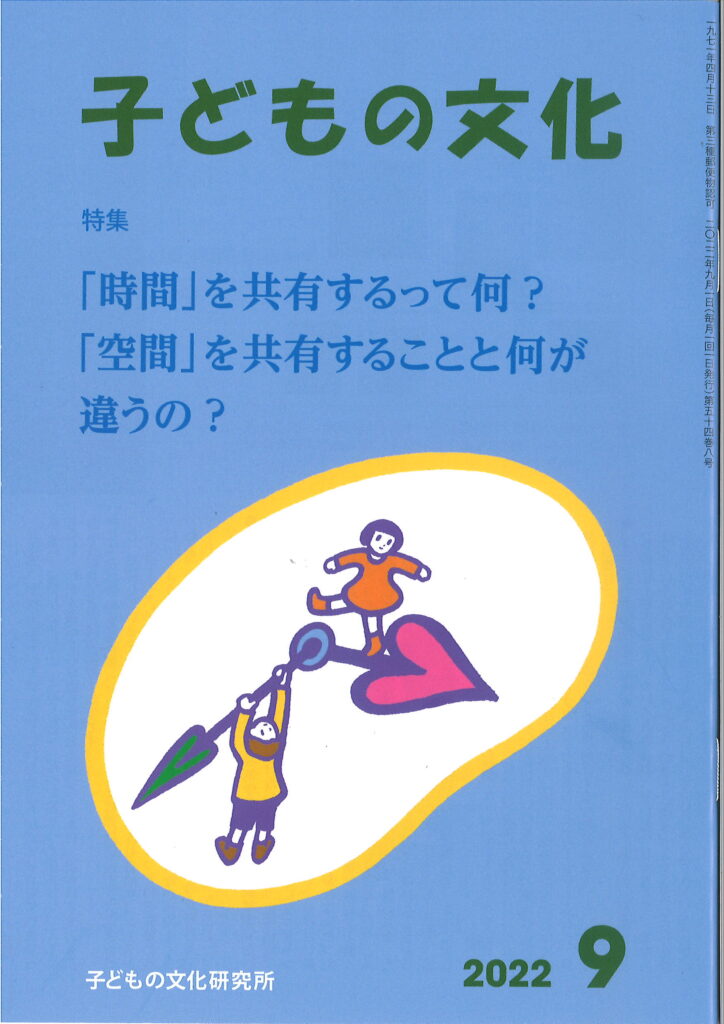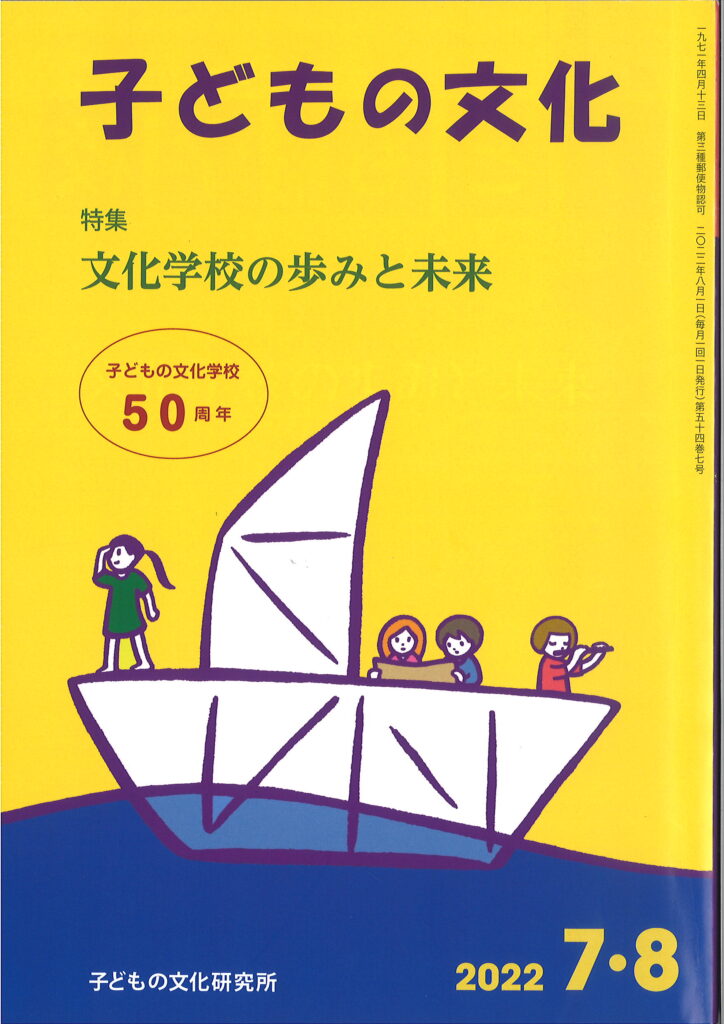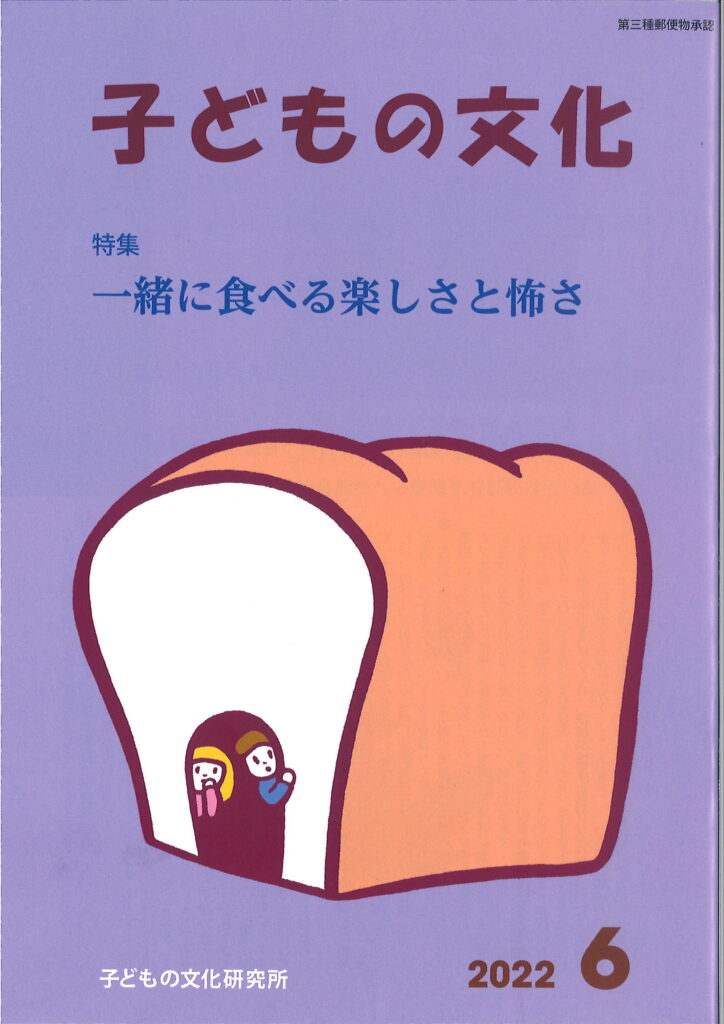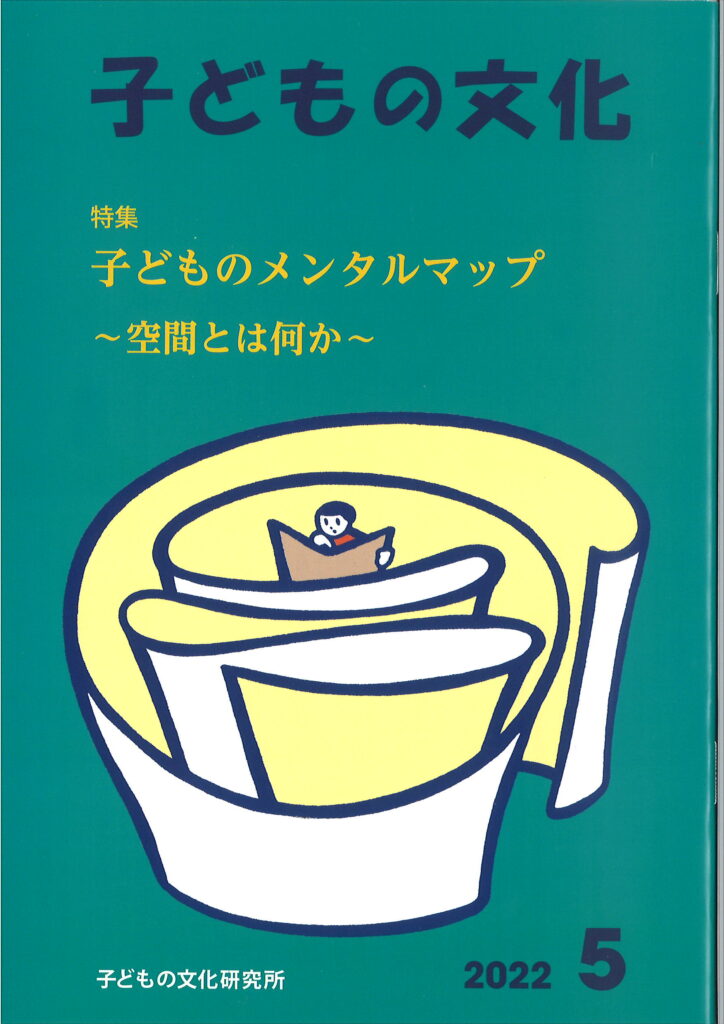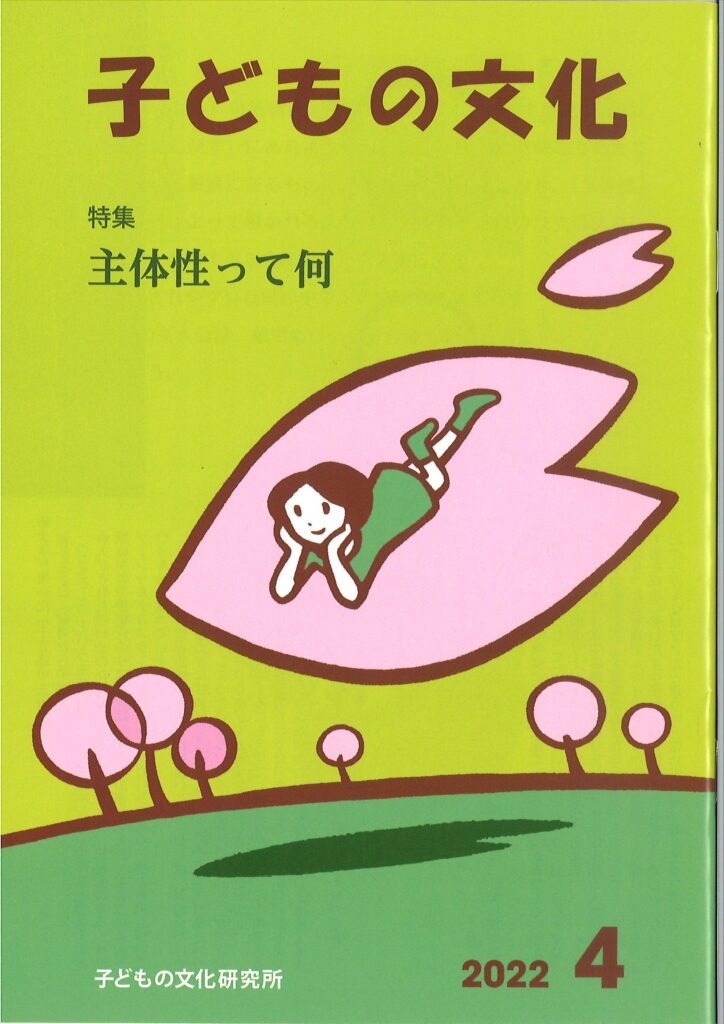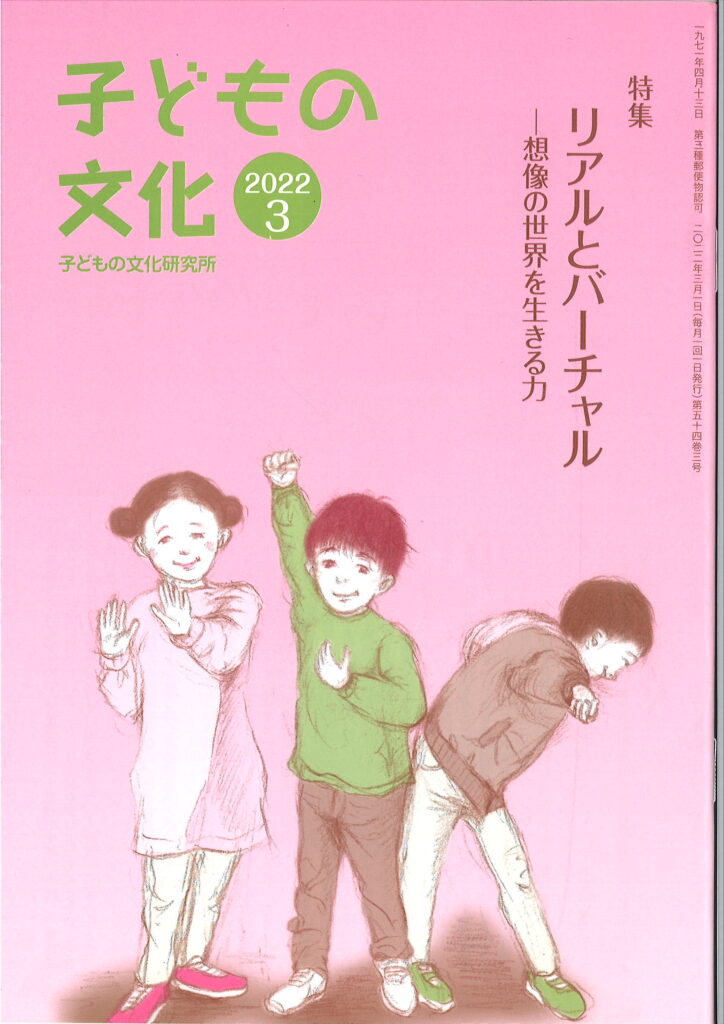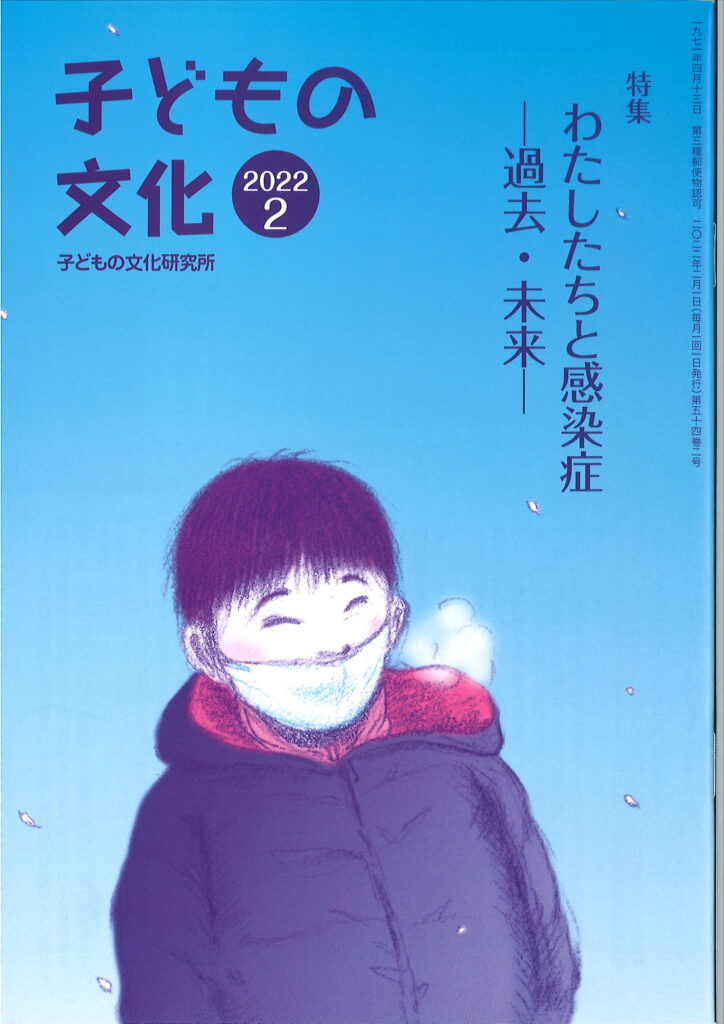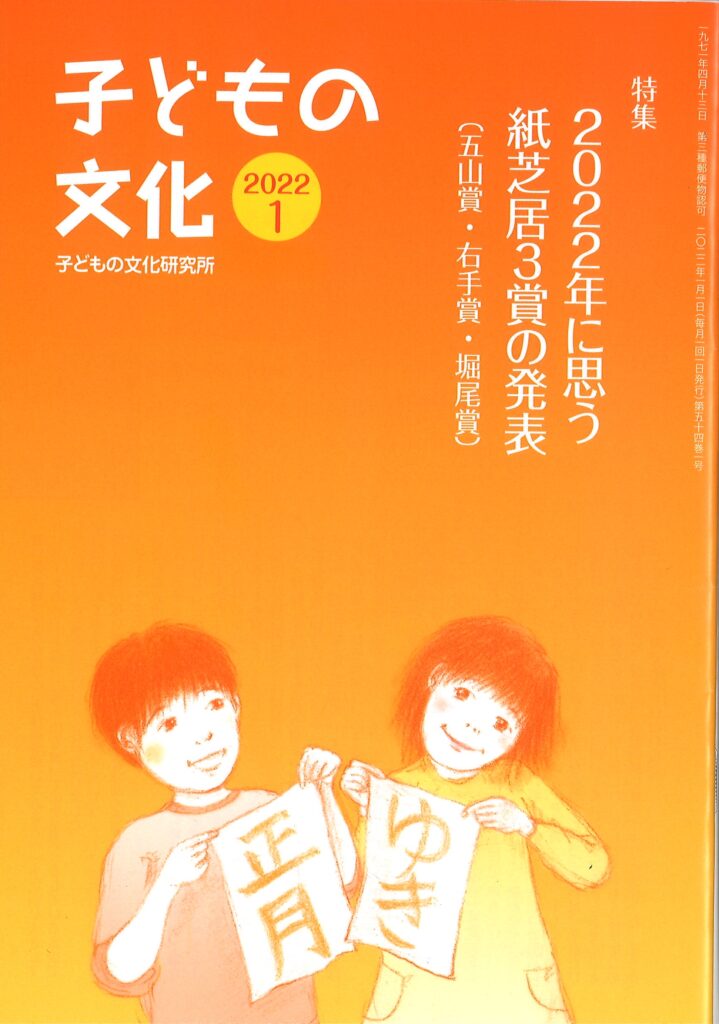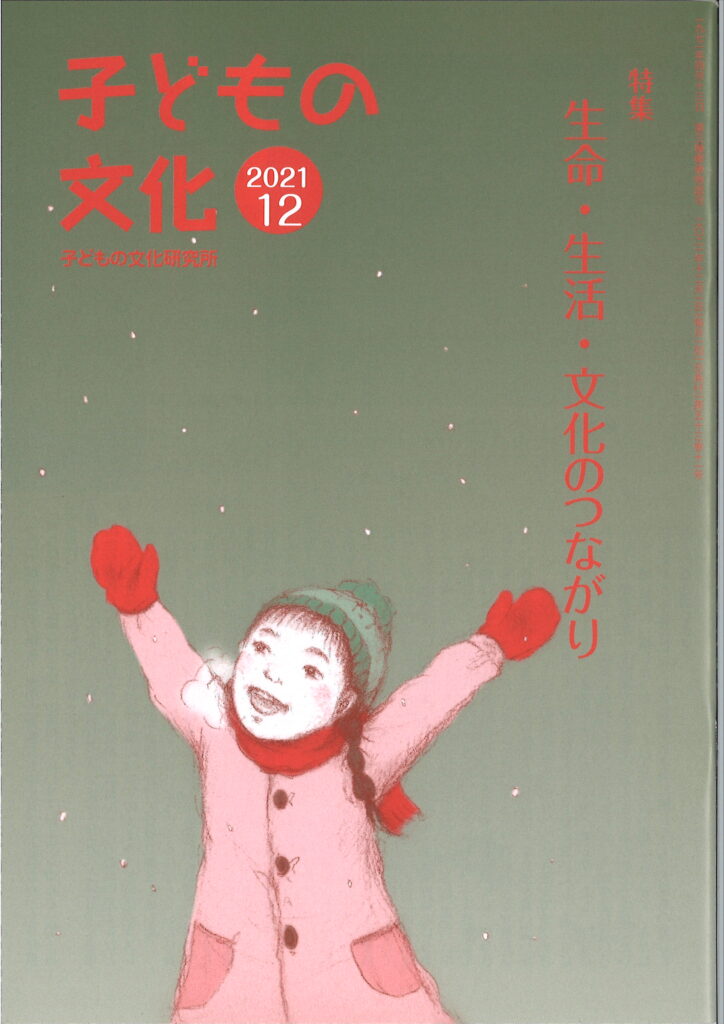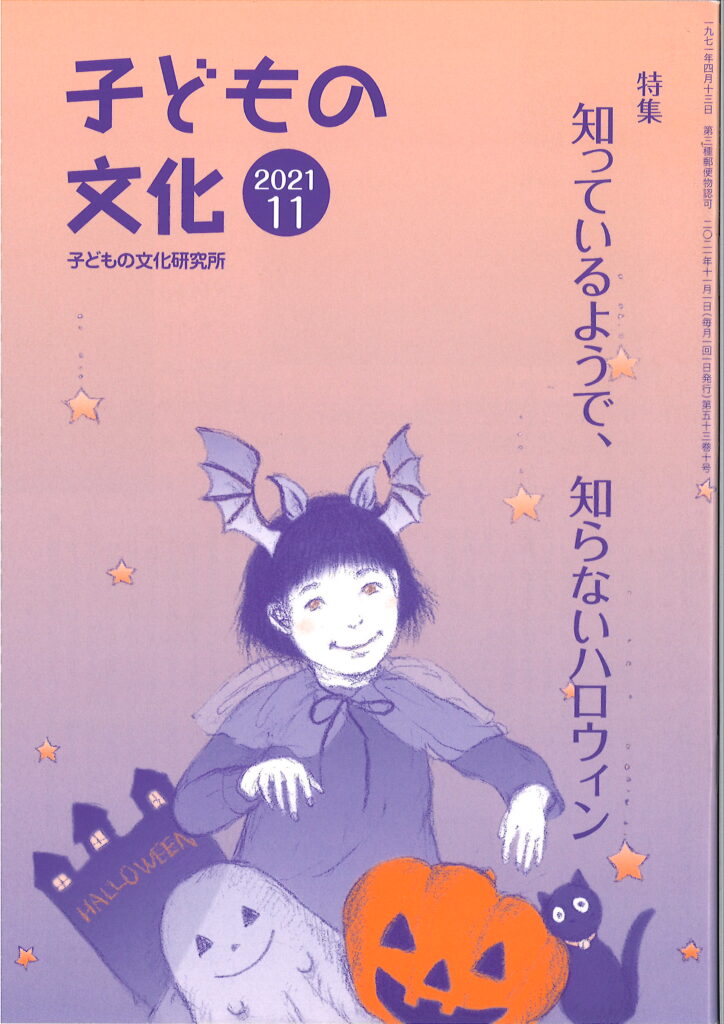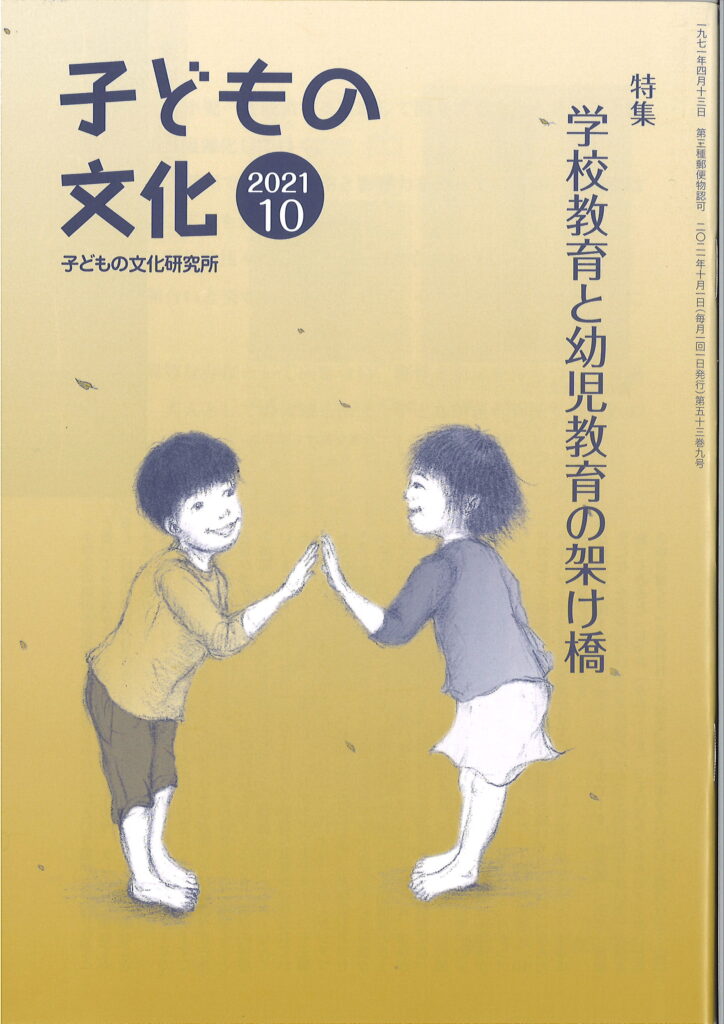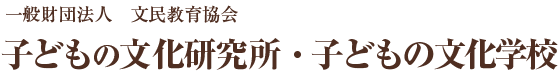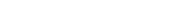月刊子どもの文化・研究子どもの文化
2022年10月号
-
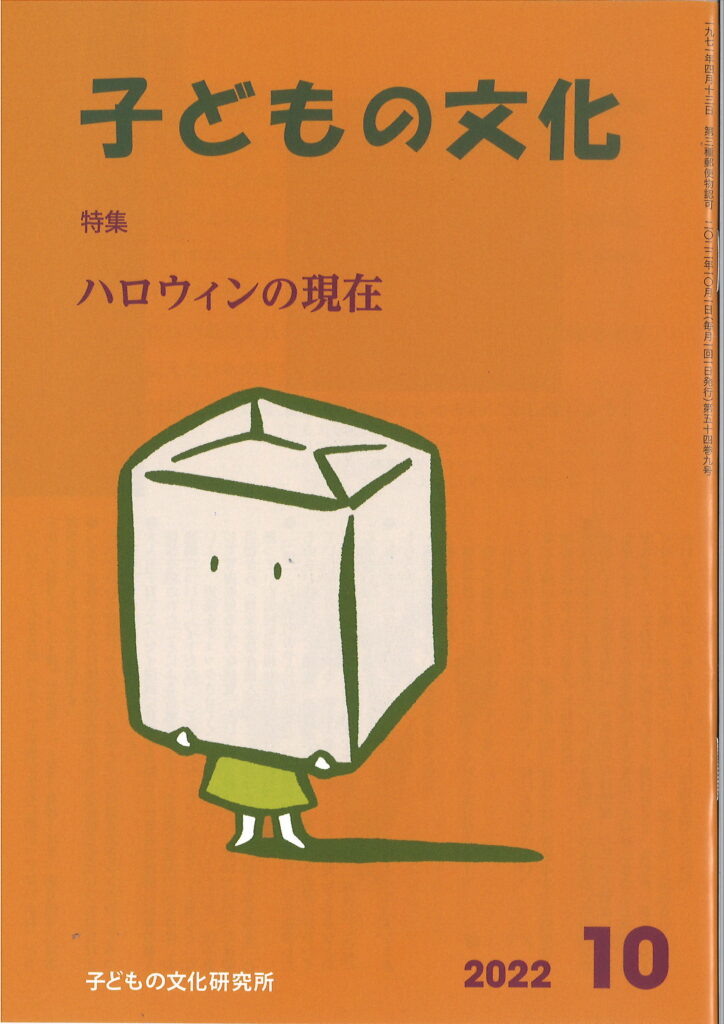
-
2022年10月号
2021年11月号では、ハロウィンを特集し、万霊節や妖怪をキーワードにその歴史や展開、文化論が論じられた。元はケルトに由来する祭礼だったハロウィンはその後、アメリカに渡り、そして現在も「ハロウィン」という言葉は変化を続け、日本でも「渋谷ハロウィン」「地味ハロウィン」などのイベントや商業、娯楽にまでおなじみの存在になっている。渋谷という空間の中に。トリック・オア・トリートのお菓子の中に。子どもの絵本の中に。波間にさまよう「ハロウィン」という言葉にそれぞれの角度から焦点を当て、ハロウィン像の一端を探る特集です。
2022年9月号
-
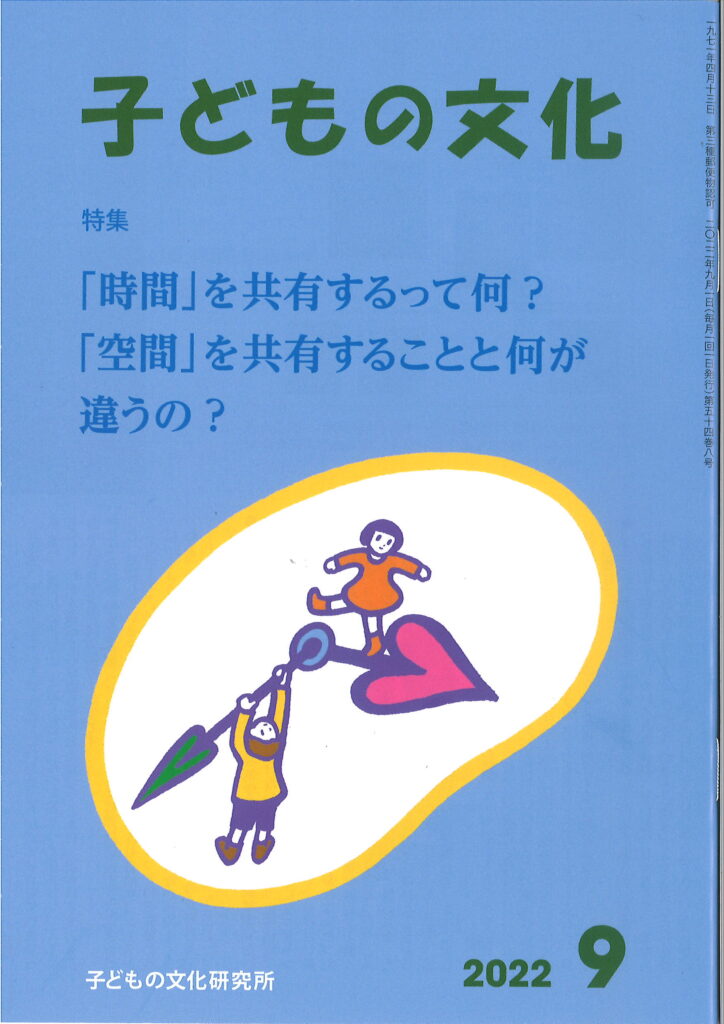
-
2022年9月号
6月号に引き続き、「空間」と「時間」を特集します。「時間」の持つ側面と「空間」の持つ側面とは?
集団生活が多い保育中や子育て中にふと不思議な感覚や不思議な時間にであうことってありますよね。
みんなでつくりあげている「空間」は「時間」の集まりとはまた違った意味合いがあるんじゃないか、
保育や育児から子どもと過ごすかけがえのない「時間」と「遊び」がもつ役割について考えた特集です。
2022年 7+8月合併号
-
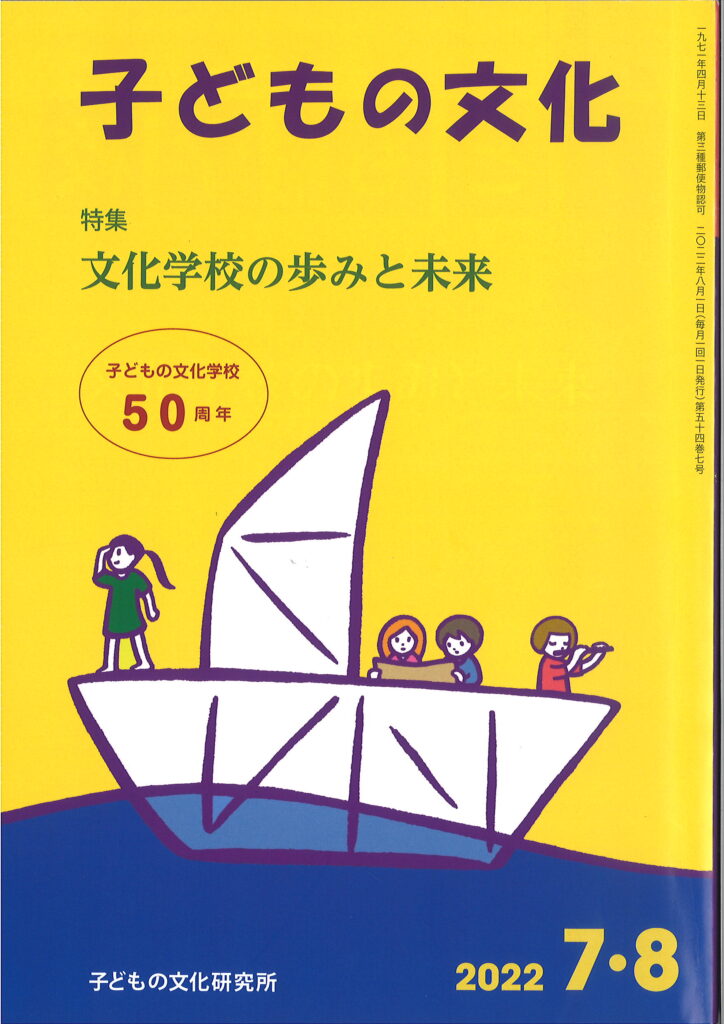
-
2022年 7+8月合併号
50周年を迎えた子どもの文化学校を1冊まるごと特集します!
50年の歴史の歩みを「歴代校長の講義録」と、現学校長加藤繁美先生による解説つきの教室リーフレットで、時代の流れと活動の歴史を振り返ります。
文化学校に通ったことがある人も、そうじゃない人もぜひ一度お読みいただけたら幸いです。
先人たちの言葉と提示する課題は今に通ずるものばかりで、私たちが目指すべきところや忘れてはならない格言にこれからの道筋を考える一冊です。
2022年6月号
-
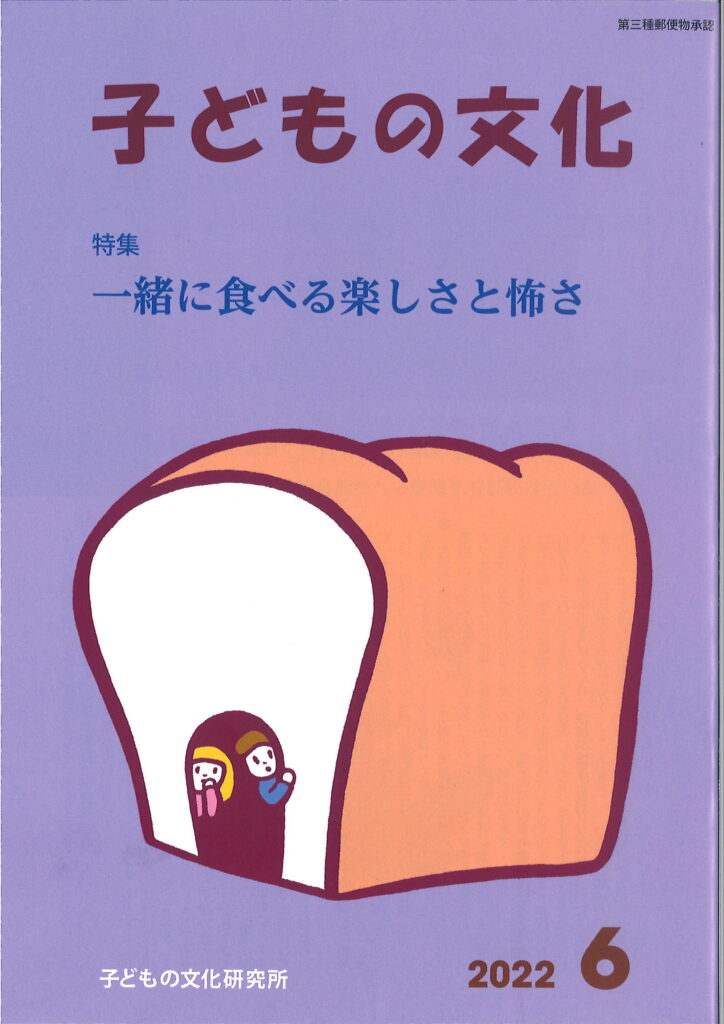
-
2022年6月号
学校では全員一方向を向いてできるだけ席を離した「黙食」が当たり前のような風景になりました。幼稚園や保育所等でも同様です。現場の教師や保育者にとっては苦渋の選択であったことは誰しも想像できます。しかし、子どもたちから仲間と自由に楽しく過ごせる給食の時間を奪ったことに対して、もっと深く捉えなおす必要があります。そこで今回の特集では子どもたちの様々な言動こそ新しい社会を生み出す大切なアンチテーゼだと捉え、より豊かな生き方を模索していきます。
2022年5月号
-
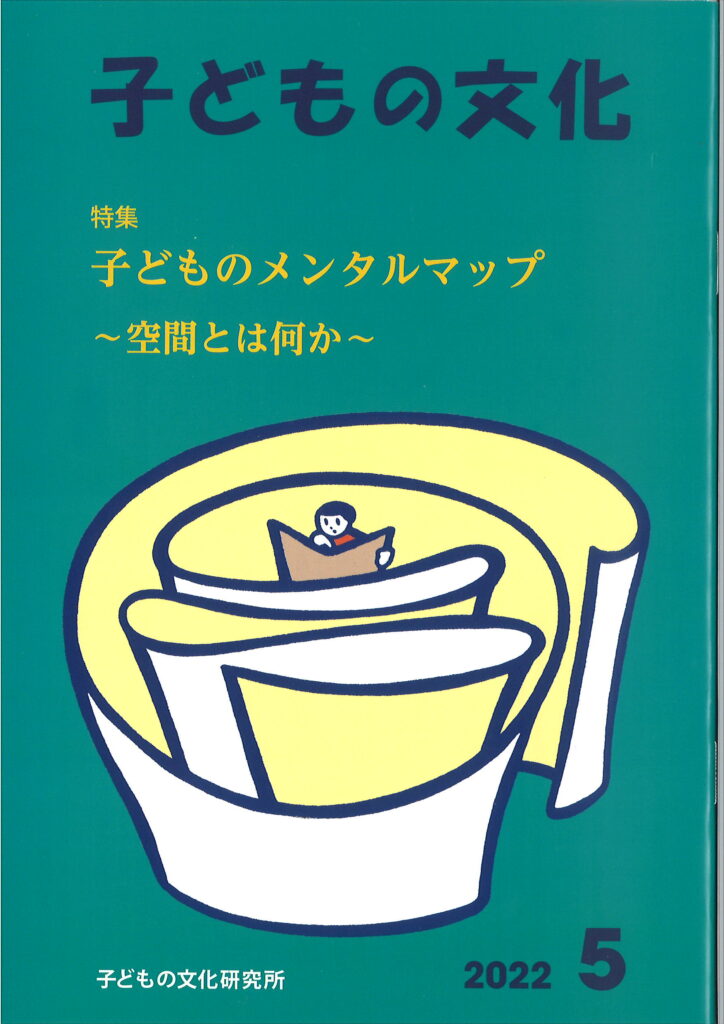
-
2022年5月号
子どもが暮らしの中で空間をどう認知していくのか、子どもの行動範囲は狭いけれど、その生活世界の「地図」を考えると、「メンタルマップ」というキーワードにたどり着く。自分自身の立ち位置を歴史的視点の時間軸ではなく空間的視点でとらえてみる、そんな1冊です。
2022年4月号(品切れ)
-
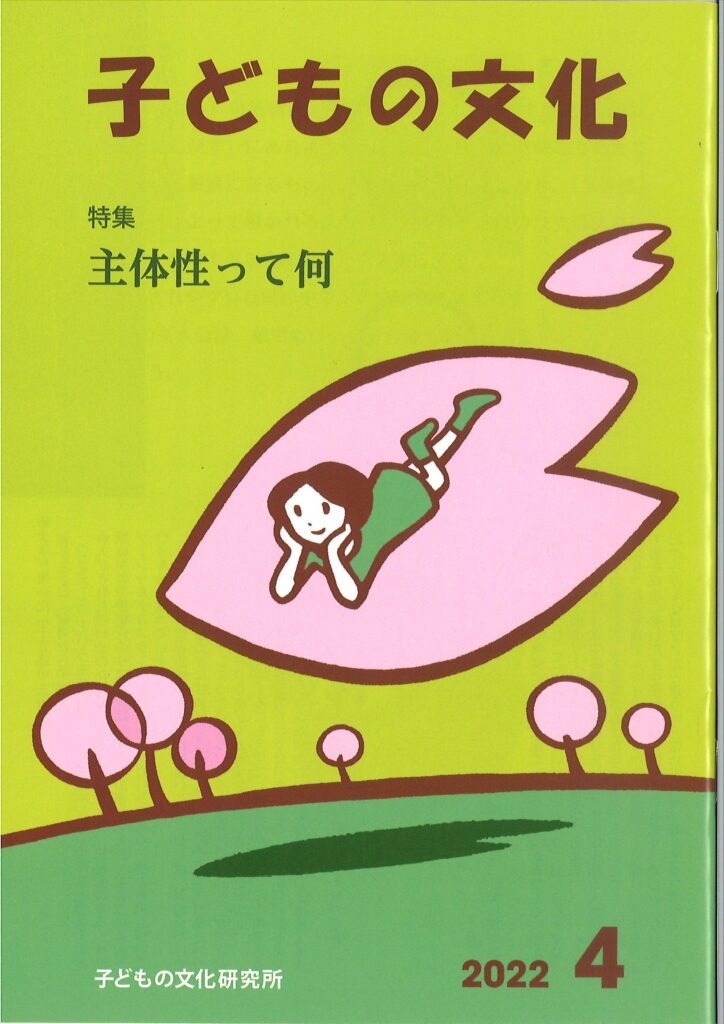
-
2022年4月号(品切れ)
今保育現場では「子どもの主体性を育てる」「主体性を尊重する」といった保育感が主流となり、各々がそれぞれに思い描いた考えで受け止め、実践しています。今回の特集では、「主体性」の真の意味、人間観や世界観の捉え方等を深い処で考えていきます。
2022年3月号
-
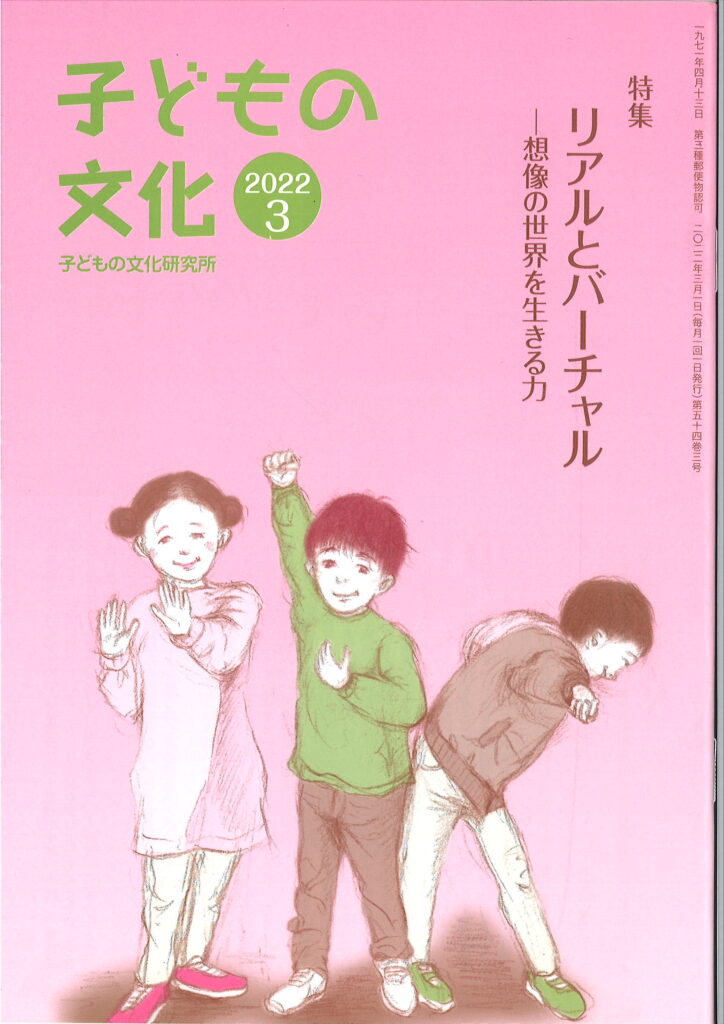
-
2022年3月号
この先も本物に近いVR(バーチャルリアリティ)の世界もどんどん進化していくでしょうし、アバター(バーチャルな世界にいるときの自分の分身)を通してのコミュニケーションもさらに進むと思います。人間がその生命活動において自分で考え、表現し、世界を広げていく能力をどのように獲得していくか、情報に惑わされる社会構造の中で、子どもたちが生きるために必要な「人を信頼し、安心感を持って自己表現しケアされる生活」の重要性について下記の執筆者に登場していただき、様々な角度から考えてみたいと思います。
2022年2月号
-
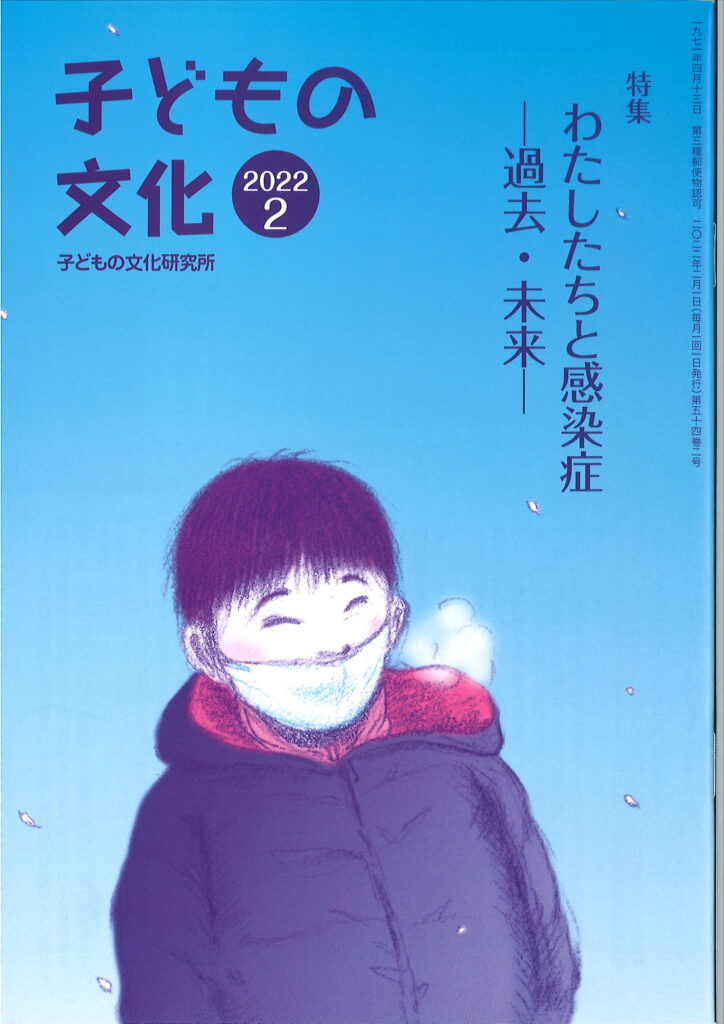
-
2022年2月号
新型コロナウイルスは私たちの生活に大きな変化をもたらしました。
しかし、過去をひもとけば、人類は感染症との闘いの連続だったとも言えます。人類が根絶させた唯一の感染症といわれる天然痘をはじめ、ペスト、スペイン風邪、結核、HIV、SARS等々…。
それらの感染症は文学として描かれたり、童謡やアマビエのような妖怪伝説・民話や、赤物といわれる厄除けの郷土玩具として残ったりと、子どもの文化のなかにもその名残をとどめています。
「子どもの文化」2月号の特集では、感染症をキーワードとして、過去から学び、未来について考えていきます。
2022年1月号
-
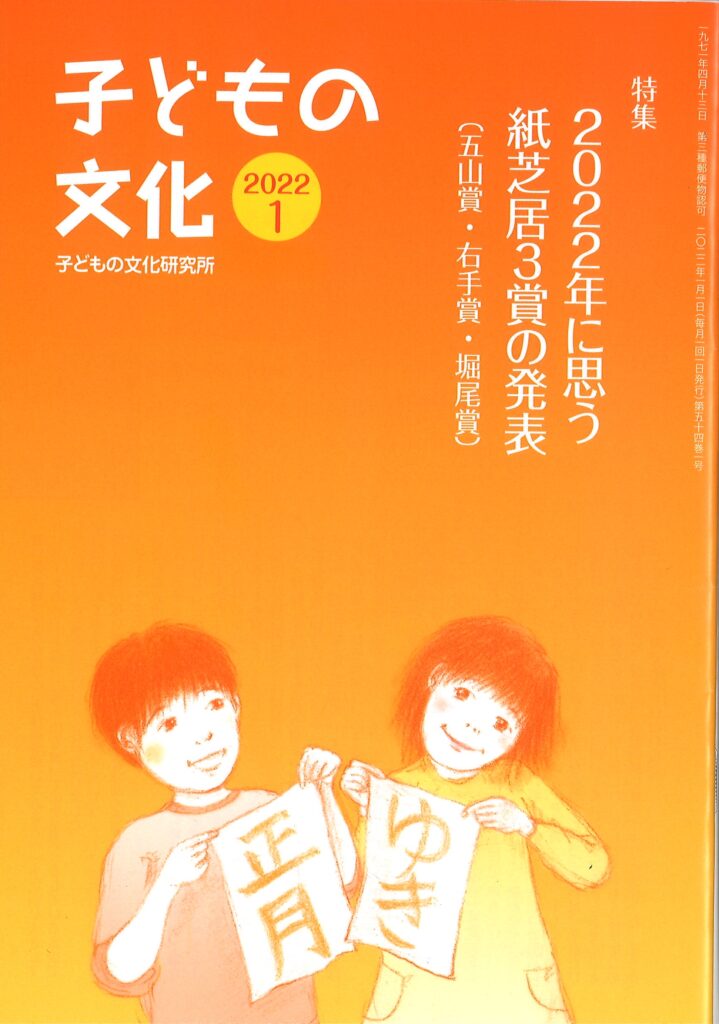
-
2022年1月号
新年の抱負を活躍中の所員に書いていただきました!
新年の明るいスタートを切る特集です。
2021年12月号
-
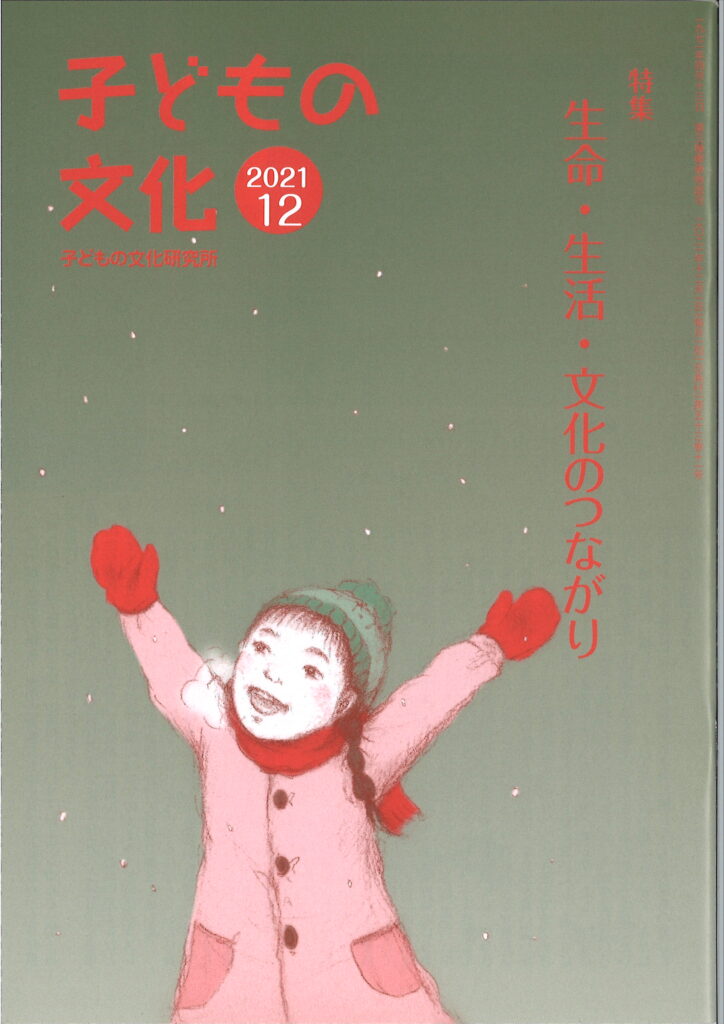
-
2021年12月号
「生命・生活・文化」をテーマに、これらをどう繋いで子どもを育てていくのか―日々の生活と保育実践を通して保育者と教育者・久保健太氏が身近な実践事例を語り合う若さあふれる座談会を筆頭に、
それぞれの先生たちによる座談会を終えての描きおろし原稿も必見です。いきいきとした子どもたちの姿が目に浮かぶような特集です。
2021年11月号
-
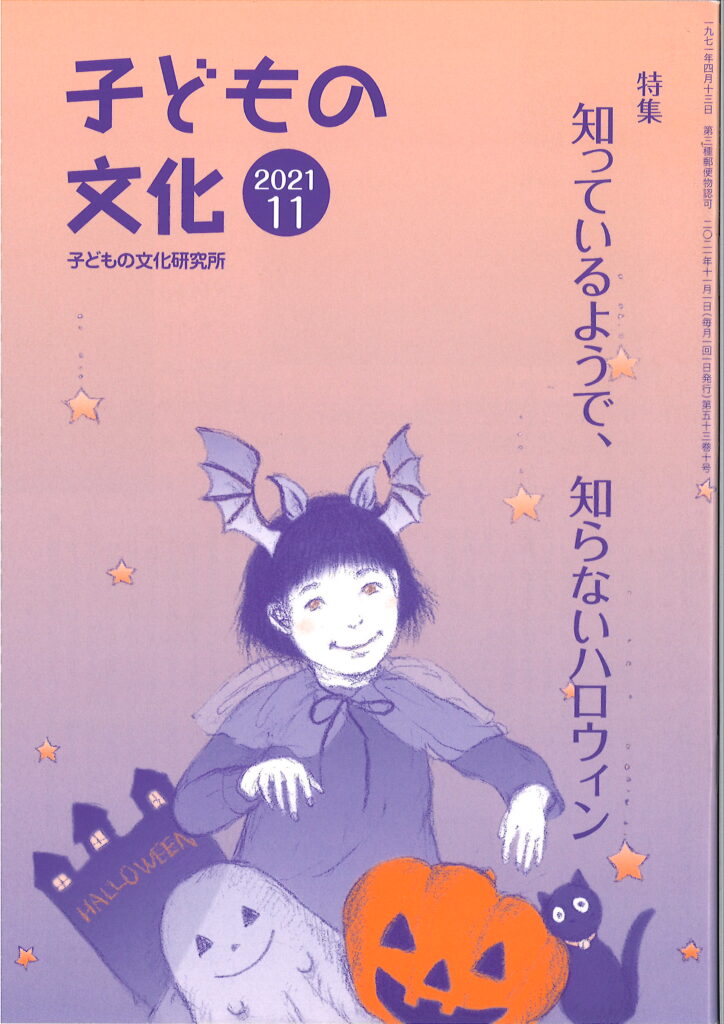
-
2021年11月号
ハロウィンはキリスト教の祭ではない、ということはあまり日本では知られていません。幼児教育の現場である幼稚園や保育所では、クリスマスと同じようにハロウィンを取り入れて行事にしている所も多いですね。そこで今回の特集は、せっかくハロウィンをするならこれくらいは知っておこうという、「妖怪文化論」や「万霊節」の視点からお伝えします。
2021年10月号
-
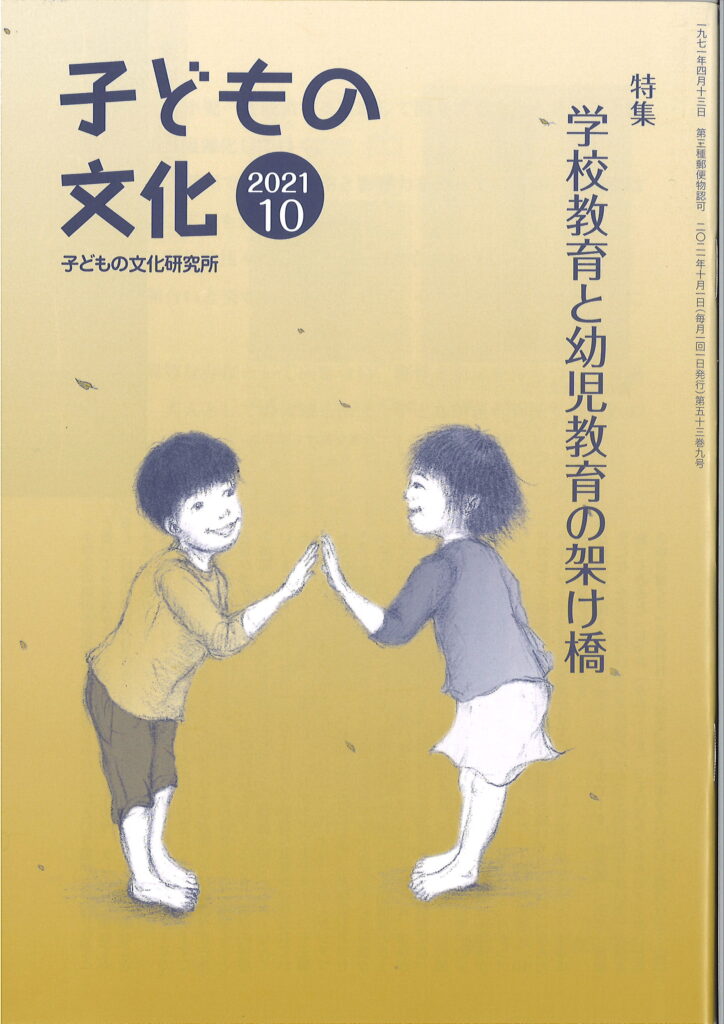
-
2021年10月号
令和3年7月「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」が設置されました。2020年の幼児教育から学校教育まで円滑な接続を目指した改訂では生涯の学びを見据え「主体的・対話的」という教育・保育の進め方が示されましたが、実践の場では中々浸透していきません。それは幼児期の学びが遊びや生活を通して行われるものなのに、いまだに「教える」「学ばせる」という教育方法論から抜け出せないからです。そこで学習指導要領要領の役割とその働きを押さえながら幼児教育、学校教育のなかにある養護的部分に視点を当てながら教育・保育することの重要性について考えてみたいと思います。