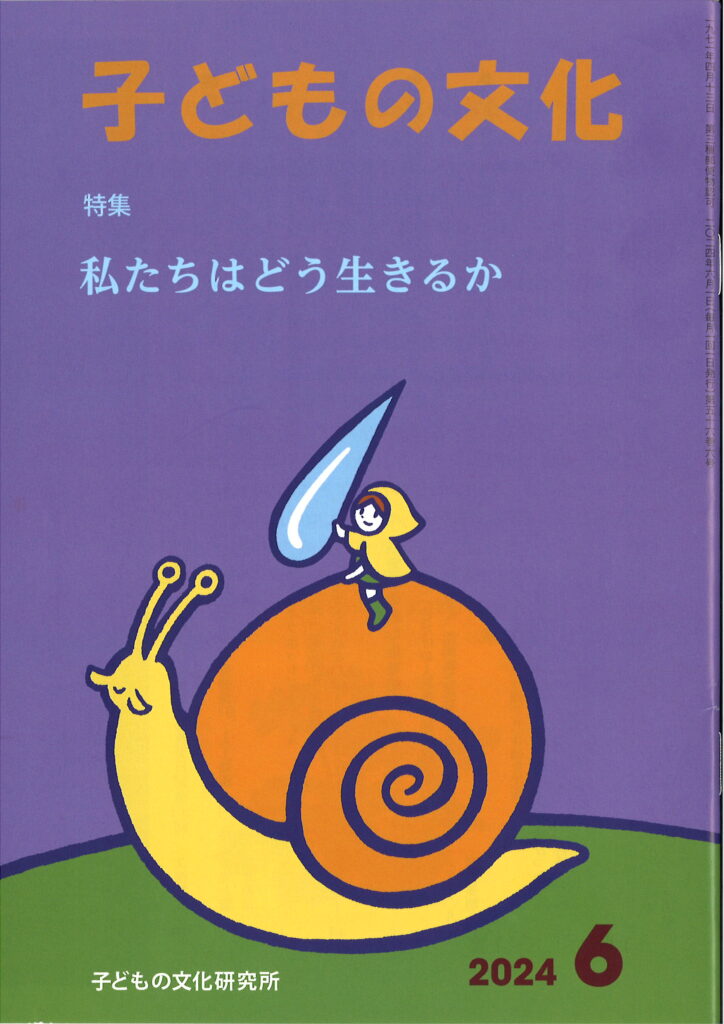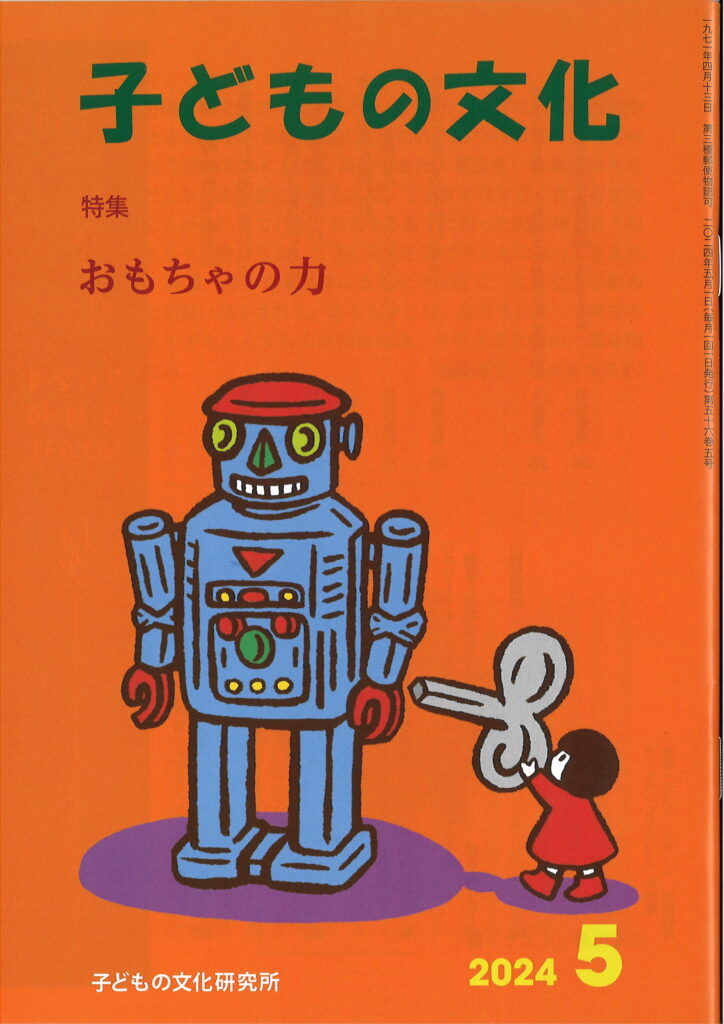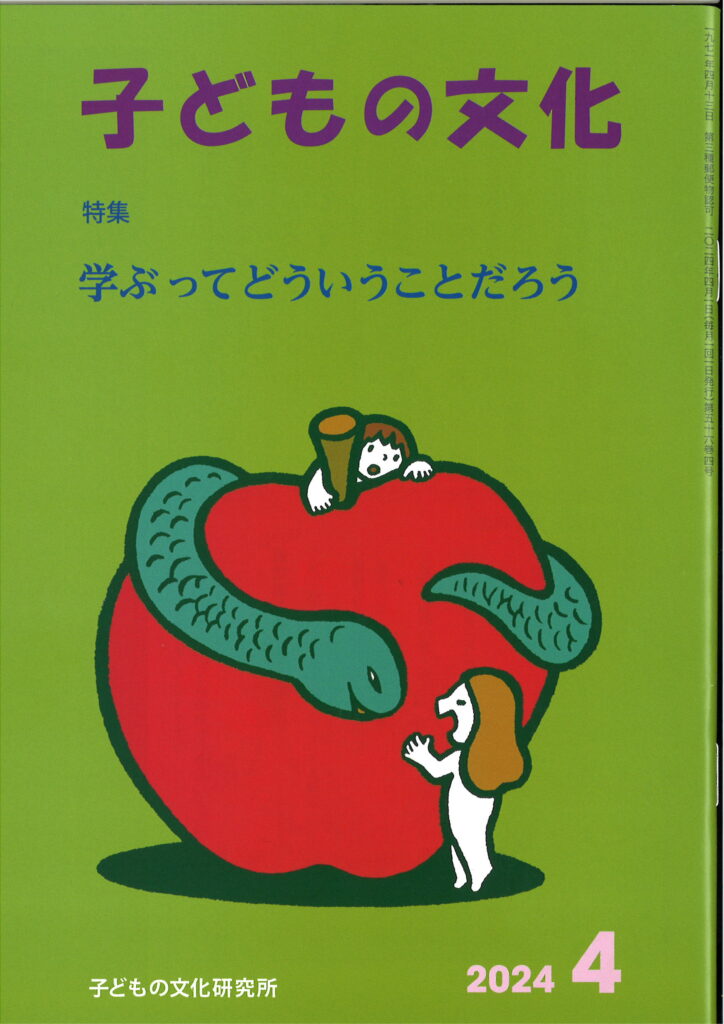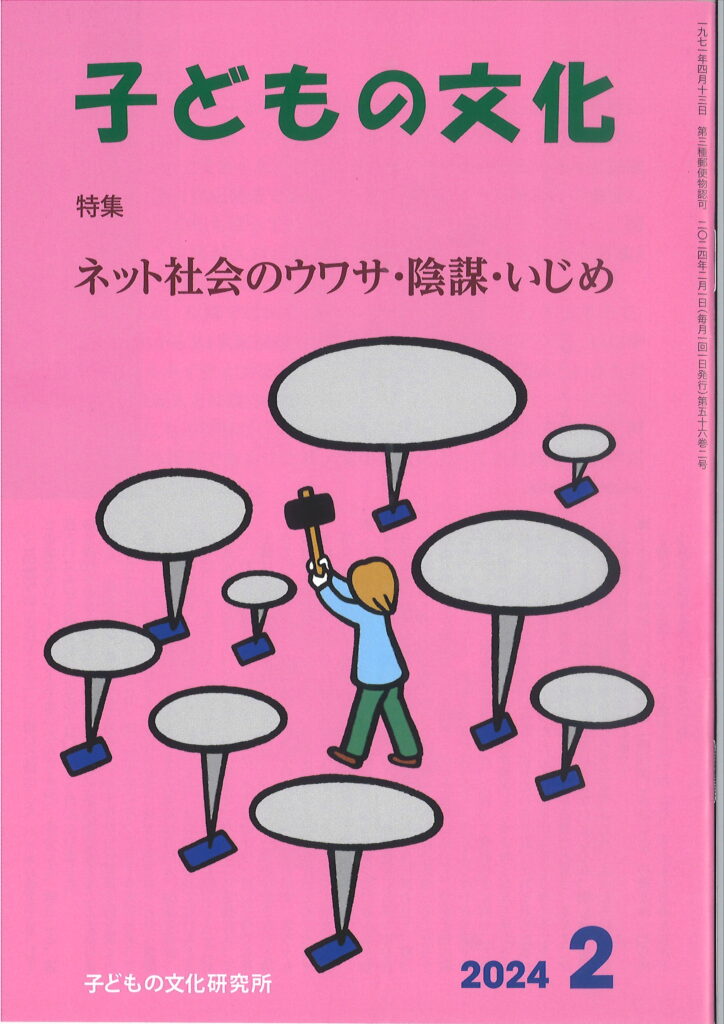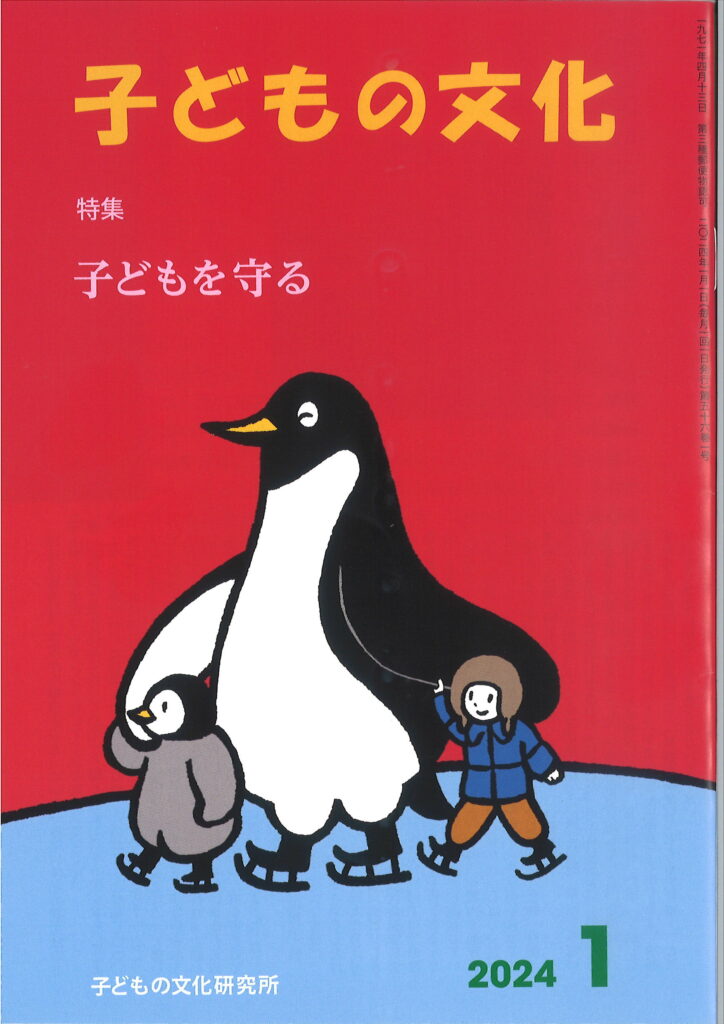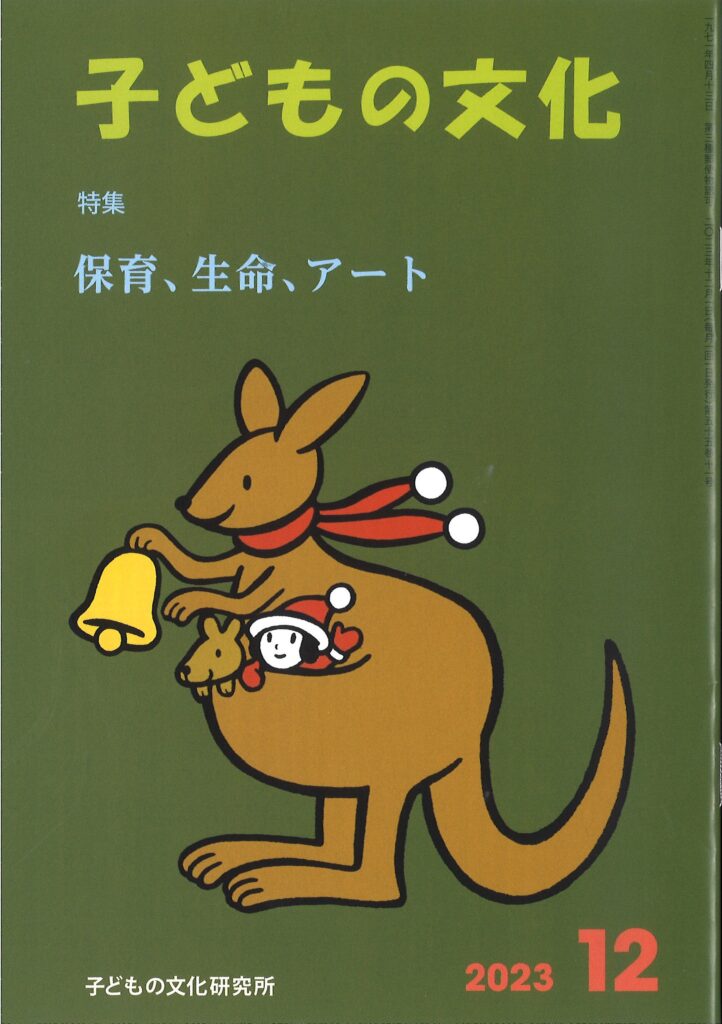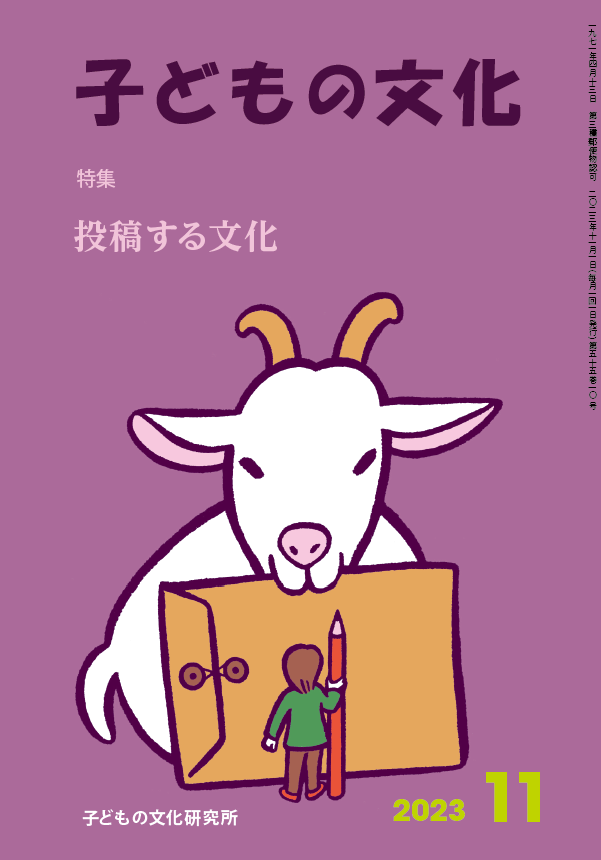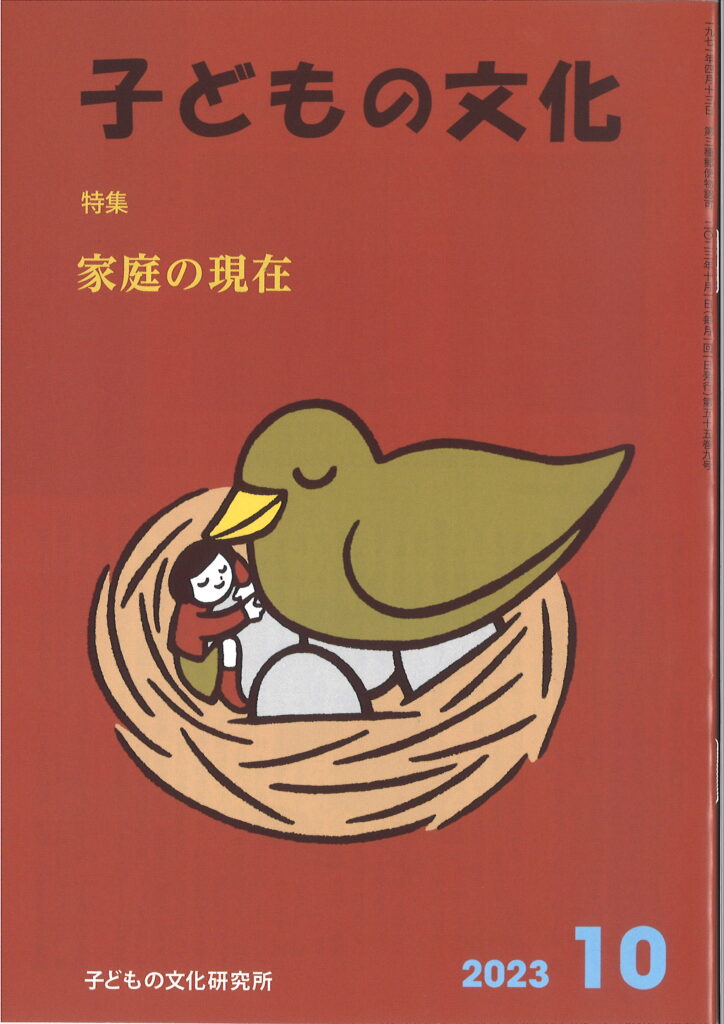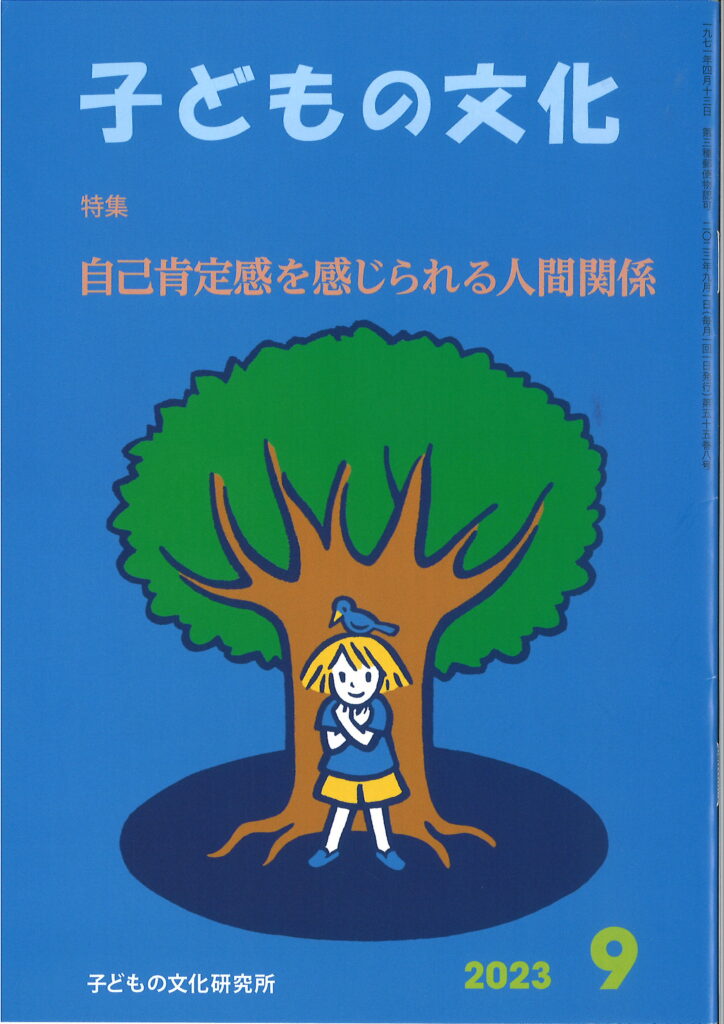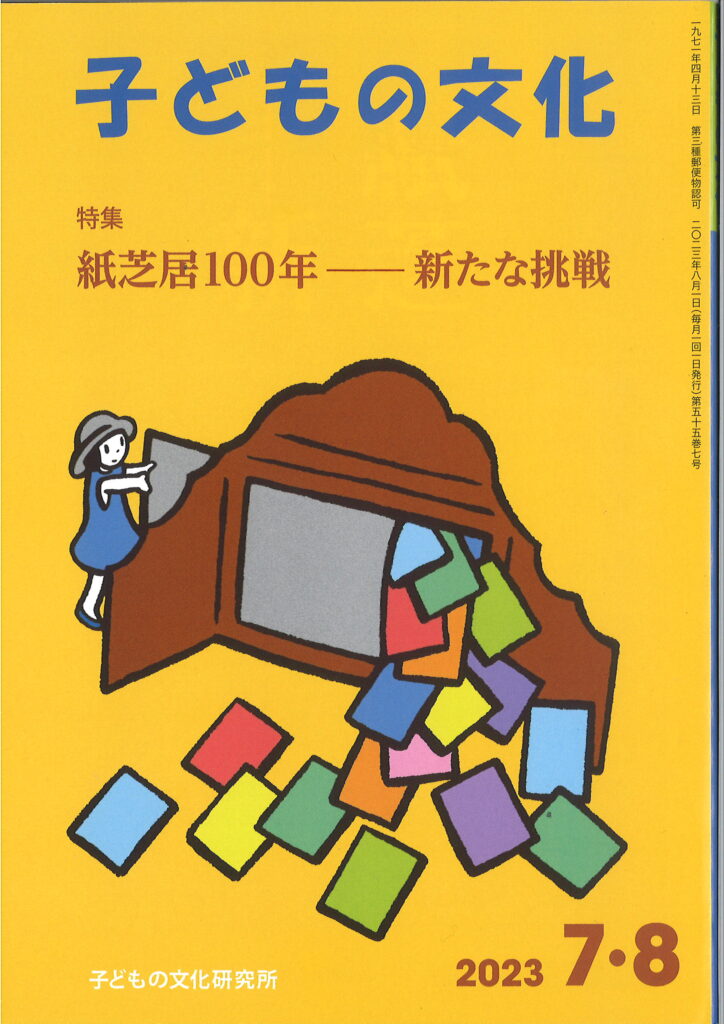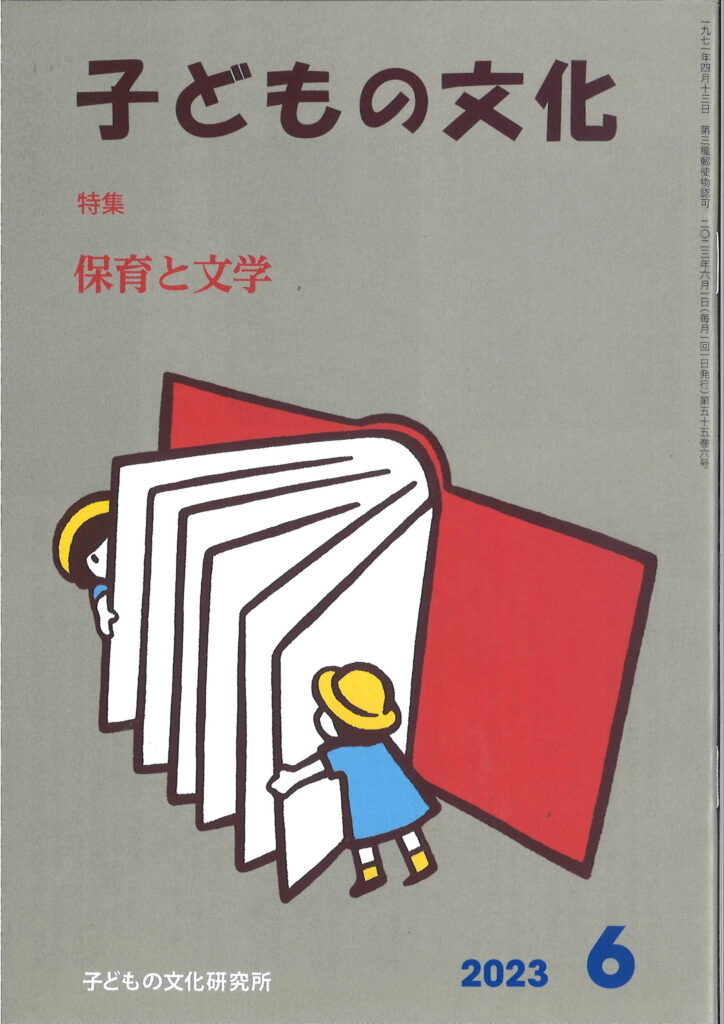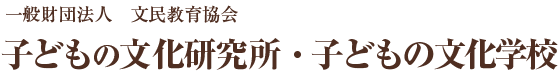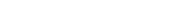月刊子どもの文化・研究子どもの文化
2024年6月号
-
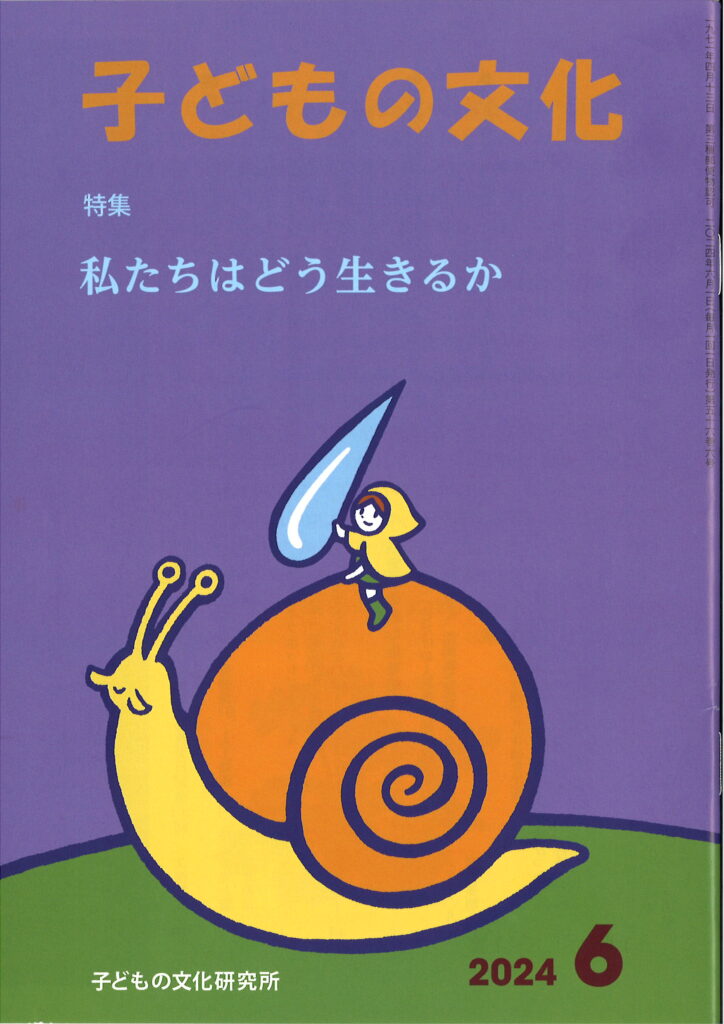
-
2024年6月号
2023年7月、日本国内で大規模な宣伝や試写会をせずに公開された宮崎駿監督のアニメ映画『君たちはどう生きるか』は、これまでの集大成として国際的に評価されている。国内で難解ととらえられた本作は、英語圏では『The Boy and Heron(少年とサギ)』というシンプルなタイトルでヒーローの成長物語として素直に受け止められたのではないか、と捉え方の差も話題になっている。これまでとは違う「戦時下」になった現在、若者たちはこの作品をどう受け止めて、どう生きようというのか、に注目したい。
2024年5月号
-
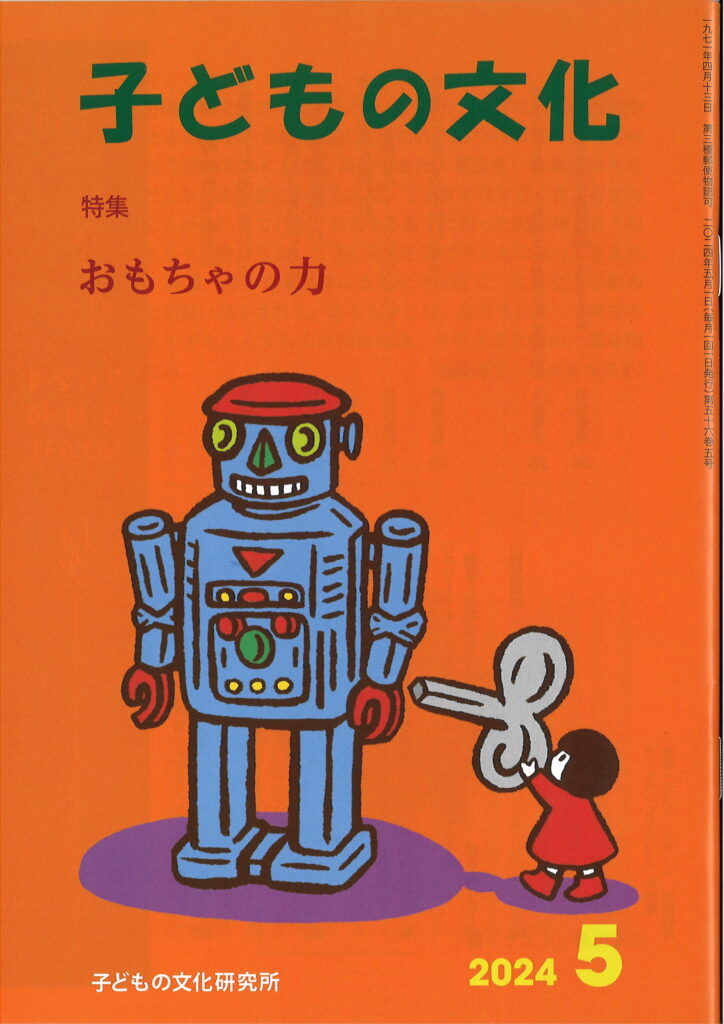
-
2024年5月号
おもちゃの誕生は文字の発明よりも早い。さまざまな年代やさまざまな場でいつの時代もおもちゃは私たちの生活のなかに存在し続けてきた。おもちゃが単なるモノではなく、大きな力を秘めていること、おもちゃとは、私たちにとって何なのか。おもちゃがもたらすものは何か。その大きな力の一端を垣間見る特集です。
2024年4月号
-
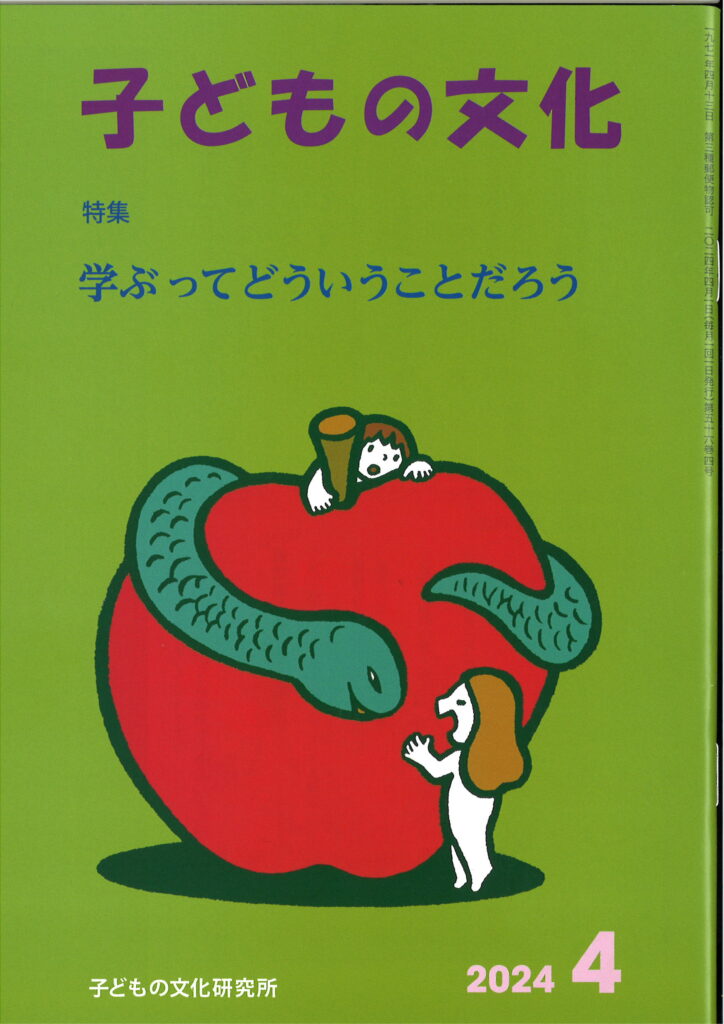
-
2024年4月号
何かを覚えることは、ほぐれていた想像力が、硬直化していくこと、のかも知れない。いや、硬直化していたものをほぐす何かが、自分の中に入ってくる、そんな学びもあるだろう。そんなことを考えながら、学びって何だろうって、若い人たちと語り合ってみました。
新連載 「紙芝居のあしたを拓く」では毎月紙芝居の新しい動きを中心に各地の運動、活動情報、紙芝居史の探索や新しい紙芝居研究などを読者の皆様にお届けします。
2024年3月号
-

-
2024年3月号
年間の特集を振り返り、新たな年度に向けて編集委員が問題をもちよって課題を確認しあった特集です。次年度の年間テーマは「なんだかモヤモヤ」です。このキーワードが意味することは、「ネガティブケーパビリティ」とよばれるいわゆる解決できない問題をそのまま受容する能力をどう獲得していくのかということです。多様性の時代の中で、白か黒かで判断をつけるのは難しく、何でもスマートフォンさえあればどうにかなる利便性のように進化するテクノロジーと比例して失われる力のようなもの、また子どもたちを目の前にすると言葉にできない課題や問題にぶつかることもよくあります。辛抱強く考え続ける力を我々は持てるのか、について考えた特集です。
2024年2月号
-
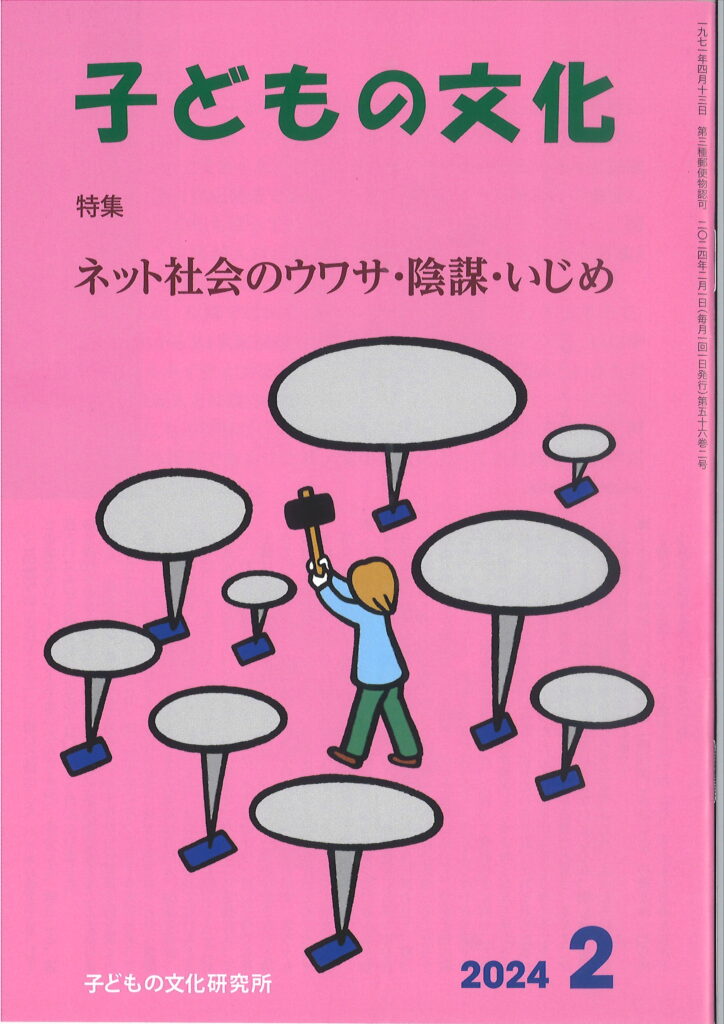
-
2024年2月号
デジタルネイティブ世代の代表としてワニザメ党のメンバーによってSNSでウワサもあっという間に広がる時代に、どんな困難や危険が待ち構えているのか、ネット時代の関係性の構築について論じた特集です。
2024年1月号
-
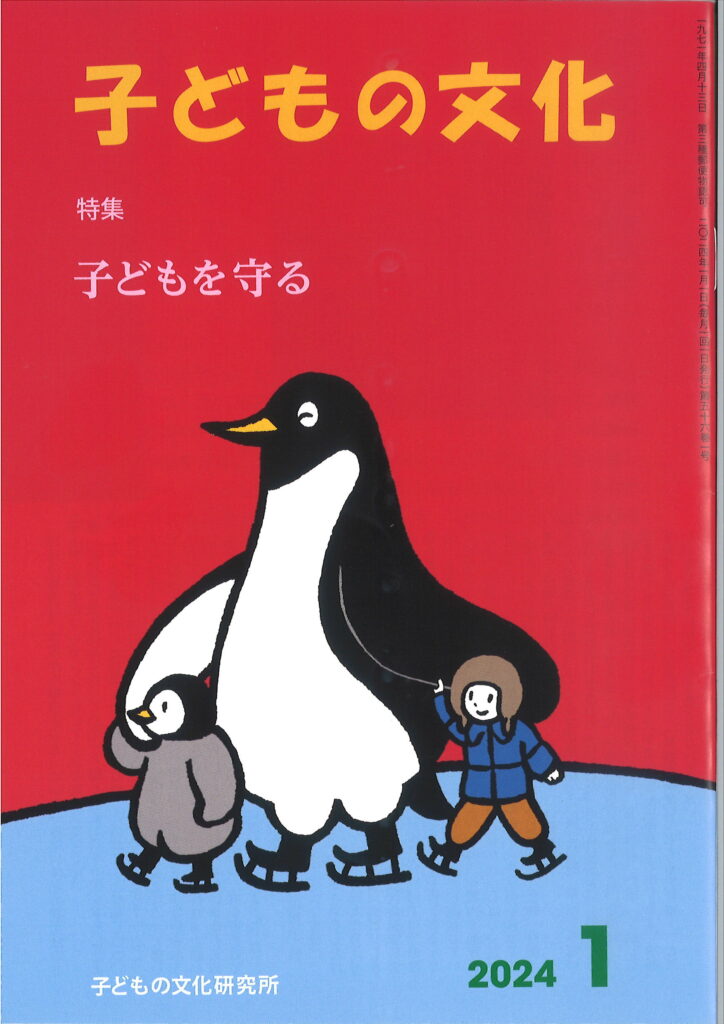
-
2024年1月号
「子どもを守る」ということを考えたとき、「安全」という視点での子育てに息苦しさを感じていませんか。子どもの最善の利益のために本当に必要なものは何か、子どもが育つために必要な環境とは何か、保育者と小児科医・看護師との対話から「子どもを守る」ことを考えた特集です。
2023年12月号
-
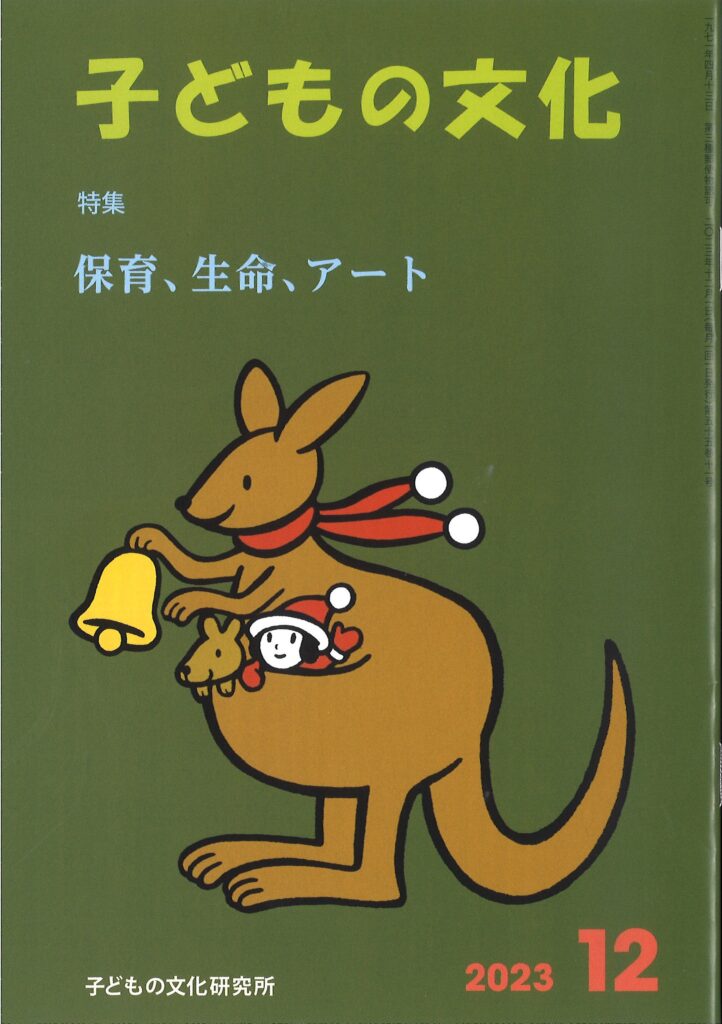
-
2023年12月号
保育は何のために行うのだろう、一人一人が幸せな人生を送るためでしょうか。子どもたちの遊びには「アート」に通ずる表現力があります、そんな子どもたちの遊びの様子から、
保育・生命・アートをキーワードに教育現場からは「久保健太先生」・保育者からは「齋藤紘良先生」・アーティストで作曲家の「トクマルシューゴさん」の3人が対談します。
2023年11月号
-
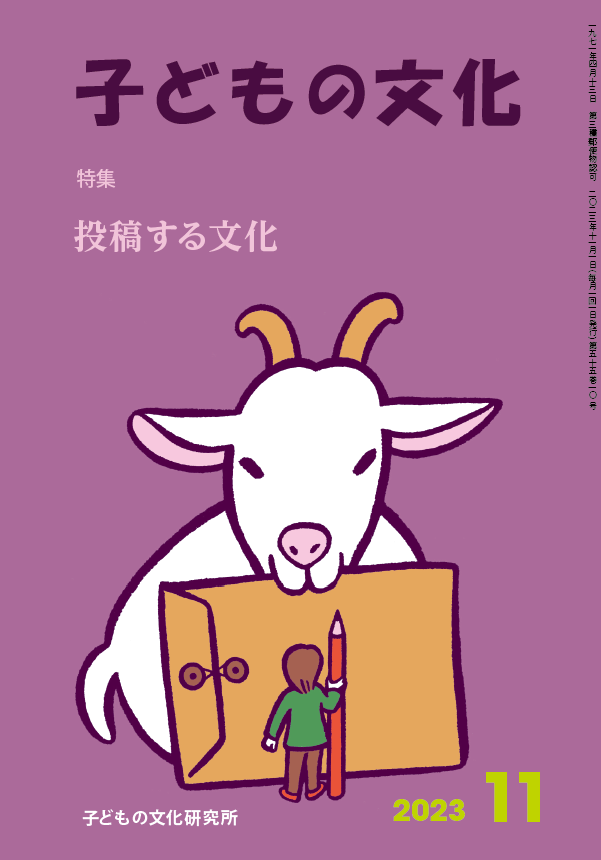
-
2023年11月号
迷惑動画や国会議員の不適切な投稿などSNSから広がる波紋が話題に上った1年でした。それでもなぜ人は「投稿」したくなるのでしょうか。明治時代からさかのぼり、「投稿文化」に見られる心理と現代の「投稿文化」に見られる特徴をそれぞれの専門家の立場から論じます。
2023年10月号
-
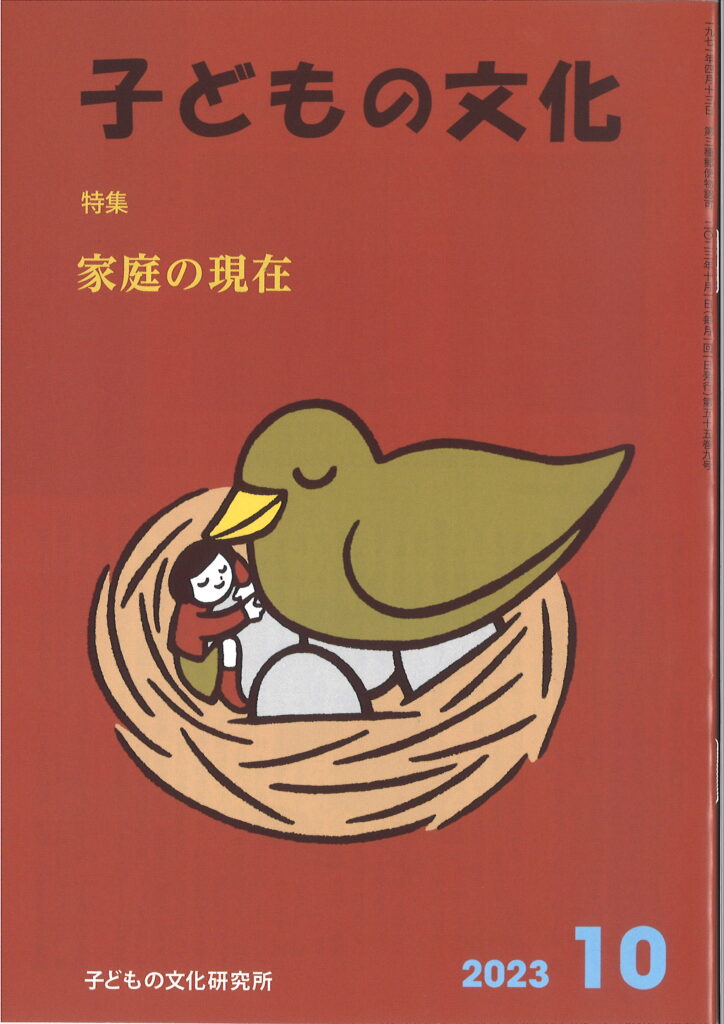
-
2023年10月号
このところ子どもの安住の場であると思われていた「家庭」が揺らいでいる。夫婦別姓問題、LGBTの結婚制度、一人親家庭の貧困、宗教2世虐待、家庭教育を支援する条例制定、カルト団体の選挙介入等々。あまりに議論百出で何が何だかわからない。何しろ、こどもを真ん中にすえた初の中央省庁だったはずの「こども庁」は、いつの間にか「こども家庭庁」に替えられてしまった。そこで、そもそも「家庭」とは何であったのかを、さまざまな立場、方法論から検証してみることにした。
2023年9月号
-
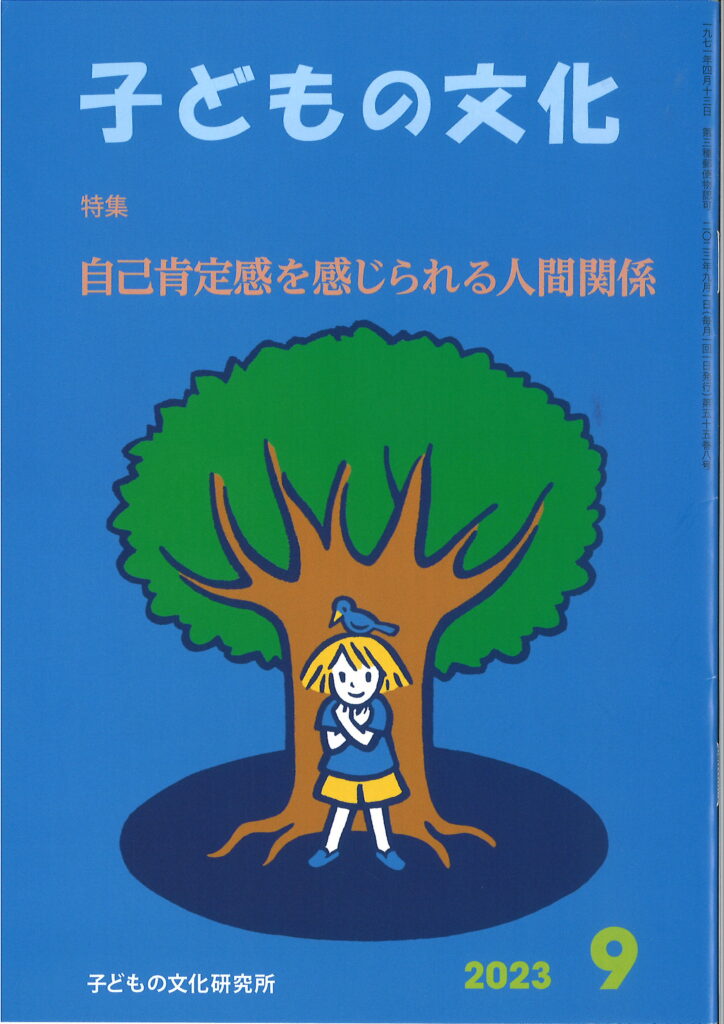
-
2023年9月号
自己肯定感の重要性が注目されて久しいが、浜谷直人氏から『自己肯定感』は「育てたり、高めたりするものではない」「仲間にとって自分は価値があり、大切だと思ってもらえていると感じることができるということ」「先生が子どもを褒めることは、自己肯定感を感じることができないクラスになってしまう」という提言を発展させた対談。自己肯定感が感じられる集団の実践例が示され、自己肯定感をとらえ直す特集です!
研究子どもの文化
-
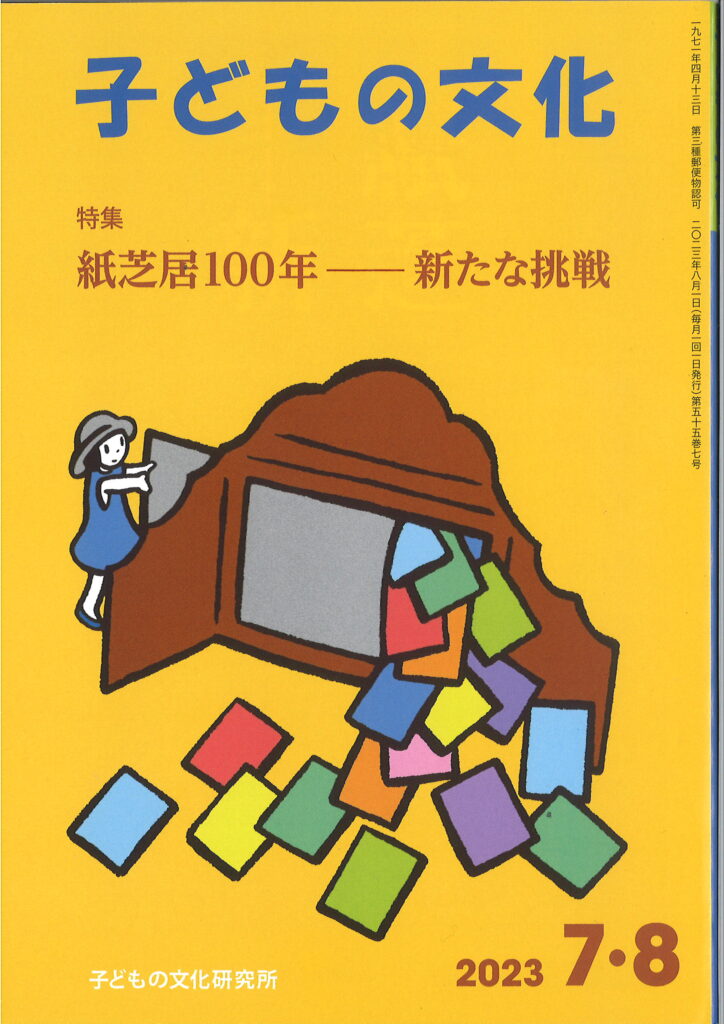
-
紙芝居100年の歴史を刻んだ紙芝居人の歩みとこれからの時代に向けてどう発展させていくのかを問いかける1冊です。高橋五山や上地ちづ子などの足跡を振り返りながら、地域で活躍する紙芝居運動の取り組みや、紙芝居が求められる新たな役割など紙芝居の再発見と魅力にあふれる特集です。
2023年6月号
-
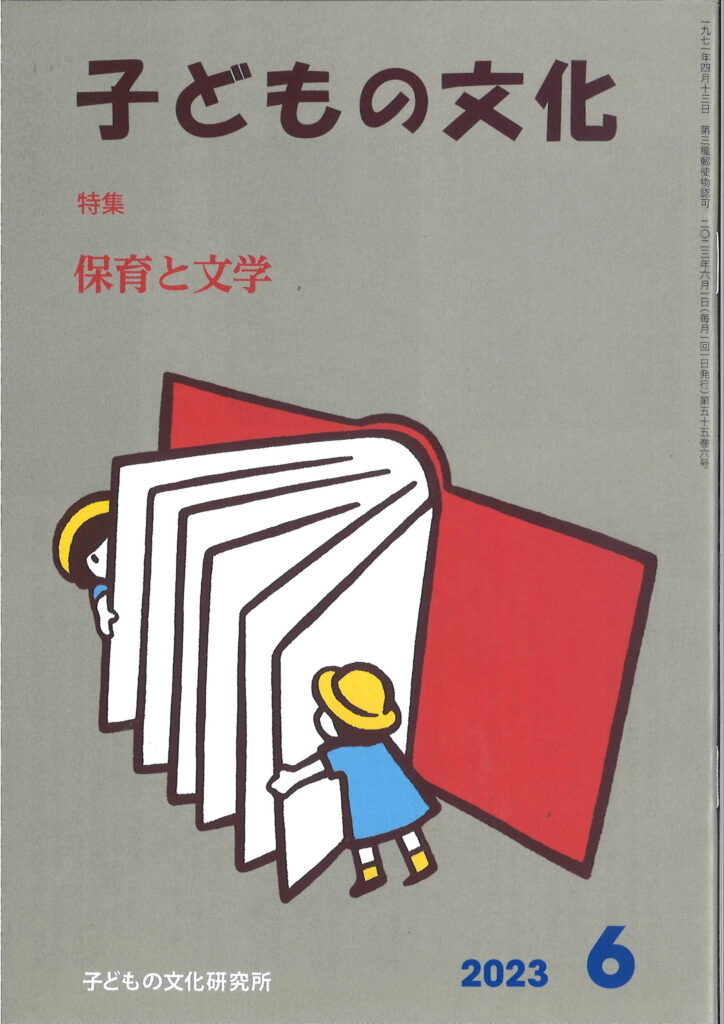
-
2023年6月号
「保育記録」を文学のようにとらえたら、どういう記録が生まれるんだろう。客観的な事実の記録という側面の強い保育記録を、主観的事実ととらえたり、文学作品のように人称をあいまいにしたり、時制をいったりもどったりすることで新しい切り口や子どもの姿が見えてくる。そんな座談会を現役保育者と教育者・小説家が集まってそれぞれの立場から語り合いました。