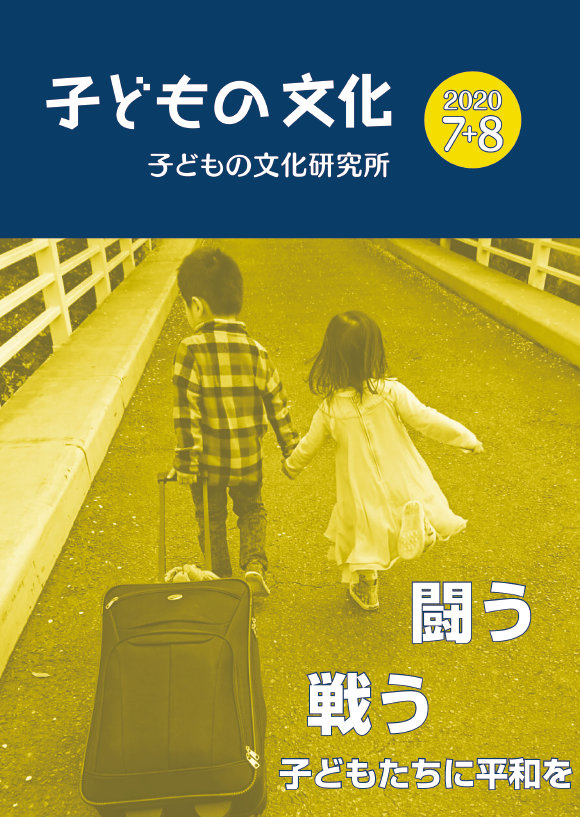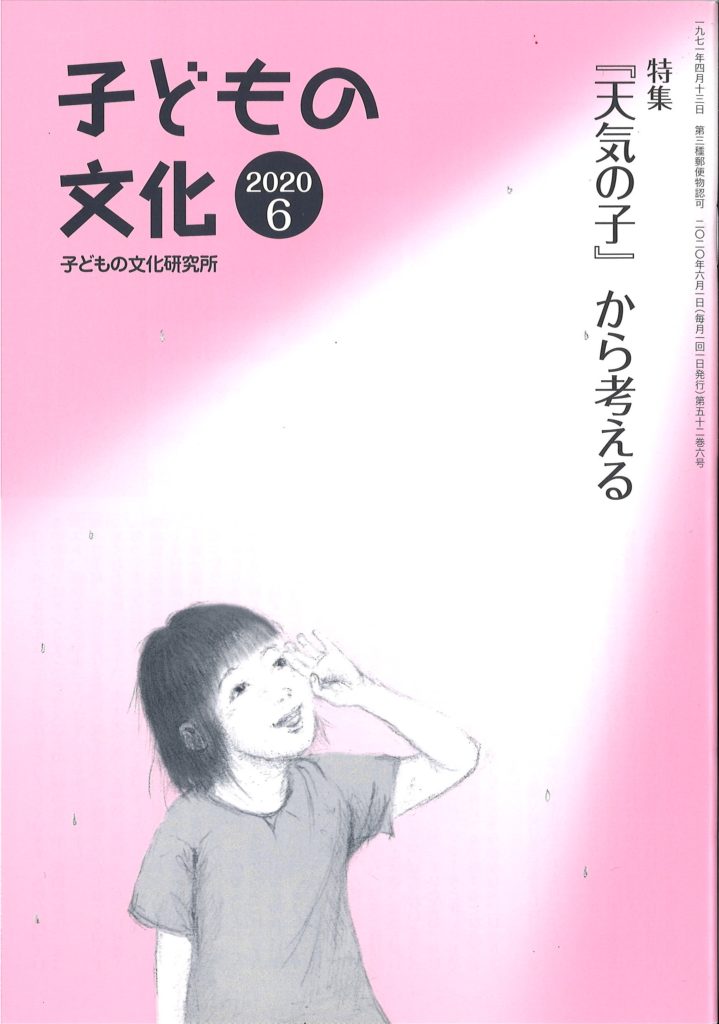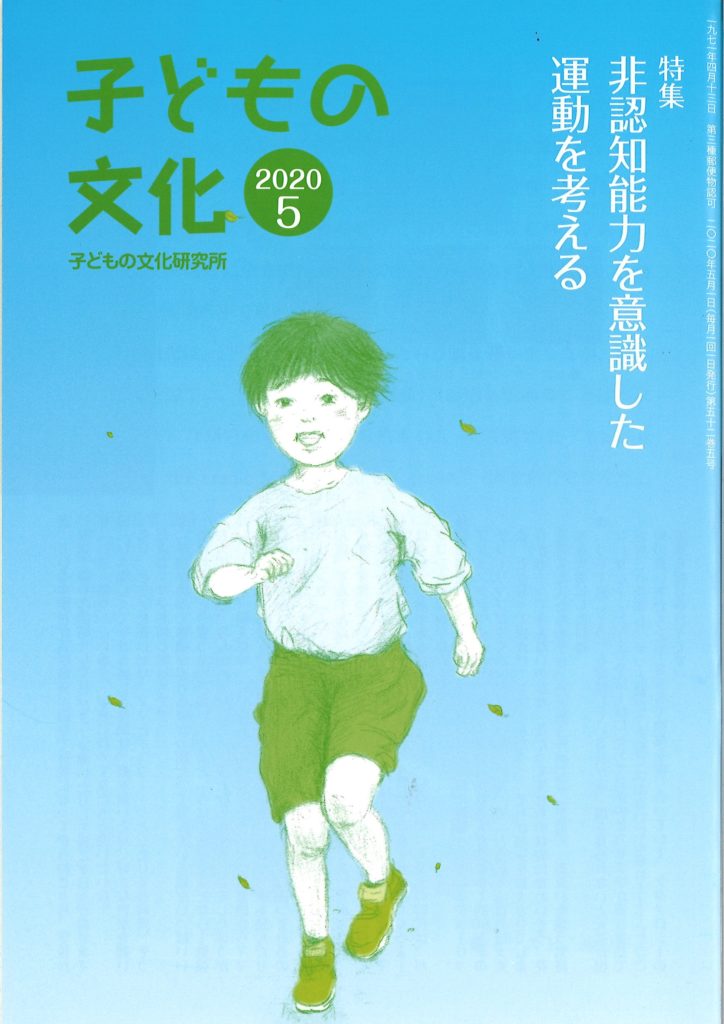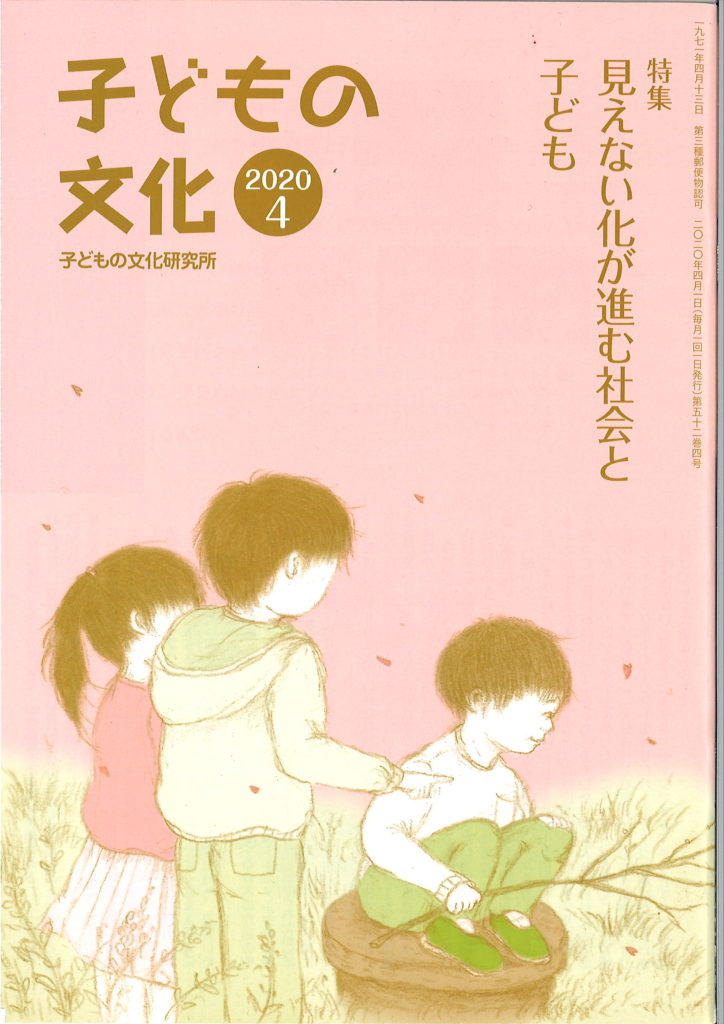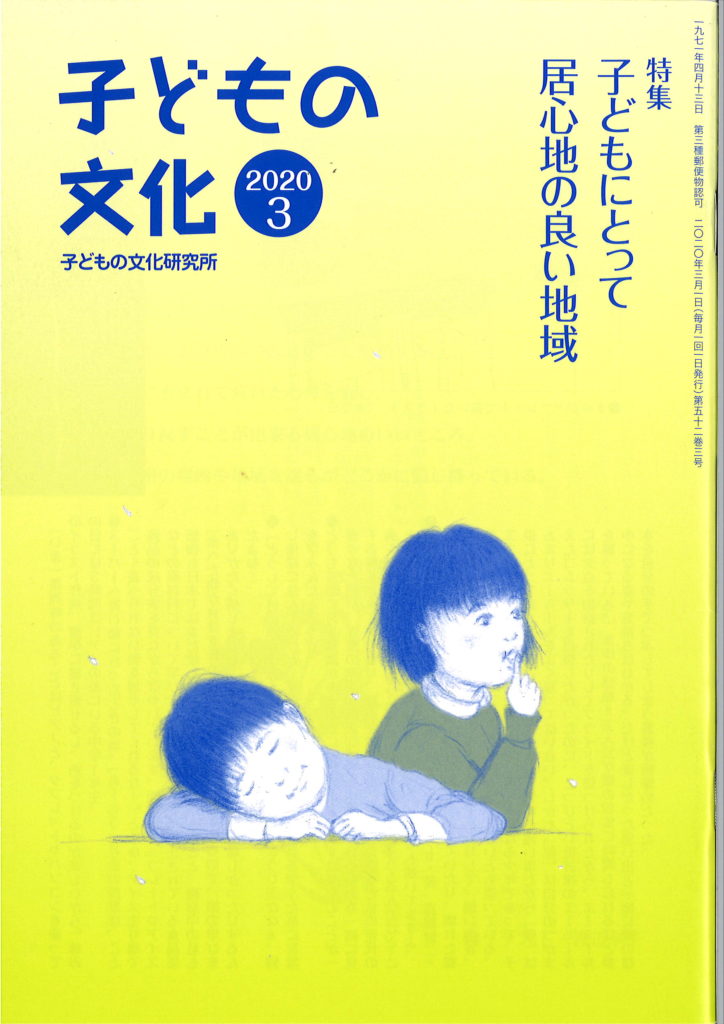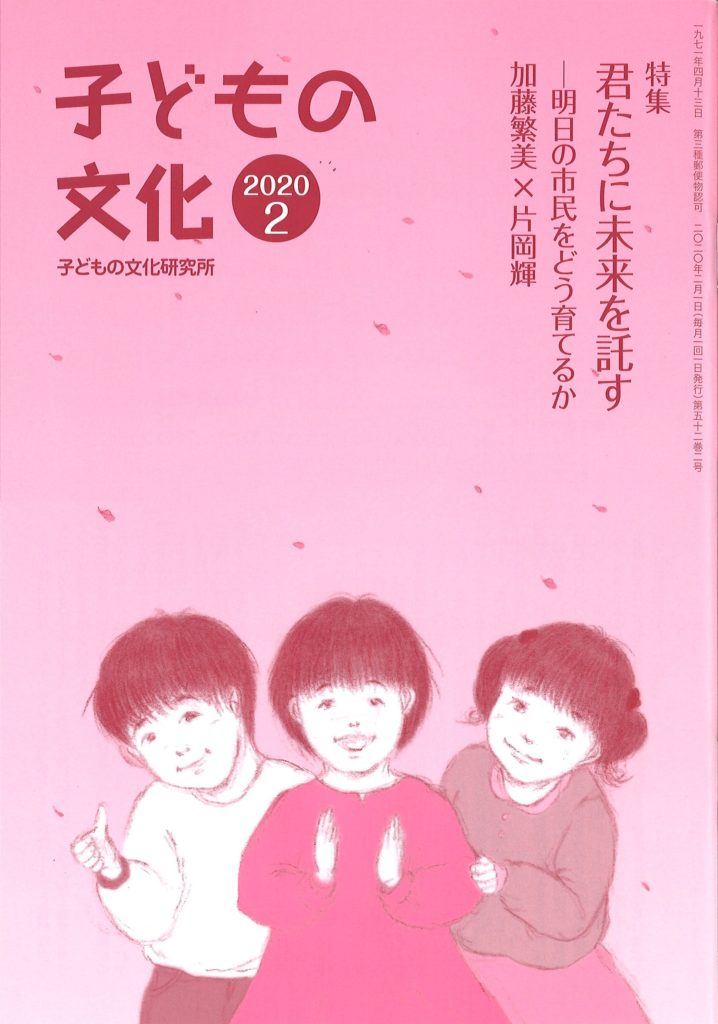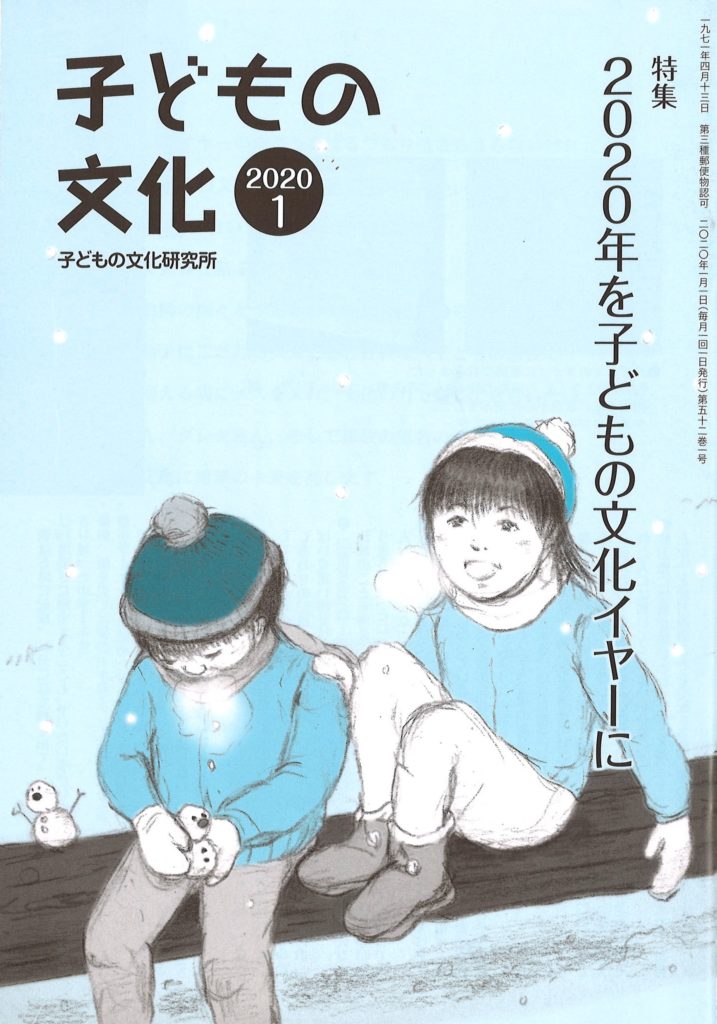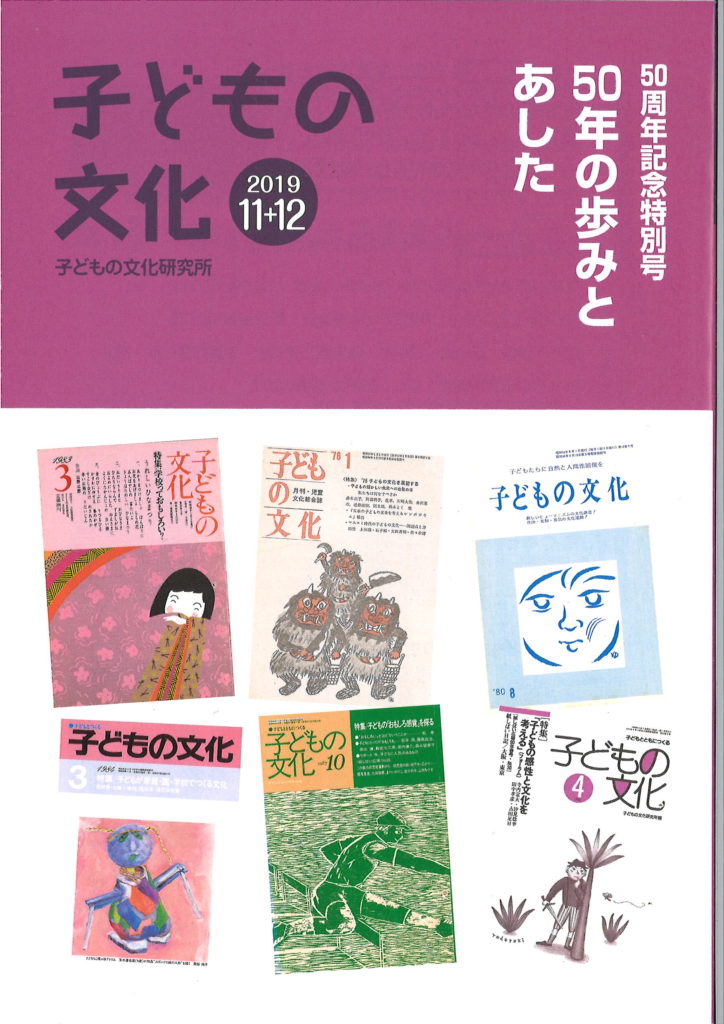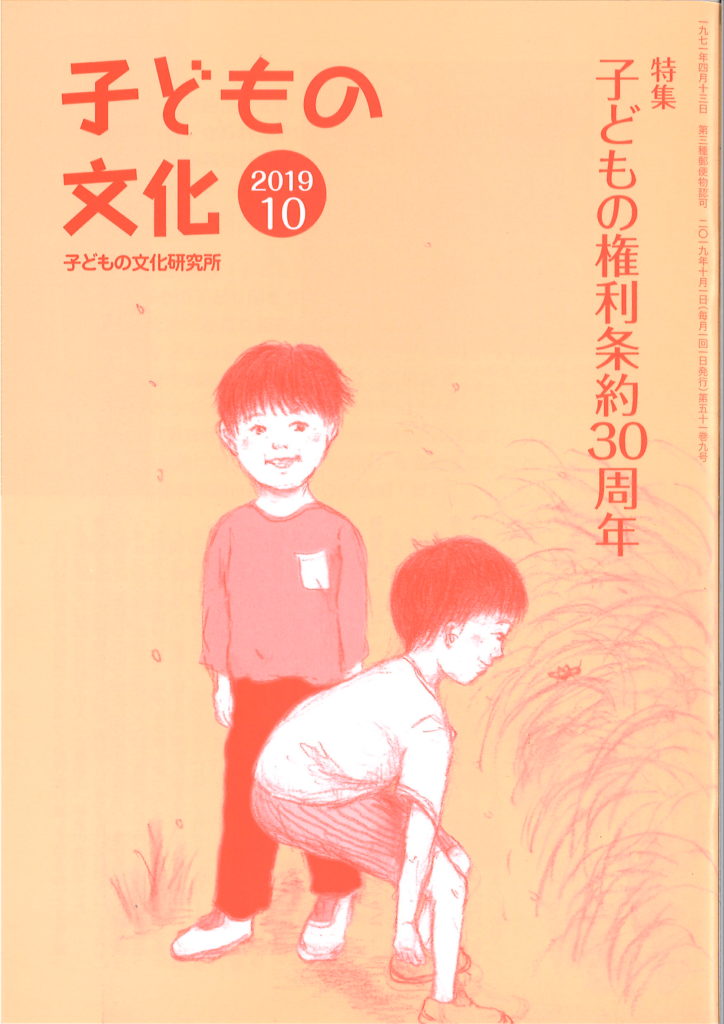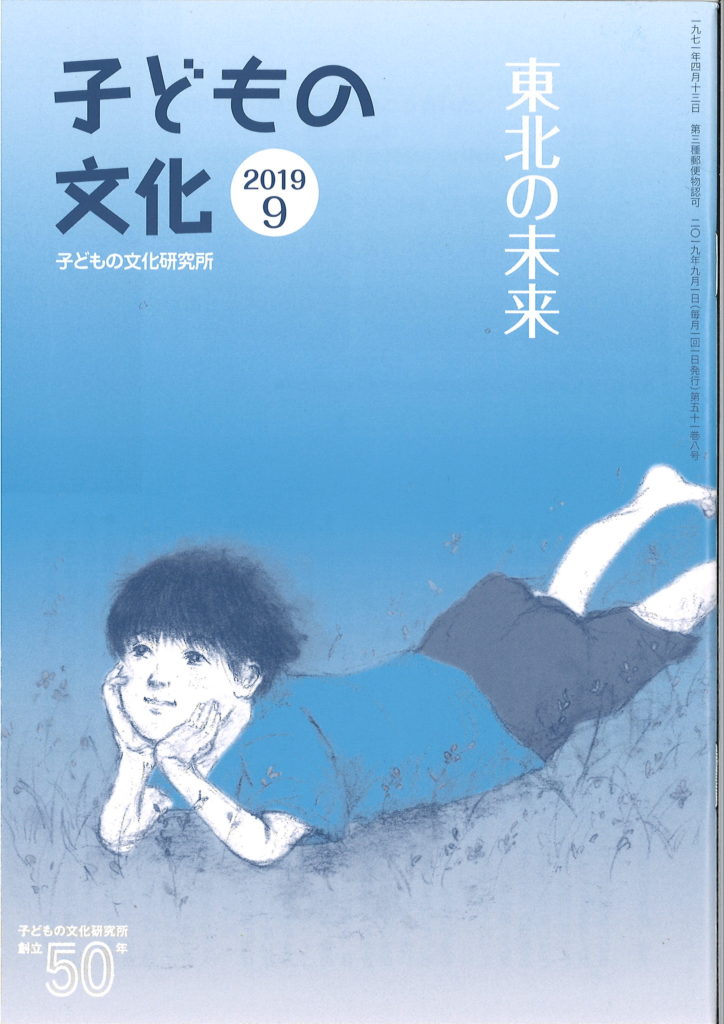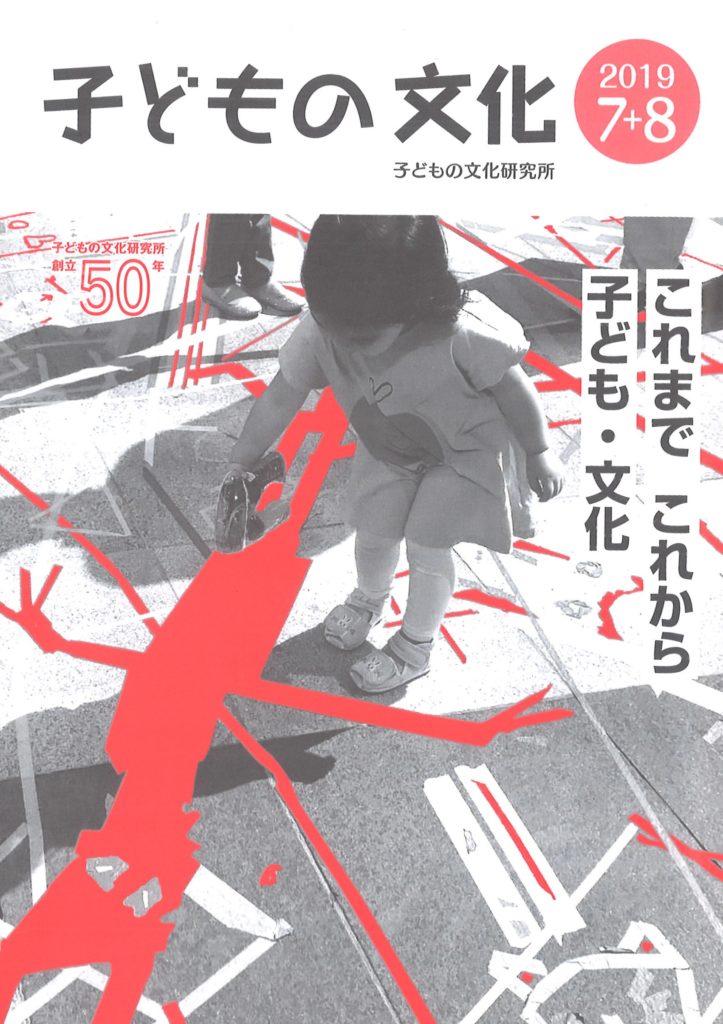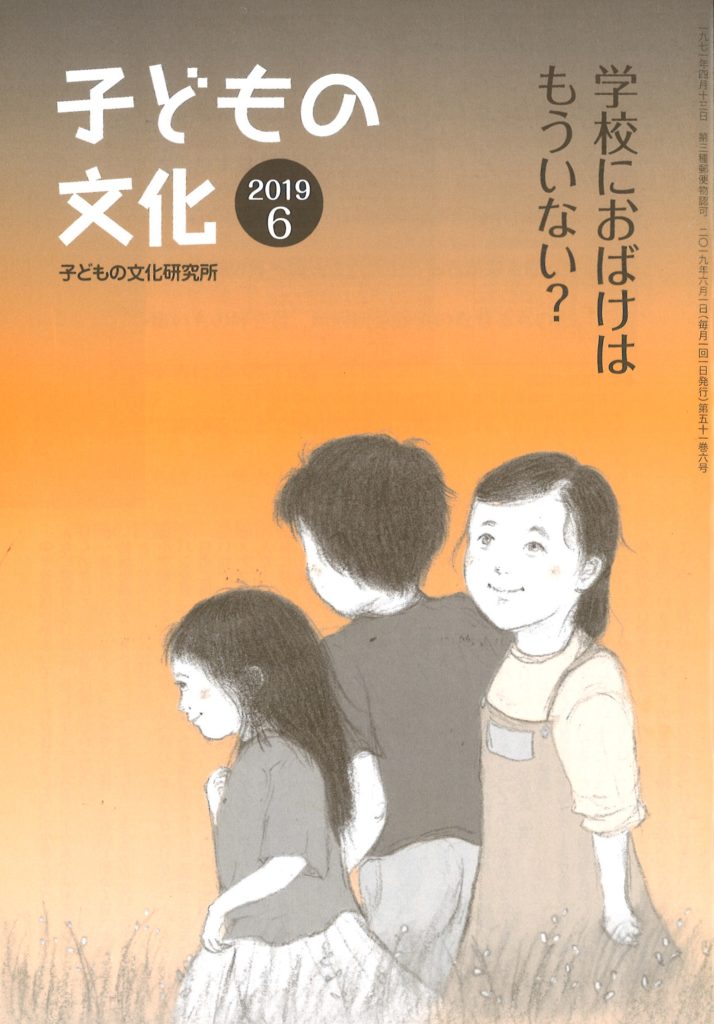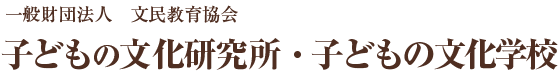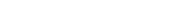月刊子どもの文化・研究子どもの文化
2020年7+8月号
-
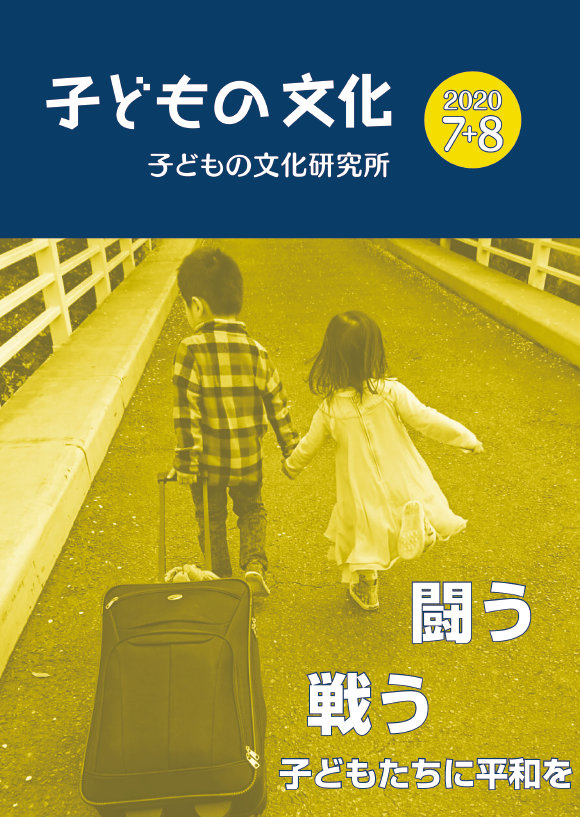
-
2020年7+8月号
5年に1度の戦争特集。オリンピックイヤーとなるはずだった今年は、「たたかう」ということを幅広くとらえ自分の身近な闘いや戦いについて執筆して頂きました。難民を救うために闘う若者たち、差別と向き合い闘う若者たち、書籍から存在が知られてきた模擬原爆のパンプキン。目に見えないウイルスの脅威と闘う今、わたしたちの身近なところにも戦争の種になるかもしれない大きな問題がたくさん潜んでいることに気づかされます。「この悲劇を2度と繰り返さない」ために、戦争の歴史を語り継ぐだけでなく、今起きている問題にも目を向た、どの世代にも読んでほしい夏の合併号です。
2020年6月号
-
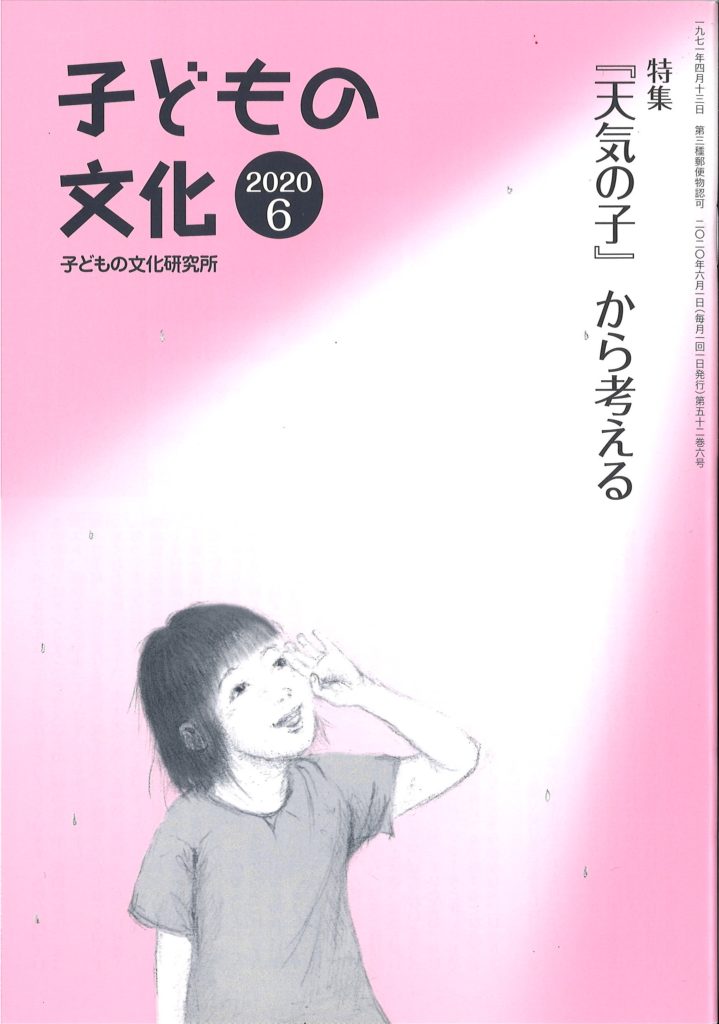
-
2020年6月号
新海誠監督の話題作『天気の子』は、我々にたくさんのことを投げかけている。作品のおもしろさ、新海監督の他の作品との比較、環境問題から隣の人の話題まで快眠談義と称して血気盛んなワニザメ党の青年3人がざっくばらんに語ります。他にも科学読物研究会副運営委員長の市川雅子先生が天気や気象の子どもの本を紹介します。
2020年5月号
-
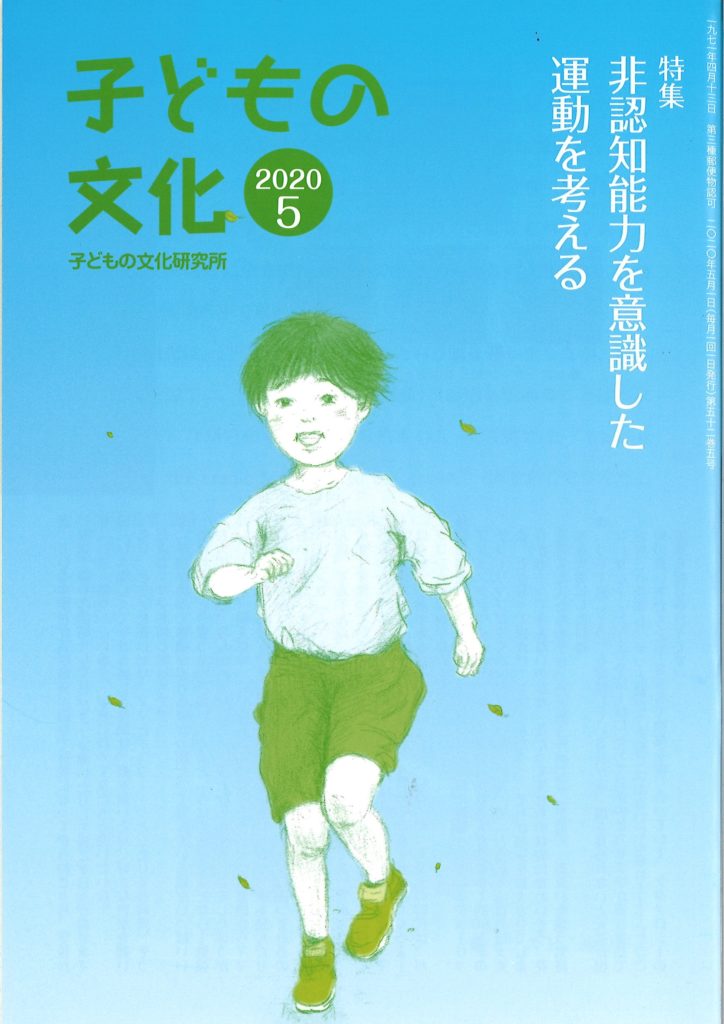
-
2020年5月号
子どもの運動能力をどう発達させるか―それは総合的な学びとして運動遊びをとらえていくこと。その具体例を長年子どもの遊びと運動を実践してきた菊池一英先生と島本一男先生が提起します。広大な里山にある東京ゆりかご幼稚園園長内野彰裕先生とサーキット遊びを展開する片山喜章先生の実践は目からウロコ!ぜひ手にとってお読みください。
2020年4月号
-
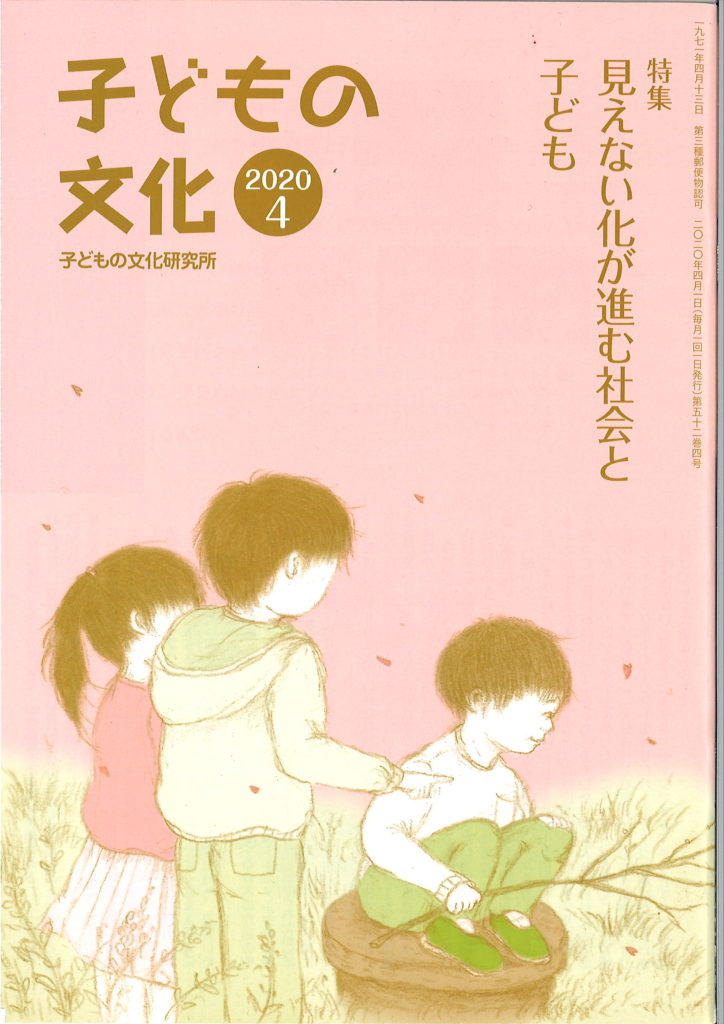
-
2020年4月号
労働やお金、ショービジネス、交友関係など今までは当たり前に目に見えていたものが、キャッシュレスやSNSなどの普及でそのやりとりは目には見えなくなっています。
子どもたちがこれから過ごす社会はさらに、‶見えない化”が進むことでしょう。お店ごっこではレジの人と会話をせずに、お金を置いて去っていく。現場では、そんな光景も見えるようになってきました。キャッシュレス社会から見る世界の動向と、子どもたちの様子、切っても切り離せないSNSとの付き合い方と可能性、子どもたちが生きるこれからの社会をみすえる特集です。
2020年3月号
-
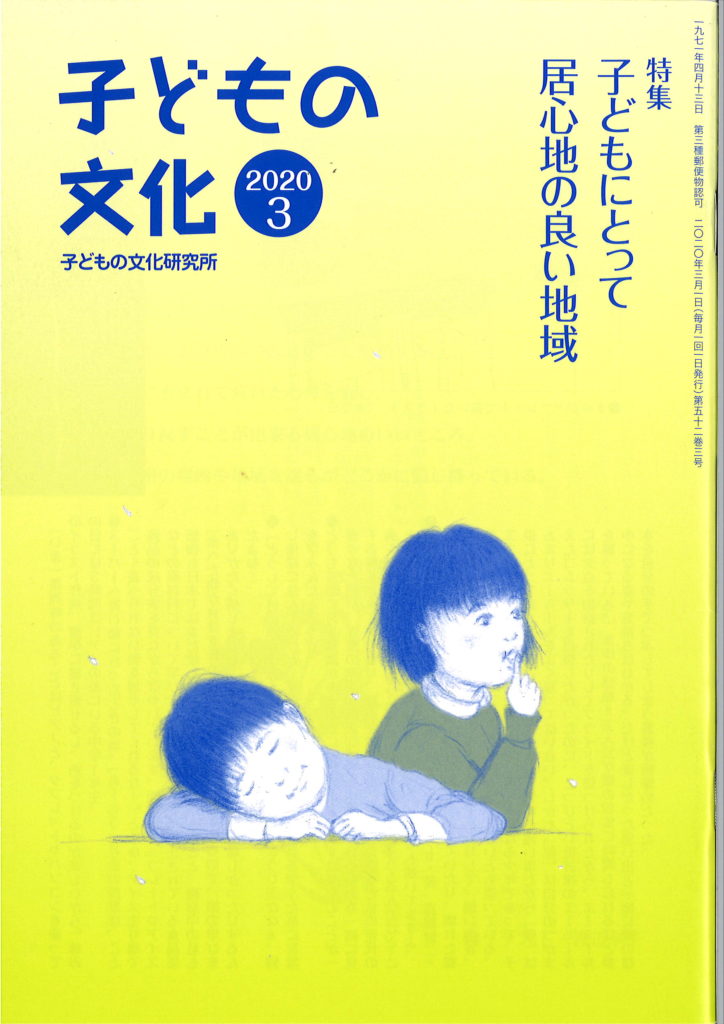
-
2020年3月号
多様な人たちがかかわって地域を元気にする手法「ローカルガバナンス」そのためには、住民、NPO、企業などの団体や個人が地域経営にかかわることが求められます。そんなローカルがバンスを保育でとらえる特集です。子どもたちに「なんだか居心地が良い」と思ってもらえるような場所づくりに求められるものはなんでしょうか。居心地の良い保育園や幼稚園、子ども園は保護者にとっても、保育者にとっても、地域福祉にとっても居心地の良い場所につながるのではないでしょうか。
2020年2月号
-
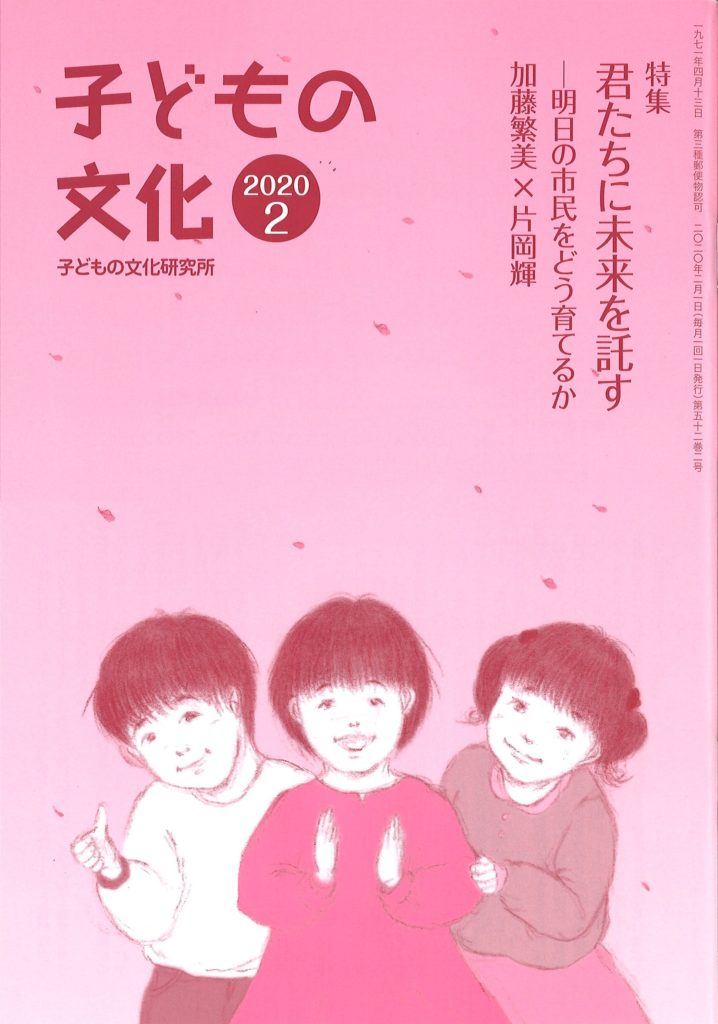
-
2020年2月号
子どもの文化50周年講演とトークの集いから「君たちに未来を託す―明日の市民をどう育てるか― 加藤繁美×片岡輝」の対談を収録。AI時代は子どもの方が大人の先に行くともいわれる中、これからの時代に大事なことは何か。子どもの権利を中心に子どもの意見を大切にしながら、文化の担い手として育ていくには何が大切なのか。童謡作家でもあり、詩人でもある当研究所所長の片岡輝と、文化学校長であり、幼児教育の専門家でもある加藤繁美による保育や教育のみならず、子育てや未来に関わる大事なヒントが満載の子どもに関わる全ての人に読んでもらいたい対談です。
2020年1月号
-
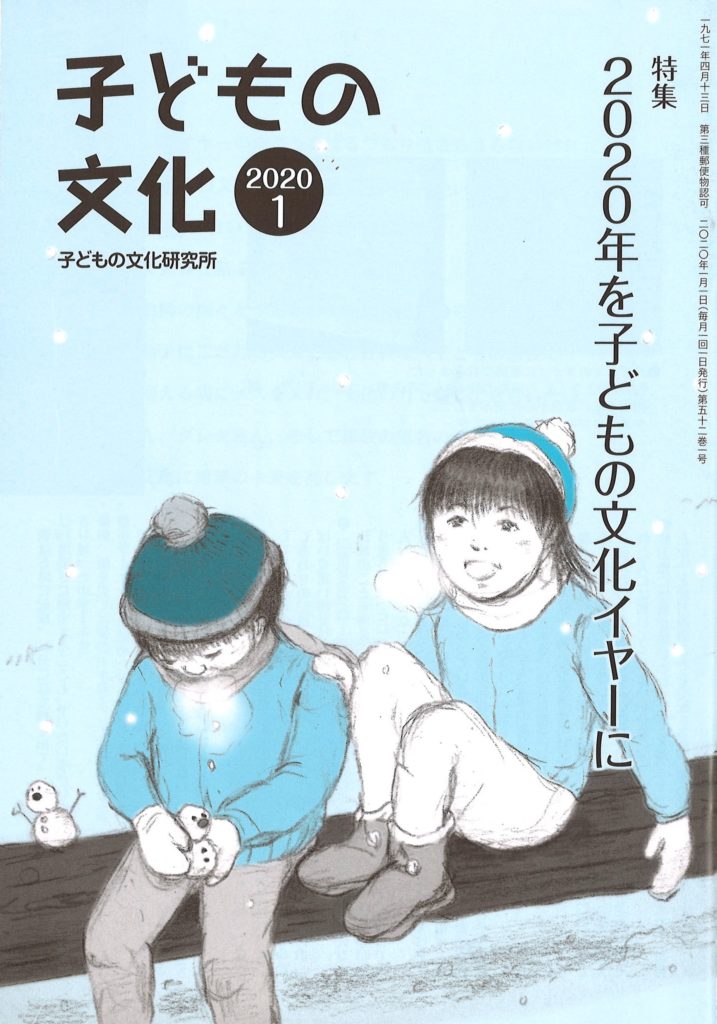
-
2020年1月号
絵本・人形劇・紙芝居と子どもの文化が今、新たな局面を迎えています。子どもの文化で世界中の輪をつなぎ、交流していきたいという決意の子どもの文化研究所51年目のスタートを飾る1月号です。地球の未来を託す子どもたちの感性を育て、大きな文化の花を咲かせたい。そんな気持ちで頑張る皆さんの活動をこれからの課題を報告していただきました。
2019年11+12月特別合併号<50周年記念誌>
-
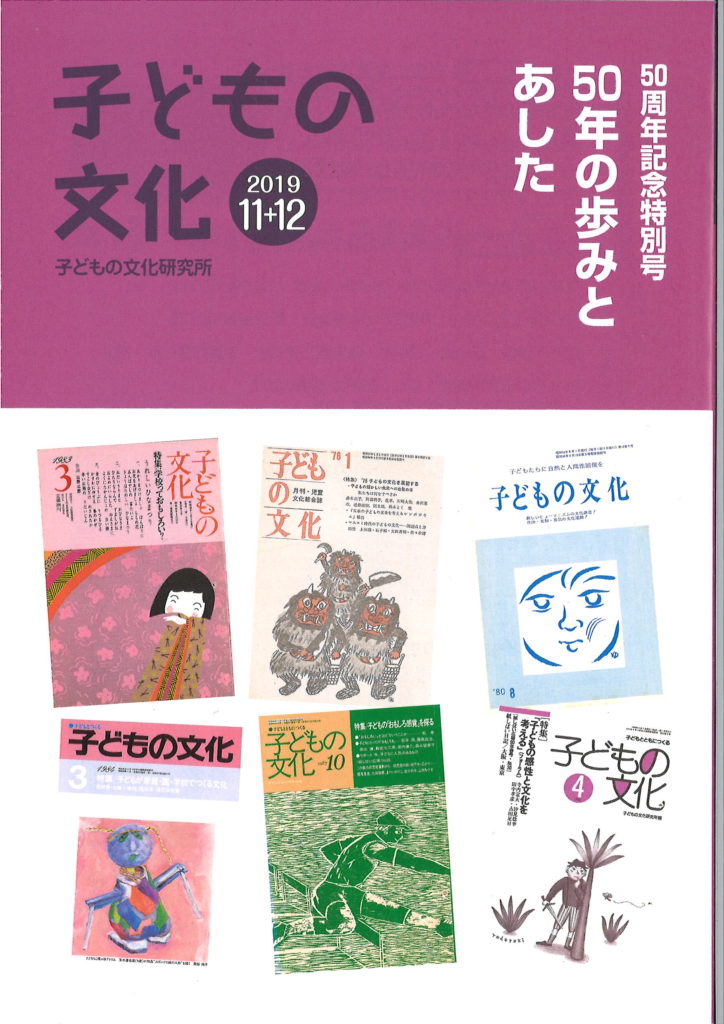
-
2019年11+12月特別合併号<50周年記念誌>
1969年に創立された子どもの文化研究所は、11月で50周年を迎えます。その50年の歴史をあますところなく網羅し、この先子どもの文化・保育について語ります。216頁の大ボリュームの一冊。
創刊号~現在までの総目次一覧や、研究所創立から今までの活動をふり返った年表に、長く研究所に関わって下さっている汐見先生に、これからの課題について語って頂きました。
2019年10月号
-
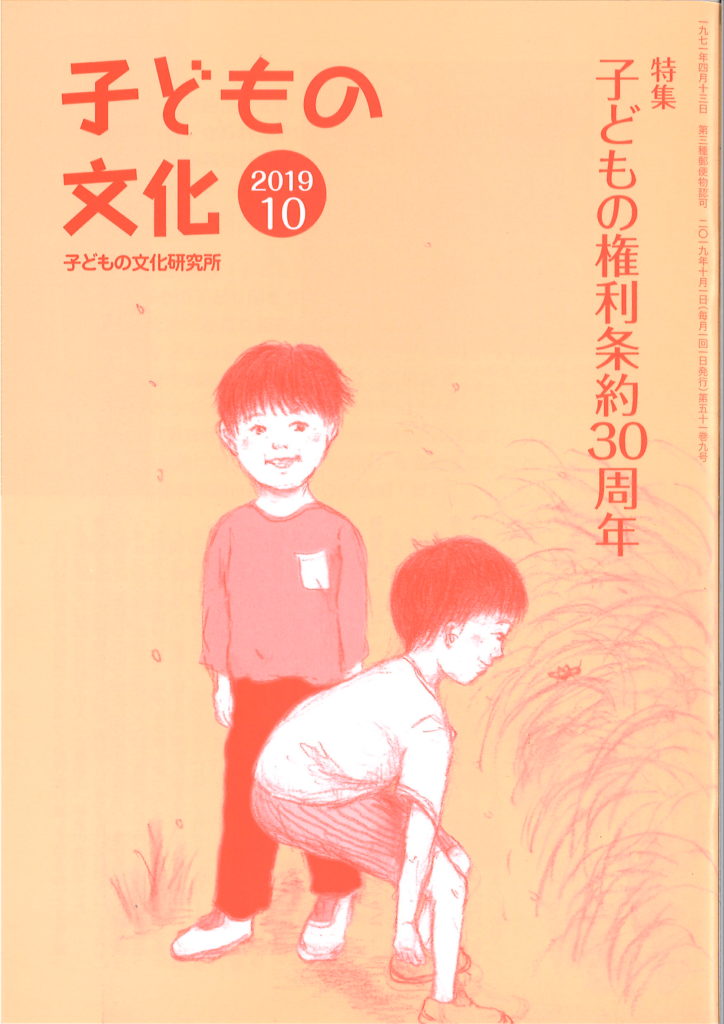
-
2019年10月号
「子どもの権利条約」が国連で採択されてから今年で30年を迎えます。そんな中、今の時代を生きる子どもたちは、守られ安全な日々を過ごしているといえるのでしょうか。
先のみえない時代の中で、子ども達の未来を保障するために我々にできることを考える特集となりました。
保育の現場からは吉葉先生・島本先生に、里親制度の側面からは自身も里親としてたくさんの子どもたちを育ててきた青葉さん、弁護士として常に子どもの立場に立って子どもの権利の弁護活動をしている児玉先生にご執筆頂きました。日常から意識を変えていく、人間はあらゆる命と対等であることを訴える一冊です。
2019年9月号
-
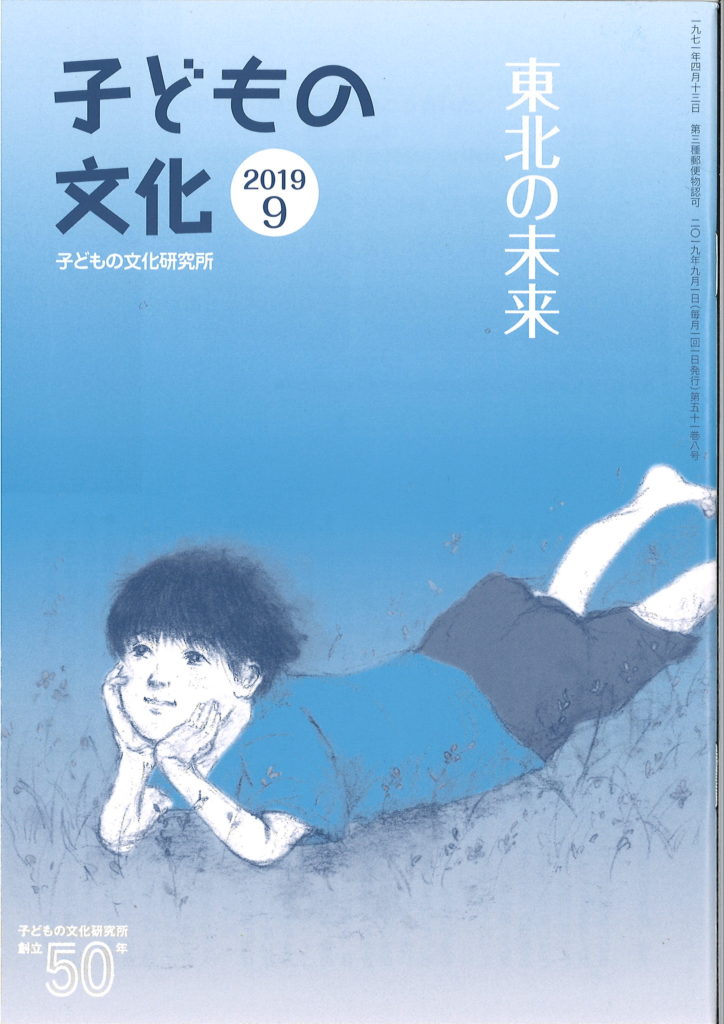
-
2019年9月号
東日本大震災から8年、岩手・宮城・福島で子どもたちの活動をしている3人の方に今の現状を書いていただきました。
そこには、今年になってようやく校庭から撤去された汚染土など、まだまだ課題があることに気づかされます。
子どもの文化を中心に、これから育つ子どもたちが「ふるさとを大好き」に「安心して帰ってこれる場所」になれるよう、真剣に取り組む活動の様子を特集しました。
2019年7+8月号
-
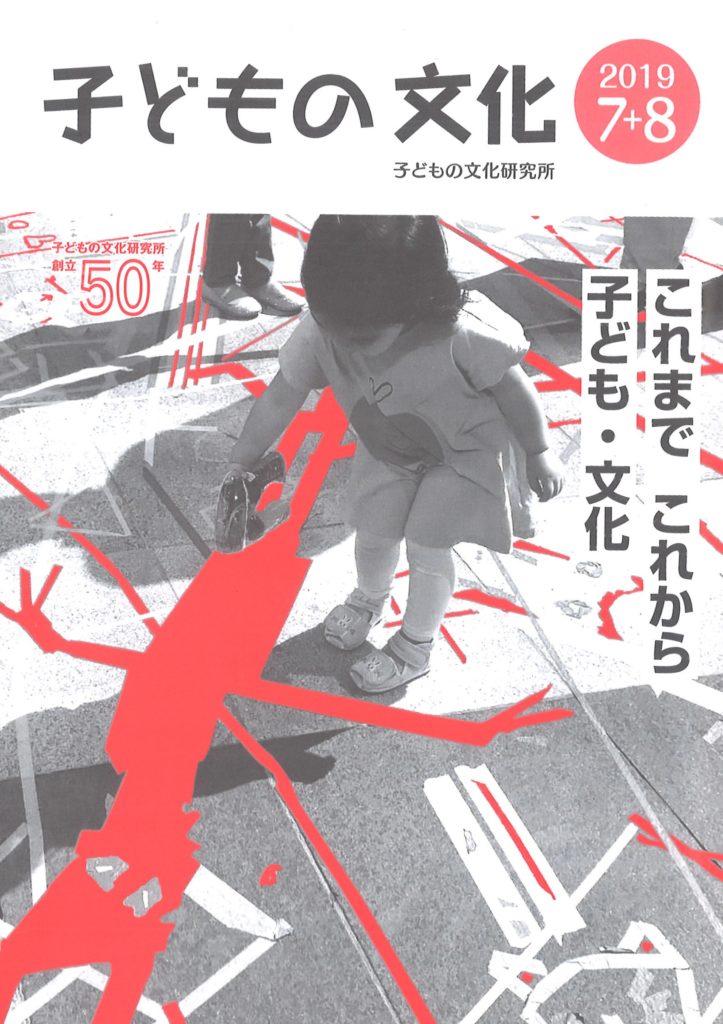
-
2019年7+8月号
子どもの文化の普及・調査・研究と、新たな子ども文化の創造を目的として子どもの文化研究所が設立されてから今年で50年。
子どもが幸せに生きる社会の実現を志向し、「児童の世紀」といわれた20世紀を経て、21世紀は「子どもの文化を守る」世紀から、「子どもの生活を守る」世紀へと後退しているのではないでしょうか。
この特集では、教育・保育、子育て、生活、文化の4側面から、これまでの50年を振り返り、子どもや大人、そして社会がどのように変わったのか、今後、どのように進んでいくのかを探ります。
2019年6月号(品切れ)
-
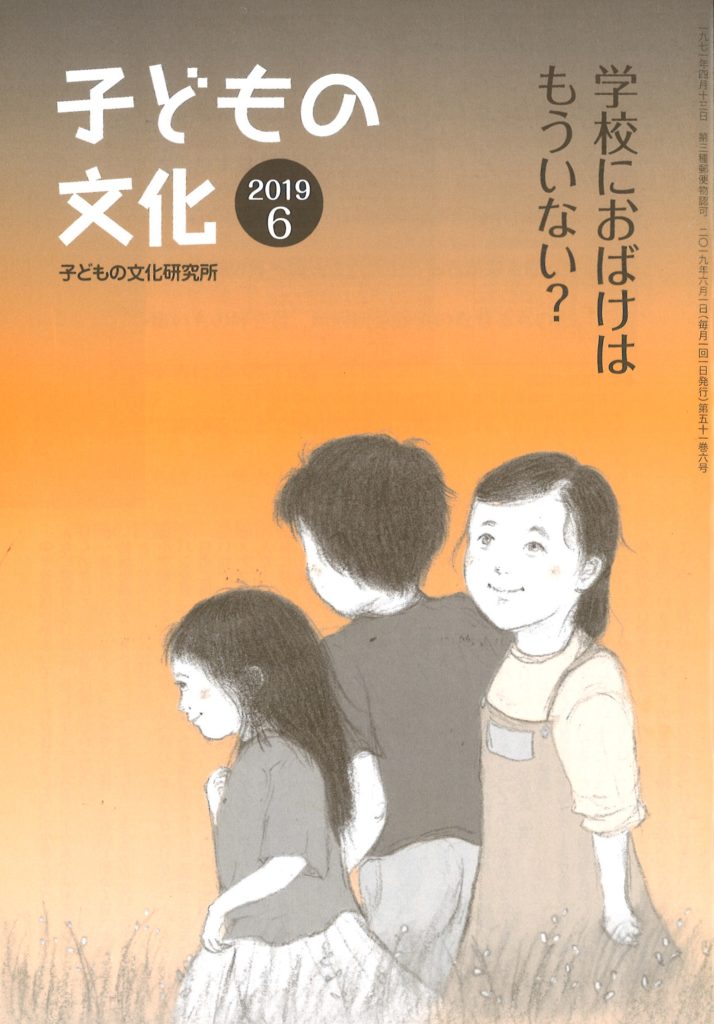
-
2019年6月号(品切れ)
学校の怪談は、1990年代多くの学校でささやかれていましたが、時代の変化とともに、綺麗に建て替えられた校舎で本当に怪談はささやかれなくなったのでしょうか?それは学校が子どもの生活の場所として、大きく変化してしまったから?様々な観点から、学校の怪談について考えます。「学校の怪談」ブームの火付け役、ポプラ社シリーズ『学校の怪談』編集委員の米屋さんや飯倉先生の日本独自の文化風土だという「学校の怪談」の論考などそのルーツと文化を考える1冊になりました。ぜひお読みください。